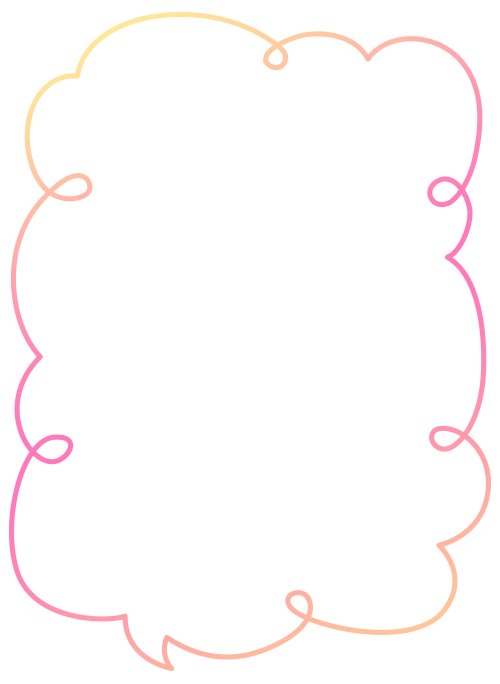それから、どれくらい眠り続けていたのだろうか。
「気づいたか?」
ゆっくりと目を開けると、今までに感じたことの無い息苦しさがあった。
目が覚めた時には、私は人工呼吸器に繋がっていて、身体中には色んな機械と点滴が繋がっていた。
声が出せず、その悔しさから目から一筋の涙が流れていた。
「ごめんな。まだ呼吸状態も悪いからその管は外せないんだ。
きっと、この管を使うのは汐帆ちゃんにとっては初めてだよな。
1週間前、ここの看護師が君を見つけてここに運んできてくれたんだ。
その事は覚えてるかな?」
私は、先生の言葉に頷いた。
「よかった。脳には支障が出てないみたいだな。
俺のことは覚えているか?」
たしか、この人はきっと私が倒れた時の午前中に保健室にきた医者。
はっきりと覚えているため、同じように頷いた。
「これからの事は、その管が取れて呼吸状態が回復してから話そう。
とりあえず今は、ここでゆっくり身体を休めて。」
こんな状態で、病院を抜け出せるはずもない。
正直、1週間も眠っていたなんて思いもよらなかった。
バイトのシフトも随分入れていたのにな…
バイトの人達にも迷惑をかけてしまった。
だけど…
きっとどこかで、こうなることも分かっていた。
小児科にいる時、私を診てくれた山城先生が、重篤な発作になった時にはこういう機械が必要になることもある。
だから、ここを退院してからも定期検診はちゃんと受けるように言われていた。
小児科を退院したから半年間、通院しなかった反動が今こうしてきたんだろうな。
ちょうど良かったのかもしれない…
きっと、心のどこかで休みたい気持ちがあったのかもしれないから…
私は、再び重い瞼を閉じて深い眠りへと落ちていった。