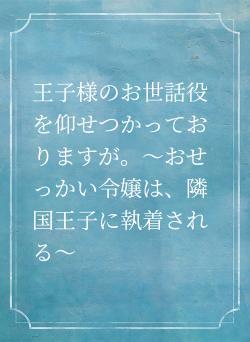「ル……ルドヴィック殿下……!!」
「ああ、エレオノーラ……やっと君に会えた気がする」
「え?」
「こちらを見て。もっと君を見せてくれないか」
とてもじゃないが、頭が追いつかない。
ついこの間まで『婚約解消直前』と揶揄されるほど、冷遇されていたのではなかっただろうか。
ルドヴィックはエレオノーラの頬を支えると、その顔を間近から顔をのぞきこんだ。その眼差しは嘘のように柔らかいものだった。
「エレオノーラ、綺麗だ」
「と、突然どうされたのですか。ルドヴィック殿下」
「……今、私が怖いか」
「え……?」
視界いっぱいにルドヴィックがいるなんて。こうして真正面から彼と向かい合ったのは、いつぶりだろう。
大人になった。高い鼻に、切れ長の瞳。背も見上げるほど高くなって、喉仏も大きな手も、大人の男である証明だと言える。
それでもエレオノーラには、彼の端正な目鼻立ちの中に太陽のような面影が見えた。それは思い出の中に生きる、ルドヴィックの笑顔で――
「いえ……驚きはしましたけど、怖くはありません。どちらかと言えば、いつものように冷たいルドヴィック殿下のほうが、よっぽど怖くて」
「……そうか、すまない」
「今は少し、なつかしく思います」
まるで昔に戻ったようだった。笑い合ったあの頃の距離感を思い出して、ほんのりと胸が温かくなる。
こうして、ルドヴィックと普通に話せることが嬉しくて。我慢できず、安心しきった頬は自然と緩んだ。
そんなエレオノーラを見下ろすルドヴィックは、ゴクリと大きく喉を鳴らす。そのうえ小声で「可愛いすぎる……」と呟くので、エレオノーラは彼こそが可愛らしいと思ってしまった。
「私はあの時、何故……」
「ルドヴィック殿下?」
「――やはり、君が怖がったからといって封印などすべきではなかった」
「封印? この、小箱についてなにか……」
ルドヴィックはこの小箱について、なにか知っているようだった。けれどそのことを尋ねようとしたその時、エレオノーラの視界がグラリと揺れる。
次第に、目の前の彼とあどけない少年時代のルドヴィックが重なってゆく。
ブレる視界に思考を奪われ、エレオノーラは彼の腕の中で、まどろむ意識を手放した。
「ああ、エレオノーラ……やっと君に会えた気がする」
「え?」
「こちらを見て。もっと君を見せてくれないか」
とてもじゃないが、頭が追いつかない。
ついこの間まで『婚約解消直前』と揶揄されるほど、冷遇されていたのではなかっただろうか。
ルドヴィックはエレオノーラの頬を支えると、その顔を間近から顔をのぞきこんだ。その眼差しは嘘のように柔らかいものだった。
「エレオノーラ、綺麗だ」
「と、突然どうされたのですか。ルドヴィック殿下」
「……今、私が怖いか」
「え……?」
視界いっぱいにルドヴィックがいるなんて。こうして真正面から彼と向かい合ったのは、いつぶりだろう。
大人になった。高い鼻に、切れ長の瞳。背も見上げるほど高くなって、喉仏も大きな手も、大人の男である証明だと言える。
それでもエレオノーラには、彼の端正な目鼻立ちの中に太陽のような面影が見えた。それは思い出の中に生きる、ルドヴィックの笑顔で――
「いえ……驚きはしましたけど、怖くはありません。どちらかと言えば、いつものように冷たいルドヴィック殿下のほうが、よっぽど怖くて」
「……そうか、すまない」
「今は少し、なつかしく思います」
まるで昔に戻ったようだった。笑い合ったあの頃の距離感を思い出して、ほんのりと胸が温かくなる。
こうして、ルドヴィックと普通に話せることが嬉しくて。我慢できず、安心しきった頬は自然と緩んだ。
そんなエレオノーラを見下ろすルドヴィックは、ゴクリと大きく喉を鳴らす。そのうえ小声で「可愛いすぎる……」と呟くので、エレオノーラは彼こそが可愛らしいと思ってしまった。
「私はあの時、何故……」
「ルドヴィック殿下?」
「――やはり、君が怖がったからといって封印などすべきではなかった」
「封印? この、小箱についてなにか……」
ルドヴィックはこの小箱について、なにか知っているようだった。けれどそのことを尋ねようとしたその時、エレオノーラの視界がグラリと揺れる。
次第に、目の前の彼とあどけない少年時代のルドヴィックが重なってゆく。
ブレる視界に思考を奪われ、エレオノーラは彼の腕の中で、まどろむ意識を手放した。