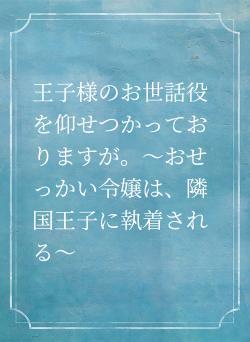白い花をモチーフにした、可愛らしい指輪だ。
デザインを見たところ、これは子供用なのだろうか。けれどしっかりと金で出来ており、白く見えた花のモチーフも、よく見ればオパールで出来ている。それなり高価な指輪であることは間違いない。
「……指輪だわ?」
「何の変哲もない指輪……ですね。見たところ、呪いの類いも見受けられません」
「良かった……! 封印されていたと聞いて、もし恐ろしいものが出てきたらどうしようかと思っていたのです」
「なぜこの指輪が封印されていたのでしょうか。エレオノーラ、心当たりは」
「さあ……愛らしい指輪ですが……」
戸惑いながらもホッと胸をなでおろす二人は、小箱が開いたことで忘れていた。
背後に怒りのルドヴィックがいたことを。
「……エレオノーラ」
彼の声に、やっと意識は引き戻された。いつの間にか、ルドヴィックはすぐ後ろまで来ていたらしい。
そういえば、彼は怒っていたのだ。なのに王子そっちのけでセルギウスと盛り上がったりして、火に油を注いだに違いない。
エレオノーラは振り向きざま、急いで頭を下げた。
「で……殿下、申し訳ありません! 実はたった今、この小箱が勝手に開きまして、それで中には指輪が――」
「エレオノーラ」
こちらへ伸ばされる腕に、切なげな声。
突然、エレオノーラは抱きしめられた。
前触れのない抱擁に、息も思考も停止する。
「殿下……?」
信じられない。
しかし身体を包み込むこの腕、頬に感じるたくましい胸は、間違いなくルドヴィック王子のものだった。
彼は何度もエレオノーラの名を呼びながら、細い身体を抱きしめる。そしてひどく甘美なものを味わうかのように白い首筋へ顔を埋めると、大きく息を吸いこんだ。
「エレオノーラ」
彼の息づかいや低い声が、首筋にビリビリと伝わって。エレオノーラは耐えられず身じろぎをするけれど、いっそう強く抱きしめられた。まるで、逃がさないとでも言うように。
デザインを見たところ、これは子供用なのだろうか。けれどしっかりと金で出来ており、白く見えた花のモチーフも、よく見ればオパールで出来ている。それなり高価な指輪であることは間違いない。
「……指輪だわ?」
「何の変哲もない指輪……ですね。見たところ、呪いの類いも見受けられません」
「良かった……! 封印されていたと聞いて、もし恐ろしいものが出てきたらどうしようかと思っていたのです」
「なぜこの指輪が封印されていたのでしょうか。エレオノーラ、心当たりは」
「さあ……愛らしい指輪ですが……」
戸惑いながらもホッと胸をなでおろす二人は、小箱が開いたことで忘れていた。
背後に怒りのルドヴィックがいたことを。
「……エレオノーラ」
彼の声に、やっと意識は引き戻された。いつの間にか、ルドヴィックはすぐ後ろまで来ていたらしい。
そういえば、彼は怒っていたのだ。なのに王子そっちのけでセルギウスと盛り上がったりして、火に油を注いだに違いない。
エレオノーラは振り向きざま、急いで頭を下げた。
「で……殿下、申し訳ありません! 実はたった今、この小箱が勝手に開きまして、それで中には指輪が――」
「エレオノーラ」
こちらへ伸ばされる腕に、切なげな声。
突然、エレオノーラは抱きしめられた。
前触れのない抱擁に、息も思考も停止する。
「殿下……?」
信じられない。
しかし身体を包み込むこの腕、頬に感じるたくましい胸は、間違いなくルドヴィック王子のものだった。
彼は何度もエレオノーラの名を呼びながら、細い身体を抱きしめる。そしてひどく甘美なものを味わうかのように白い首筋へ顔を埋めると、大きく息を吸いこんだ。
「エレオノーラ」
彼の息づかいや低い声が、首筋にビリビリと伝わって。エレオノーラは耐えられず身じろぎをするけれど、いっそう強く抱きしめられた。まるで、逃がさないとでも言うように。