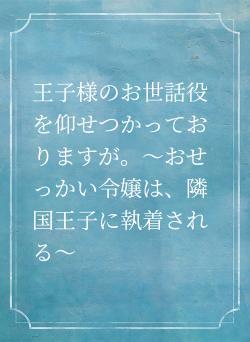「――この箱は、ルドヴィック殿下のものだったのですね」
「そうだ。私も先程思い出したところだが」
「何かが封印されていたようですけれど」
「ああ。この箱には私の、その……劣情が封印されていた」
「劣情」
この人は突然、何を言い出すのだろう。
言葉を失うエレオノーラに、ルドヴィックは深刻な顔で弁解をする。
「今……私を軽蔑しただろう」
「いえ、その、反応に困って」
「いや、軽蔑されても仕方がない。けどな、当時は一刻を争う事態だったんだ!」
ルドヴィックは顔を青くしたまま当時を振り返る。
十三歳の彼といったら、寝ても醒めてもエレオノーラのことばかりを想う少年だった。
しかも念願叶って婚約が結ばれた。そうなるともう、彼女を前にルドヴィックの青い理性など全く役に立たなかった。
そして堪え性の無いルドヴィックは、尊いエレオノーラを怖がらせてしまった。あの、キス未遂事件である。
けれど彼女への欲求は募るばかり。
そばに居たいのに、エレオノーラへの衝動を止められない。悶々とした日々を過ごすうちに、見つけたのだ。この欲を抑える方法を。
「古い魔術書に書いてあったんだ。感情を抑える方法が」
「え……まさかそんな魔術があるなんて」
「はるか昔は、罪人にこの魔術を施していたらしい」
「そんな……」
エレオノーラを怖がらせる人間など、罪人と変わらない。
そう思い詰めた十三歳のルドヴィックは、魔術書と共に高名な魔術師の元を訪ねた。そして持て余した欲求を、この小箱へと封印したのだという。
「そうだ。私も先程思い出したところだが」
「何かが封印されていたようですけれど」
「ああ。この箱には私の、その……劣情が封印されていた」
「劣情」
この人は突然、何を言い出すのだろう。
言葉を失うエレオノーラに、ルドヴィックは深刻な顔で弁解をする。
「今……私を軽蔑しただろう」
「いえ、その、反応に困って」
「いや、軽蔑されても仕方がない。けどな、当時は一刻を争う事態だったんだ!」
ルドヴィックは顔を青くしたまま当時を振り返る。
十三歳の彼といったら、寝ても醒めてもエレオノーラのことばかりを想う少年だった。
しかも念願叶って婚約が結ばれた。そうなるともう、彼女を前にルドヴィックの青い理性など全く役に立たなかった。
そして堪え性の無いルドヴィックは、尊いエレオノーラを怖がらせてしまった。あの、キス未遂事件である。
けれど彼女への欲求は募るばかり。
そばに居たいのに、エレオノーラへの衝動を止められない。悶々とした日々を過ごすうちに、見つけたのだ。この欲を抑える方法を。
「古い魔術書に書いてあったんだ。感情を抑える方法が」
「え……まさかそんな魔術があるなんて」
「はるか昔は、罪人にこの魔術を施していたらしい」
「そんな……」
エレオノーラを怖がらせる人間など、罪人と変わらない。
そう思い詰めた十三歳のルドヴィックは、魔術書と共に高名な魔術師の元を訪ねた。そして持て余した欲求を、この小箱へと封印したのだという。