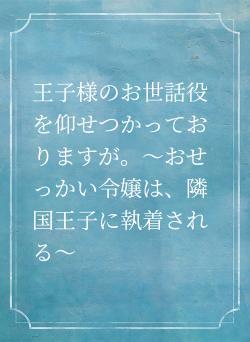◇◇◇
エレオノーラは、夢を見た。
二人の婚約が結ばれた、特別な日の夢だった。
ようやく正式に婚約者同士となったエレオノーラとルドヴィックは、幸せの絶頂にあったのだが。
「やだっ……!」
鮮やかな花が咲き誇る、王城のテラス。
十二歳のエレオノーラは、ルドヴィックの胸を力いっぱい押し返した。倒れ込んだ彼の手からは、エレオノーラのために用意した指輪がコロコロと転がり落ちる。
当時は今と違って、二人の体格もさほど変わらず、華奢なエレオノーラでも彼を突き飛ばすことくらいは出来てしまう。
床に尻もちをついたルドヴィックの、見開かれた碧い瞳が小刻みに震えた。まさか口付けを拒絶されるとは思ってもみなかったのだろう。いきなりの事でとっさに拒んでしまったけれど、彼の深く傷付いた目を見れば罪悪感がエレオノーラを襲った。
「あっ……ご、ごめんなさい、私」
「……嫌だったか?」
「嫌ではありません、でも」
「怖かったのか……?」
ルドヴィックの問いかけに、エレオノーラは否定もできず頷いた。
彼のことは大好きだった。いつも優しくて、格好良くて、一緒にいると楽しくて。エレオノーラには、ルドヴィックだけが誰よりも輝いて見えた。政略結婚にも関わらず、こんなにも好きな人と結婚できるだなんて、本当に夢のよう話だった。
しかし、それとこれとは話が別なのだ。
びっくりした。怖かった。いつも太陽のように明るいルドヴィックが、別人のように見えたのだ。
相手が愛しい人とはいえ、何も心の準備が出来ないまま口付けを受け入れるなんて、到底無理なことだった。まだ子供のエレオノーラには。
「あの、少し、待っていただけませんか」
「少し……?」
「はい、どうか……私が大人になるまでは」
花でいっぱいのテラスは美しくて、婚約を祝福するかのような眩しい光に溢れているというのに。
二人の間にはこれ以上無く気まずい空気が流れた。エレオノーラはなにも話すことが出来なくて、ルドヴィックを見ることもないまま立ち尽くす。その後どのように過ごしたのか、どうやって帰路に着いたのかも覚えていない。
そうして、婚約したばかりの二人によるファーストキスは未遂に終わった。
ルドヴィック十三歳、エレオノーラ十二歳の、失われていた思い出だ。
◇◇◇
エレオノーラは、夢を見た。
二人の婚約が結ばれた、特別な日の夢だった。
ようやく正式に婚約者同士となったエレオノーラとルドヴィックは、幸せの絶頂にあったのだが。
「やだっ……!」
鮮やかな花が咲き誇る、王城のテラス。
十二歳のエレオノーラは、ルドヴィックの胸を力いっぱい押し返した。倒れ込んだ彼の手からは、エレオノーラのために用意した指輪がコロコロと転がり落ちる。
当時は今と違って、二人の体格もさほど変わらず、華奢なエレオノーラでも彼を突き飛ばすことくらいは出来てしまう。
床に尻もちをついたルドヴィックの、見開かれた碧い瞳が小刻みに震えた。まさか口付けを拒絶されるとは思ってもみなかったのだろう。いきなりの事でとっさに拒んでしまったけれど、彼の深く傷付いた目を見れば罪悪感がエレオノーラを襲った。
「あっ……ご、ごめんなさい、私」
「……嫌だったか?」
「嫌ではありません、でも」
「怖かったのか……?」
ルドヴィックの問いかけに、エレオノーラは否定もできず頷いた。
彼のことは大好きだった。いつも優しくて、格好良くて、一緒にいると楽しくて。エレオノーラには、ルドヴィックだけが誰よりも輝いて見えた。政略結婚にも関わらず、こんなにも好きな人と結婚できるだなんて、本当に夢のよう話だった。
しかし、それとこれとは話が別なのだ。
びっくりした。怖かった。いつも太陽のように明るいルドヴィックが、別人のように見えたのだ。
相手が愛しい人とはいえ、何も心の準備が出来ないまま口付けを受け入れるなんて、到底無理なことだった。まだ子供のエレオノーラには。
「あの、少し、待っていただけませんか」
「少し……?」
「はい、どうか……私が大人になるまでは」
花でいっぱいのテラスは美しくて、婚約を祝福するかのような眩しい光に溢れているというのに。
二人の間にはこれ以上無く気まずい空気が流れた。エレオノーラはなにも話すことが出来なくて、ルドヴィックを見ることもないまま立ち尽くす。その後どのように過ごしたのか、どうやって帰路に着いたのかも覚えていない。
そうして、婚約したばかりの二人によるファーストキスは未遂に終わった。
ルドヴィック十三歳、エレオノーラ十二歳の、失われていた思い出だ。
◇◇◇