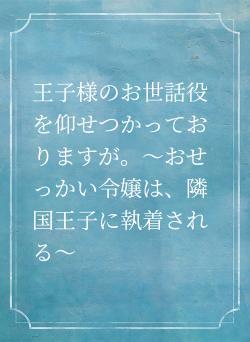「私、いいと思ったのになあ。お兄様とフィーナの結婚」
「こら、チェリ。もう終わったことを言うのは止めなさい」
フィーナ、ディレット、チェリの三人は、木陰の広がるテラスでお茶の時間を過ごしている。
あれから数日。フィーナの十回目の見合いは、あっさりと幕を閉じた。一見すると、トルメンタ伯爵家には元通りの日々が戻っているようにも見える。
「こうなったのはカミロの自業自得よ。フィーナちゃんには、他にもいい縁談がたくさんあるの。こんなにも良い子なのだから」
「ええー。結婚なんてしないで、ずっとここで暮らせばいいのにぃ」
二人の会話に、フィーナは苦笑いで応えるほか無かった。チェリがいくら望んでくれたとしても、カミロとの縁談はもう終わったのだ。ディレットだって、次の相手を探してくれている。
「お兄様は馬鹿よねぇ。普通に『好きだ!』って言えばよかっただけなのに」
「どうせ、自覚なかったのよ。融通が効かないんだから」
フィーナのことを思ってか、ディレットもチェリも『馬鹿だ』『酷い男だ』とカミロを責めた。それはもう、フィーナが遠慮してしまうくらい手酷く。
当のカミロ本人は、ただ『すまなかった』と謝るだけだった。あの日から彼は早朝に出勤し、深夜に帰宅するという生活を送っている。気を遣っているのだろうか、フィーナの前に姿を見せることは無い。
「こら、チェリ。もう終わったことを言うのは止めなさい」
フィーナ、ディレット、チェリの三人は、木陰の広がるテラスでお茶の時間を過ごしている。
あれから数日。フィーナの十回目の見合いは、あっさりと幕を閉じた。一見すると、トルメンタ伯爵家には元通りの日々が戻っているようにも見える。
「こうなったのはカミロの自業自得よ。フィーナちゃんには、他にもいい縁談がたくさんあるの。こんなにも良い子なのだから」
「ええー。結婚なんてしないで、ずっとここで暮らせばいいのにぃ」
二人の会話に、フィーナは苦笑いで応えるほか無かった。チェリがいくら望んでくれたとしても、カミロとの縁談はもう終わったのだ。ディレットだって、次の相手を探してくれている。
「お兄様は馬鹿よねぇ。普通に『好きだ!』って言えばよかっただけなのに」
「どうせ、自覚なかったのよ。融通が効かないんだから」
フィーナのことを思ってか、ディレットもチェリも『馬鹿だ』『酷い男だ』とカミロを責めた。それはもう、フィーナが遠慮してしまうくらい手酷く。
当のカミロ本人は、ただ『すまなかった』と謝るだけだった。あの日から彼は早朝に出勤し、深夜に帰宅するという生活を送っている。気を遣っているのだろうか、フィーナの前に姿を見せることは無い。