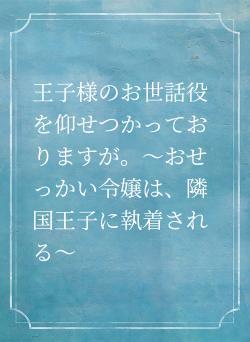「もちろん、結婚願望が薄いまま結ばれる夫婦だっているだろうけど。君はまだ若いだろう? フィーナさんが僕と結婚したとしても、勿体ないだろうと思って」
「……それは、もしかして誰かに指摘されましたか?」
返事を、誘導している自覚はあった。
フィーナの手のひらには汗がにじむ。
「ああ。カミロ様が図書館にいらっしゃって、言われたんだ。『お前はフィーナを幸せに出来るのか』って」
「えっ……」
フィーナは頭が真っ白になった。
まただ。また、カミロがフィーナの縁談に口を出していた。
フィーナの知らないところでなんて失礼なことを言っているのだ。この無礼を、どう詫びれば良いのだろう。
「カミロ様がそんな失礼なことを……本当に申し訳ありませんでした」
「良いんだよ、もう二年も前のことだし。おかげで僕には結婚しない人生もあると分かったからね。本にまみれて暮らしてゆくよ」
清々しいほどに吹っ切れた彼の顔だけが救いだ。フィーナは下げられる頭を思い切り下げてから、図書館を後にしたのだった。
「……それは、もしかして誰かに指摘されましたか?」
返事を、誘導している自覚はあった。
フィーナの手のひらには汗がにじむ。
「ああ。カミロ様が図書館にいらっしゃって、言われたんだ。『お前はフィーナを幸せに出来るのか』って」
「えっ……」
フィーナは頭が真っ白になった。
まただ。また、カミロがフィーナの縁談に口を出していた。
フィーナの知らないところでなんて失礼なことを言っているのだ。この無礼を、どう詫びれば良いのだろう。
「カミロ様がそんな失礼なことを……本当に申し訳ありませんでした」
「良いんだよ、もう二年も前のことだし。おかげで僕には結婚しない人生もあると分かったからね。本にまみれて暮らしてゆくよ」
清々しいほどに吹っ切れた彼の顔だけが救いだ。フィーナは下げられる頭を思い切り下げてから、図書館を後にしたのだった。