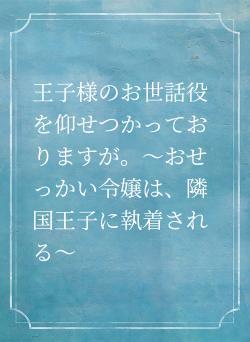気まずさを誤魔化すためにも、フィーナはせっかくのスープをいただくことにした。
会話は無いが、カミロがこの部屋から出ていく気配はない。いや、ここは彼の部屋なのだから、彼がいてもおかしく無いのだが……どうやらフィーナの世話に徹することにしたようである。
しんとした部屋で、ようやくカミロが口を開いた。
「見合い相手とは、いつも何をしていた?」
「え?」
「いつも、見合い相手に会いに行くと出掛けていただろう」
「はい。ただ、すぐ断られてしまうので……特に『何を』していたかと言われたら、何も」
いつも、見合い相手とは昨日のようにカフェで顔合わせをして。しばらくお互いに差し障りのない会話をしたあと、次の約束をした。
次の約束は評判のよいレストランであったり、雰囲気の良い公園であったり、夕方の街をぶらぶらしてみたり。本当に色々だった。
「会って、お話をして……特に、変わったことをしていなくて。前回のお相手とは花畑へ行く約束をしていましたが」
「では、次の休みはその花畑へ行くとしよう」
「え? カミロ様が……私と、ですか?」
「お前以外の誰と行くんだ」
フィーナは想像した。
カミロが腕を組み、花畑の中に立つ。その姿を思い浮かべただけでも違和感があり過ぎた。彼には大自然が似合わない。
なのに彼は本当に行こうとしている。フィーナの見合い話に付き合うために。
「カミロ様……本気なのですか? 花畑ですよ?」
「お前は、行きたかったのだろう」
驚いた。彼はフィーナの気持ちを知っていた。なぜだろう、誰にも『本当は行きたかった』だなんて言っていないのに。
図らずも、カミロと花畑へ行くことになってしまった。
フィーナは困惑を隠せぬまま、温かいスープを味わったのだった。
会話は無いが、カミロがこの部屋から出ていく気配はない。いや、ここは彼の部屋なのだから、彼がいてもおかしく無いのだが……どうやらフィーナの世話に徹することにしたようである。
しんとした部屋で、ようやくカミロが口を開いた。
「見合い相手とは、いつも何をしていた?」
「え?」
「いつも、見合い相手に会いに行くと出掛けていただろう」
「はい。ただ、すぐ断られてしまうので……特に『何を』していたかと言われたら、何も」
いつも、見合い相手とは昨日のようにカフェで顔合わせをして。しばらくお互いに差し障りのない会話をしたあと、次の約束をした。
次の約束は評判のよいレストランであったり、雰囲気の良い公園であったり、夕方の街をぶらぶらしてみたり。本当に色々だった。
「会って、お話をして……特に、変わったことをしていなくて。前回のお相手とは花畑へ行く約束をしていましたが」
「では、次の休みはその花畑へ行くとしよう」
「え? カミロ様が……私と、ですか?」
「お前以外の誰と行くんだ」
フィーナは想像した。
カミロが腕を組み、花畑の中に立つ。その姿を思い浮かべただけでも違和感があり過ぎた。彼には大自然が似合わない。
なのに彼は本当に行こうとしている。フィーナの見合い話に付き合うために。
「カミロ様……本気なのですか? 花畑ですよ?」
「お前は、行きたかったのだろう」
驚いた。彼はフィーナの気持ちを知っていた。なぜだろう、誰にも『本当は行きたかった』だなんて言っていないのに。
図らずも、カミロと花畑へ行くことになってしまった。
フィーナは困惑を隠せぬまま、温かいスープを味わったのだった。