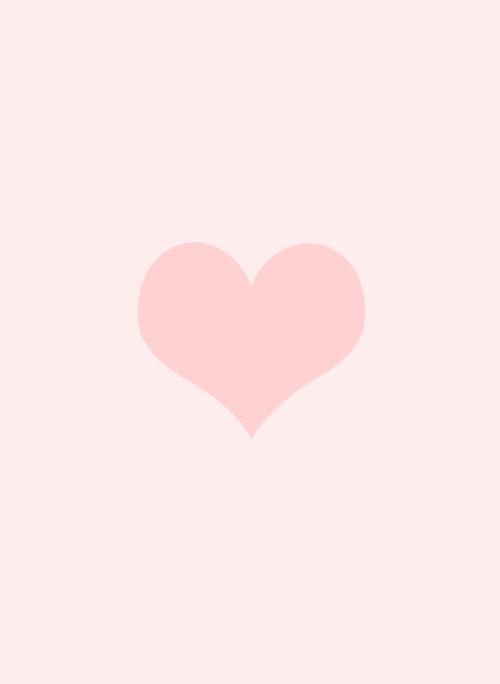(死ぬのって、痛いのかしら。
ああ……でも、奏也に伝えられた。私の本当の気持ち……)
だから悔いはない。
柏崎 紫は、自分の思うままに生きて、自分の思うように死んでいくのだ。
〝現代の悪役令嬢〟は、王子様や他の誰かに処刑されるのではなく、自分の罪を悔いて、自分で罰するのだ。
(短い人生だったけど、奏也と一緒にいられて幸せだった)
屋上から落ちて行く中で、紫は、奏也との思い出の走馬灯を見た。
初めて奏也と会った時、紫は、誰にでもいい顔をして愛想を振りまく奏也のことが実は好きではなかった。
むしろ嫌いな人種だと思った。
どうして他人に自分を合わせる必要があるのか、紫には、理解できなかった。
だから、奏也が紫に遊ぼうと手を差し伸べてきても、いつもその手を突っぱねた。
でも、奏也は、それくらいではへこたれなかった。
どんなに紫がひどいことを言っても、奏也は、いつもにこにこと嬉しそうに笑っていた。
(どうして、いつも笑ってるの?
私にあんなこと言われて、どうして平気なの?
……きっと何もわかってないのね。ばっかみたい!)
紫は、奏也のことが嫌いで、気になって、彼のことを目で追うようになった。
そして、気が付けば、奏也のことを誰よりも好きになってしまっていたのだ。
紫が自分の気持ちに気が付いたのは、はじめて奏也の泣き顔を見た時だった。
(いつも笑ってた、奏也が泣いてる……)
紫に怪我をさせてしまったことを悔いて、紫のために泣いているのだ。
そう思った次の瞬間、紫は、自分でも思いがけない提案を奏也に持ち掛けていた。
――私の許嫁になって。
奏也が何故、紫に向かって石を投げたのか、その理由と背景を紫は、大人たちが話すのを聞いて、大体のことは理解していた。
いくら晃牙の命令と言えども、自分を傷つけた奏也のことを簡単に許すわけにはいかない。
これは、紫を傷つけた奏也への罰なのだ、と紫は自分に言い聞かせた。
奏也のことを好きだと素直に告白するには、紫の自尊心が高すぎたのだ。
そもそも諸悪の根源は、紫が〝悪党〟と内心で呼んでいた、白山 晃牙だ。
人を疑うことの知らない奏也は、紫の目から見て、庇護するべき小動物か何かのように映っていたのかもしれない。
(私が守ってあげなくちゃ)
当時、紫は、『嵐が丘』という本にはまっていた。
イギリスの荒野を舞台に、幼馴染であるキャサリンとヒースクリフの激しい恋――結末は悲劇に終わるけれど、自分もいつか、こんなに誰かと深く愛し合える恋がしたい、と密かに憧れていた。
ヒースクリフは、孤児として嵐が丘の養子となり、キャサリンだけがヒースクリフを庇い、彼の一番の理解者だった。
紫は、奏也と自分を『嵐が丘』のキャサリンとヒースクリフに重ねて見ていたところがあったかもしれない。
そして、キャサリンとヒースクリフは、すれ違いの末、互いを傷つけ合い、命を落とす――――。
(やっぱり〝悪役令嬢〟には、バッドエンドしかないんだわ。
でも……死ぬなら、せめて奏也の腕の中で――――)
紫が意識を手放そうとした、その時――――紫の耳に聞きなれた愛しい人の声が飛び込んできた。
「紫!!!」
衝撃。
落下速度が頂点に達した時、紫の身体が何か強い力で抱き留められた。
勢い余り、そのまま地面を転がる。
それでも、紫は、誰かの力強い腕の中に守られて、無事だった。
「ばっか⋯⋯!
お前、何考えてんだよっ!!」
「そう、や……?」
目を開けた紫は、自分の見たものが信じられなかった。
奏也は、怒っていた。
走って来たのか、肩で息をしながら、目を赤くして、泣きながら怒っている。
今までどれだけ紫が無茶なことを言っても、奏也が怒った顔を見たことなどない。
その奏也がカンカンに怒っている。
「奏也が助けてくれたの?」
「当たり前だろうっ!! 俺は、俺は……」
「わたし、奏也に嫌われてるって……」
「好きな女にあんなセリフ吐かれて、死なせてたまるかっ」
途端、紫は、泣いた。
幼少期の頃から決して人前で涙を見せたことのない紫が
大声を上げて、幼い子供のように泣いた。
周囲を大勢の生徒たちに囲まれているのにも構わず、奏也の胸に顔を押し付けるようにして泣きじゃくった。
はじめて奏也に怒鳴られたからでも、死からの恐怖に逃れた安堵からでもない。
自分の傍に、奏也がいる。
そのことが嬉しくて、自分の想いが通じたことが嬉しくて、ただその想いだけを胸に抱きながら泣き続けた。
一生分は泣いたかと思った頃、学校中の生徒に見られたと気付き、顔を真っ赤にして泣いた。
***
「いやぁ~、人間じゃないね、君は。
まさか、あの距離から走って間に合うとは」
あっけらかんと口を開けて笑うと、翼は、食べかけの卵焼きを美味しそうに頬張った。
屋上には、紫と奏也、翼の三人が居る以外、誰もいない。
あの日、サッカーグラウンドから、紫が屋上で叫んでいる姿を無言で見ていた奏也は、紫が落ちそうになったのを見て、即座に走り出していた。
周りで練習試合をしていたサッカー部の連中を追い抜き、
校庭で騒ぎを見ていた野次馬たちの間をすり抜け、
紫が落としたスマホの位置まで止まることなく走り駆けた。
たまたまその時、校庭で走り込みをしてた陸上部のエースがそれを見ていて、自分が本気を出しても、あそこまで速くは走れないぞ、愛の力は偉大だなぁ、などと話していたそうだ。
「翼が紫を掴んでてくれて、助かったよ。
そうじゃなかったら、さすがのオレも間に合わなかった」
奏也と翼は、長年一緒に戦い抜いた戦友のような顔をして笑い合う。
その様子を傍でじっと黙って睨んでいた紫は、持っていた箸の先端で翼を指した。
「どうして、あんたがここに居るのよ」
「こら、そんな言い方ないだろう。
翼がいなかったら、お前、本当に死んでたんだからな」
「うっ、奏也が怒ってる……」
「当たり前だ」
「そうちゃんは、過保護に甘やかしすぎよ。
恋人だからって、何でも許すのは間違ってる。
悪いことは悪いって、ちゃんと叱らなきゃ」
「そうちゃん?!
あんたねぇ……確かに、この前のことは、助けてくれて感謝してるわ。
でも、私は、まだあんたが奏也にしたこと、許してないんだからねっ!」
「えー、私、何かした?」
「とぼけないでっ。
私が見ているの気付いてて、奏也にキスしたでしょ!
……ま、まぁ、私も、似たようなことしてたから、人のこと言えないけど……
奏也は、私の許嫁なのよ! この売女っ!!」
「おいっ、どこでそんな言葉を……ってか、キスしたって、一体何のことだ?」
「あぁ、あれね。キスしてるように見えた?
実は、私の目にゴミが入っちゃって、奏也くんに見てもらってただけよ~」
「はぁ?! あんた、ふざけてるの?
絶対、確信犯でしょ!!!」
「あ、もしかして、紫が何かすっげぇ怒ってた時か。
確かオレ、あの時、すっごい傷つくこと言われたんだよなー」
「うっ……あの時は、ごめんなさい。
奏也を傷つけるつもりは、なかったのよ。
まさか、あんな反応を返されるとは思わなくて……」
「まぁ、俺も、今まではっきり自分の気持ちを伝えたことなかったからな。
これでも、言葉より行動で示してたつもりだったんだけど、
まさか逆の意味に受け取られてるとは、ショックだったよ」
「だって、そもそも私を怪我させた責任をとるって約束で、許嫁になってくれたでしょう?
人の弱みにつけこんで脅すようなことをする相手に、どうして好きになってくれるなんて思えるのよ?」
「あ、自覚あるんだ。さすが〝現代の悪役令嬢〟。
でも、私も興味あるなぁ。
奏也くんが紫ちゃんのどこに惹かれたのか」
「うーん、俺もはっきりこれだっていうのは、わかんないんだけどさぁ。
……やっぱ、あの時かな。
〝やりたくないことは、やりたくなって言え!〟って紫に言われて、確かになぁって。
俺、よく人から何も考えてないだろうって言われるんだけど、これでも結構、人に気を遣うタイプでさ。
皆が言うことに全部うんうん言ってたら、あれ、俺のやりたいことって何だっけ?ってなっていって……でも、紫は、そんな俺とは真逆でさ。
自分のやりたくないことは絶対にやらないし、やりたいことは何がなんでもやる。そんな自分を持っているところに惹かれたのかもな」
「あーそれ、私も分かる。
ほら、私の親、転勤族だって言ったじゃない?
だから、しょっちゅう学校が変わるし、新しい場所に早く打ち解けようって、みんなに良い顔して、皆の理想の〝聖女〟を演じてるんだよね。
紫ちゃんみたいに、自分の気持ちに素直になれたら、どれだけ楽だろうって思ってた。
それで、ちょっと悔しい気持ちもあったんだよね。
だから、意地悪しちゃった。ごめんね」
「許さん」
「まぁまぁ。せっかくこうして友達になれたんだから、いいじゃないか」
「いつ友達になったのかしら」
「ふっふっふ。ってわけで、これからも仲良くしましょう。
〝現代の悪役令嬢〟さん♡」
「〝聖女〟と〝悪役令嬢〟が仲良くなんて、そんな話あり得ない!」
「私、どっちかって言うと、〝悪役令嬢〟の方が好きだけどなぁ。
ほら、影の支配者っぽくて、なんかカッコイイじゃない」
「それじゃ、〝悪役令嬢〟じゃなくて、〝悪役代官〟よ。
というか、それ以前に……」
奏也と翼が紫を見つめ、続く言葉を待った。
「私は、〝悪役令嬢〟じゃありませんっ!!!」
完
ああ……でも、奏也に伝えられた。私の本当の気持ち……)
だから悔いはない。
柏崎 紫は、自分の思うままに生きて、自分の思うように死んでいくのだ。
〝現代の悪役令嬢〟は、王子様や他の誰かに処刑されるのではなく、自分の罪を悔いて、自分で罰するのだ。
(短い人生だったけど、奏也と一緒にいられて幸せだった)
屋上から落ちて行く中で、紫は、奏也との思い出の走馬灯を見た。
初めて奏也と会った時、紫は、誰にでもいい顔をして愛想を振りまく奏也のことが実は好きではなかった。
むしろ嫌いな人種だと思った。
どうして他人に自分を合わせる必要があるのか、紫には、理解できなかった。
だから、奏也が紫に遊ぼうと手を差し伸べてきても、いつもその手を突っぱねた。
でも、奏也は、それくらいではへこたれなかった。
どんなに紫がひどいことを言っても、奏也は、いつもにこにこと嬉しそうに笑っていた。
(どうして、いつも笑ってるの?
私にあんなこと言われて、どうして平気なの?
……きっと何もわかってないのね。ばっかみたい!)
紫は、奏也のことが嫌いで、気になって、彼のことを目で追うようになった。
そして、気が付けば、奏也のことを誰よりも好きになってしまっていたのだ。
紫が自分の気持ちに気が付いたのは、はじめて奏也の泣き顔を見た時だった。
(いつも笑ってた、奏也が泣いてる……)
紫に怪我をさせてしまったことを悔いて、紫のために泣いているのだ。
そう思った次の瞬間、紫は、自分でも思いがけない提案を奏也に持ち掛けていた。
――私の許嫁になって。
奏也が何故、紫に向かって石を投げたのか、その理由と背景を紫は、大人たちが話すのを聞いて、大体のことは理解していた。
いくら晃牙の命令と言えども、自分を傷つけた奏也のことを簡単に許すわけにはいかない。
これは、紫を傷つけた奏也への罰なのだ、と紫は自分に言い聞かせた。
奏也のことを好きだと素直に告白するには、紫の自尊心が高すぎたのだ。
そもそも諸悪の根源は、紫が〝悪党〟と内心で呼んでいた、白山 晃牙だ。
人を疑うことの知らない奏也は、紫の目から見て、庇護するべき小動物か何かのように映っていたのかもしれない。
(私が守ってあげなくちゃ)
当時、紫は、『嵐が丘』という本にはまっていた。
イギリスの荒野を舞台に、幼馴染であるキャサリンとヒースクリフの激しい恋――結末は悲劇に終わるけれど、自分もいつか、こんなに誰かと深く愛し合える恋がしたい、と密かに憧れていた。
ヒースクリフは、孤児として嵐が丘の養子となり、キャサリンだけがヒースクリフを庇い、彼の一番の理解者だった。
紫は、奏也と自分を『嵐が丘』のキャサリンとヒースクリフに重ねて見ていたところがあったかもしれない。
そして、キャサリンとヒースクリフは、すれ違いの末、互いを傷つけ合い、命を落とす――――。
(やっぱり〝悪役令嬢〟には、バッドエンドしかないんだわ。
でも……死ぬなら、せめて奏也の腕の中で――――)
紫が意識を手放そうとした、その時――――紫の耳に聞きなれた愛しい人の声が飛び込んできた。
「紫!!!」
衝撃。
落下速度が頂点に達した時、紫の身体が何か強い力で抱き留められた。
勢い余り、そのまま地面を転がる。
それでも、紫は、誰かの力強い腕の中に守られて、無事だった。
「ばっか⋯⋯!
お前、何考えてんだよっ!!」
「そう、や……?」
目を開けた紫は、自分の見たものが信じられなかった。
奏也は、怒っていた。
走って来たのか、肩で息をしながら、目を赤くして、泣きながら怒っている。
今までどれだけ紫が無茶なことを言っても、奏也が怒った顔を見たことなどない。
その奏也がカンカンに怒っている。
「奏也が助けてくれたの?」
「当たり前だろうっ!! 俺は、俺は……」
「わたし、奏也に嫌われてるって……」
「好きな女にあんなセリフ吐かれて、死なせてたまるかっ」
途端、紫は、泣いた。
幼少期の頃から決して人前で涙を見せたことのない紫が
大声を上げて、幼い子供のように泣いた。
周囲を大勢の生徒たちに囲まれているのにも構わず、奏也の胸に顔を押し付けるようにして泣きじゃくった。
はじめて奏也に怒鳴られたからでも、死からの恐怖に逃れた安堵からでもない。
自分の傍に、奏也がいる。
そのことが嬉しくて、自分の想いが通じたことが嬉しくて、ただその想いだけを胸に抱きながら泣き続けた。
一生分は泣いたかと思った頃、学校中の生徒に見られたと気付き、顔を真っ赤にして泣いた。
***
「いやぁ~、人間じゃないね、君は。
まさか、あの距離から走って間に合うとは」
あっけらかんと口を開けて笑うと、翼は、食べかけの卵焼きを美味しそうに頬張った。
屋上には、紫と奏也、翼の三人が居る以外、誰もいない。
あの日、サッカーグラウンドから、紫が屋上で叫んでいる姿を無言で見ていた奏也は、紫が落ちそうになったのを見て、即座に走り出していた。
周りで練習試合をしていたサッカー部の連中を追い抜き、
校庭で騒ぎを見ていた野次馬たちの間をすり抜け、
紫が落としたスマホの位置まで止まることなく走り駆けた。
たまたまその時、校庭で走り込みをしてた陸上部のエースがそれを見ていて、自分が本気を出しても、あそこまで速くは走れないぞ、愛の力は偉大だなぁ、などと話していたそうだ。
「翼が紫を掴んでてくれて、助かったよ。
そうじゃなかったら、さすがのオレも間に合わなかった」
奏也と翼は、長年一緒に戦い抜いた戦友のような顔をして笑い合う。
その様子を傍でじっと黙って睨んでいた紫は、持っていた箸の先端で翼を指した。
「どうして、あんたがここに居るのよ」
「こら、そんな言い方ないだろう。
翼がいなかったら、お前、本当に死んでたんだからな」
「うっ、奏也が怒ってる……」
「当たり前だ」
「そうちゃんは、過保護に甘やかしすぎよ。
恋人だからって、何でも許すのは間違ってる。
悪いことは悪いって、ちゃんと叱らなきゃ」
「そうちゃん?!
あんたねぇ……確かに、この前のことは、助けてくれて感謝してるわ。
でも、私は、まだあんたが奏也にしたこと、許してないんだからねっ!」
「えー、私、何かした?」
「とぼけないでっ。
私が見ているの気付いてて、奏也にキスしたでしょ!
……ま、まぁ、私も、似たようなことしてたから、人のこと言えないけど……
奏也は、私の許嫁なのよ! この売女っ!!」
「おいっ、どこでそんな言葉を……ってか、キスしたって、一体何のことだ?」
「あぁ、あれね。キスしてるように見えた?
実は、私の目にゴミが入っちゃって、奏也くんに見てもらってただけよ~」
「はぁ?! あんた、ふざけてるの?
絶対、確信犯でしょ!!!」
「あ、もしかして、紫が何かすっげぇ怒ってた時か。
確かオレ、あの時、すっごい傷つくこと言われたんだよなー」
「うっ……あの時は、ごめんなさい。
奏也を傷つけるつもりは、なかったのよ。
まさか、あんな反応を返されるとは思わなくて……」
「まぁ、俺も、今まではっきり自分の気持ちを伝えたことなかったからな。
これでも、言葉より行動で示してたつもりだったんだけど、
まさか逆の意味に受け取られてるとは、ショックだったよ」
「だって、そもそも私を怪我させた責任をとるって約束で、許嫁になってくれたでしょう?
人の弱みにつけこんで脅すようなことをする相手に、どうして好きになってくれるなんて思えるのよ?」
「あ、自覚あるんだ。さすが〝現代の悪役令嬢〟。
でも、私も興味あるなぁ。
奏也くんが紫ちゃんのどこに惹かれたのか」
「うーん、俺もはっきりこれだっていうのは、わかんないんだけどさぁ。
……やっぱ、あの時かな。
〝やりたくないことは、やりたくなって言え!〟って紫に言われて、確かになぁって。
俺、よく人から何も考えてないだろうって言われるんだけど、これでも結構、人に気を遣うタイプでさ。
皆が言うことに全部うんうん言ってたら、あれ、俺のやりたいことって何だっけ?ってなっていって……でも、紫は、そんな俺とは真逆でさ。
自分のやりたくないことは絶対にやらないし、やりたいことは何がなんでもやる。そんな自分を持っているところに惹かれたのかもな」
「あーそれ、私も分かる。
ほら、私の親、転勤族だって言ったじゃない?
だから、しょっちゅう学校が変わるし、新しい場所に早く打ち解けようって、みんなに良い顔して、皆の理想の〝聖女〟を演じてるんだよね。
紫ちゃんみたいに、自分の気持ちに素直になれたら、どれだけ楽だろうって思ってた。
それで、ちょっと悔しい気持ちもあったんだよね。
だから、意地悪しちゃった。ごめんね」
「許さん」
「まぁまぁ。せっかくこうして友達になれたんだから、いいじゃないか」
「いつ友達になったのかしら」
「ふっふっふ。ってわけで、これからも仲良くしましょう。
〝現代の悪役令嬢〟さん♡」
「〝聖女〟と〝悪役令嬢〟が仲良くなんて、そんな話あり得ない!」
「私、どっちかって言うと、〝悪役令嬢〟の方が好きだけどなぁ。
ほら、影の支配者っぽくて、なんかカッコイイじゃない」
「それじゃ、〝悪役令嬢〟じゃなくて、〝悪役代官〟よ。
というか、それ以前に……」
奏也と翼が紫を見つめ、続く言葉を待った。
「私は、〝悪役令嬢〟じゃありませんっ!!!」
完