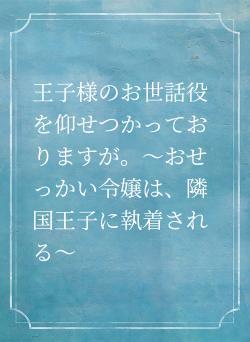「皆、やっぱりいい人だ」
二人はやっとのことで道具屋へと戻ってきた。
辺りはもう夕暮れ。長い長い一日だった。自分の家なのに、随分と久し振りのような感じがする。
「他人は自分の写し鏡と言うじゃないですか。ラウレル様がいい方だからですよ」
扉を閉め、ランタンに火を灯そうとするビオレッタの手をラウレルが止めた。
その手から彼を見上げると、ほの暗い道具屋で、蒼い瞳が切なげに輝く。
「ビオレッタは、これからも俺の事そう呼ぶの」
ランタンに伸ばされていたビオレッタの指は、ラウレルに絡み取られてしまった。全神経が指先に集中して、また彼のことしか考えられなくなっていく。
「ようやくただの『ラウレル』になれたのに、ビオレッタは変わらない?」
シンとした店内で、彼の熱っぽい声だけが妙に響いて。
ビオレッタには痛いくらいに伝わってくる。
彼が何を求めているのか。
「本当にいいんでしょうか? ……私で」
「何度でも言うけど、俺はビオレッタと結婚したい」
ラウレルが『オルテンシアの勇者』では無くなった今、 急に二人の結婚が現実味を帯びた。
「グリシナ村はとても田舎ですし」
「転移魔法を使えばどこへでも行ける」
「道具屋は経営も上手く行っていなくて……」
「そんなもの、二人で一緒に頑張ればいい」
「……私は世間知らずの田舎者で」
「俺はビオレッタの元に帰りたい」
強く、ラウレルは言い切った。
いつもそうだ。ビオレッタがどんなに後ろ向きな態度をとっても、彼は想いを貫き通してくれる。
「ラウレル……様」
『勇者』という言い訳の理由が無くなった今、ビオレッタにできるのは自分の気持ちに素直になることだけ。
「……ラウレル」
勇気を振り絞って、彼の名を呼んだ。
「ラウレル、ずっと私の傍にいて」
素直になってしまえば、止まらなかった。
この熱い顔を隠すように彼の胸にしがみつくと、それに応えるようにラウレルもビオレッタを抱きしめた。
「ああ、俺はビオレッタの傍にいる」
「ずっとだからね……」
いつの間にか目からは涙が溢れていた。
ビオレッタは、またひとつ知った。幸せすぎて流れる涙もあることを。
そして愛すことも愛されることも、このキスも。ラウレルがすべて教えてくれた。
二人は、何度も何度も、気持ちが溶け合うようなキスをした。深くなるキスは、互いの想いを伝え合うようで……
ひっそりとした道具屋の窓からは茜色の夕陽が射し込む。
雨上がりの空には、喜びを分かち合うようにほのかな虹がかかっていた。
二人はやっとのことで道具屋へと戻ってきた。
辺りはもう夕暮れ。長い長い一日だった。自分の家なのに、随分と久し振りのような感じがする。
「他人は自分の写し鏡と言うじゃないですか。ラウレル様がいい方だからですよ」
扉を閉め、ランタンに火を灯そうとするビオレッタの手をラウレルが止めた。
その手から彼を見上げると、ほの暗い道具屋で、蒼い瞳が切なげに輝く。
「ビオレッタは、これからも俺の事そう呼ぶの」
ランタンに伸ばされていたビオレッタの指は、ラウレルに絡み取られてしまった。全神経が指先に集中して、また彼のことしか考えられなくなっていく。
「ようやくただの『ラウレル』になれたのに、ビオレッタは変わらない?」
シンとした店内で、彼の熱っぽい声だけが妙に響いて。
ビオレッタには痛いくらいに伝わってくる。
彼が何を求めているのか。
「本当にいいんでしょうか? ……私で」
「何度でも言うけど、俺はビオレッタと結婚したい」
ラウレルが『オルテンシアの勇者』では無くなった今、 急に二人の結婚が現実味を帯びた。
「グリシナ村はとても田舎ですし」
「転移魔法を使えばどこへでも行ける」
「道具屋は経営も上手く行っていなくて……」
「そんなもの、二人で一緒に頑張ればいい」
「……私は世間知らずの田舎者で」
「俺はビオレッタの元に帰りたい」
強く、ラウレルは言い切った。
いつもそうだ。ビオレッタがどんなに後ろ向きな態度をとっても、彼は想いを貫き通してくれる。
「ラウレル……様」
『勇者』という言い訳の理由が無くなった今、ビオレッタにできるのは自分の気持ちに素直になることだけ。
「……ラウレル」
勇気を振り絞って、彼の名を呼んだ。
「ラウレル、ずっと私の傍にいて」
素直になってしまえば、止まらなかった。
この熱い顔を隠すように彼の胸にしがみつくと、それに応えるようにラウレルもビオレッタを抱きしめた。
「ああ、俺はビオレッタの傍にいる」
「ずっとだからね……」
いつの間にか目からは涙が溢れていた。
ビオレッタは、またひとつ知った。幸せすぎて流れる涙もあることを。
そして愛すことも愛されることも、このキスも。ラウレルがすべて教えてくれた。
二人は、何度も何度も、気持ちが溶け合うようなキスをした。深くなるキスは、互いの想いを伝え合うようで……
ひっそりとした道具屋の窓からは茜色の夕陽が射し込む。
雨上がりの空には、喜びを分かち合うようにほのかな虹がかかっていた。