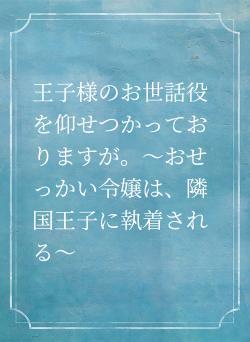贅を尽くした晩餐に、時々送り込まれてくるコラール姫。
勇者像を建ててやろう、屋敷をやろうとまで言われ、丁重に断る日々。
城での毎日はクタクタに疲れ果てた。とにかく早く、ビオレッタに会いたかった。
何度も嘆願し、一ヶ月後ようやく報酬を受け取った際、またもや王から姫との結婚を打診を受けた。
「気は変わったか」と。変わるわけない。
常々あった王に対する不信感は、もはや嫌悪感へと変わってしまった。本当に気持ちが悪かった。なんとしても勇者をオルテンシアの駒にしておきたいという王の思惑が。
これ以上我慢出来なくなったラウレルは、とうとう転移魔法で抜け出してグリシナ村までやって来たのだった。
そこからは必死だった。厚かましく強引だった自覚はある。しかし何をしてでも彼女のそばにいたかった。
裏口から出入りできる特別感。ビオレッタに毎日「おやすみ」と言える距離。彼女とのふたり暮しは、天にも登るように幸せな毎日で。
暮らすうちに、彼女を渇望していた心は、もっともっとと欲が出た。
ビオレッタの小さな肩、細い腰、さらさらとした長い髪が、触れられるほど傍にあるのだ。今だって、横たわる彼女の白い首筋に目がいってしまう。
そんな邪な自分を理性で制したりを繰り返して、この二ヶ月間なんとかやり過ごしている。
彼女から嫌われるようなことはしないと、そう約束をしたのだから。ベッドに押し倒された時は、さすがに我慢が効かず危なかったけれど。
あの時だって、ビオレッタは純粋にラウレルの体調ばかりを心配していた。そんな彼女を好きな気持ちは、膨らむばかりで。
優しく心配性な彼女が好きだ。
新しい世界を知るたびに、目を輝かせる彼女が好きだ。
ビオレッタの何もかもが……
「ビオレッタ、愛しています」
安らかな寝息をたてるビオレッタに向かって、ラウレルはぽつりと呟いた。
彼女の寝顔の隣で、やっと得られた幸せを手放すまいと固く心に決めたのだった。
勇者像を建ててやろう、屋敷をやろうとまで言われ、丁重に断る日々。
城での毎日はクタクタに疲れ果てた。とにかく早く、ビオレッタに会いたかった。
何度も嘆願し、一ヶ月後ようやく報酬を受け取った際、またもや王から姫との結婚を打診を受けた。
「気は変わったか」と。変わるわけない。
常々あった王に対する不信感は、もはや嫌悪感へと変わってしまった。本当に気持ちが悪かった。なんとしても勇者をオルテンシアの駒にしておきたいという王の思惑が。
これ以上我慢出来なくなったラウレルは、とうとう転移魔法で抜け出してグリシナ村までやって来たのだった。
そこからは必死だった。厚かましく強引だった自覚はある。しかし何をしてでも彼女のそばにいたかった。
裏口から出入りできる特別感。ビオレッタに毎日「おやすみ」と言える距離。彼女とのふたり暮しは、天にも登るように幸せな毎日で。
暮らすうちに、彼女を渇望していた心は、もっともっとと欲が出た。
ビオレッタの小さな肩、細い腰、さらさらとした長い髪が、触れられるほど傍にあるのだ。今だって、横たわる彼女の白い首筋に目がいってしまう。
そんな邪な自分を理性で制したりを繰り返して、この二ヶ月間なんとかやり過ごしている。
彼女から嫌われるようなことはしないと、そう約束をしたのだから。ベッドに押し倒された時は、さすがに我慢が効かず危なかったけれど。
あの時だって、ビオレッタは純粋にラウレルの体調ばかりを心配していた。そんな彼女を好きな気持ちは、膨らむばかりで。
優しく心配性な彼女が好きだ。
新しい世界を知るたびに、目を輝かせる彼女が好きだ。
ビオレッタの何もかもが……
「ビオレッタ、愛しています」
安らかな寝息をたてるビオレッタに向かって、ラウレルはぽつりと呟いた。
彼女の寝顔の隣で、やっと得られた幸せを手放すまいと固く心に決めたのだった。