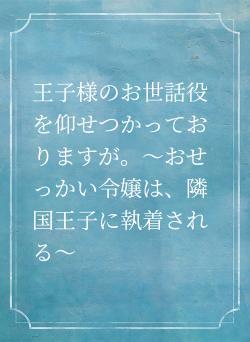「ラウレル様。一度、お姫様とお会いしてはいかがでしょうか」
ビオレッタは堪えきれず、ずっと考えていた言葉を口にした。プルガの背の上で、ラウレルの傷付いたような顔が彼女に向けられる。
「……なぜ会う必要があるんでしょうか? 俺はビオレッタさんと結婚したいと言ったはずです」
「分かっています、それはとてもありがたいと思っています」
「ならどうしてそんなことを言うんですか」
どうして、と聞かれてしまったら、それは――
「ラウレル様のことが好きだから」
ビオレッタには、彼の顔を見ることは出来なかった。
「好きだから、ラウレル様を自分に縛り付けるのが辛いんです」
ラウレルとの二人暮らしは、これ以上ないほど幸せだった。一人きりの毎日に戻りたくないくらいには。
けれど、彼は皆の希望だ。
広い世界に身を置くべきラウレルを、狭い世界に閉じ込めるようなこと、あってはならないと。
その事がずっとビオレッタを咎め続けている。
つい、瞳からは大粒の涙がこぼれてしまった。風をきり飛ぶプルガに、涙は飛んで散って行く。
(本当に、余計な気持ちを知ってしまったわ……)
自分を選んで欲しい、でも彼のためを思うと自分を選んで欲しくない。彼と一緒の暮らしを続けたい、でも彼を村に縛り続けるのが辛い。
なんて面倒な女になってしまったのだろう。
「でも」ばかり。逃げ道を探してばかり。
「だから……」
言葉を続けようとした口を、ラウレルの唇が塞いだ。
優しいような、強引なようなその唇は、名残惜しそうにゆっくりと離れていった。
「ずっと、キスしたかった」
睫毛が触れ合うほど近くで、蕩けそうな瞳がビオレッタを見つめている。それはあの日、二人きりの部屋で向けられた熱い眼差しと同じものだ。
「俺はずっと……毎日、どんな瞬間も、ビオレッタさんと結婚したいと思ってます」
「ラウレル様……」
「ビオレッタさんが困ることはしたくない……けど、こうして抑えが効かなくなるくらい、あなたのことが好きなんです」
彼の真っ直ぐな言葉が胸に刺さる。
その言葉が嬉しくて嬉しくて、彼のこと以外何も考えられなくなってしまう。
「どうか、勇者では無いただ一人の男として見てください。ビオレッタさんは何を望みますか。俺にとって大事なのはそれだけです」
「私……私は」
彼に求めるものなど……
もし、ひとつだけ願うなら、それは。
「……ラウレル様、どうかもう一度『ビオレッタ』と」
頭を離れない、あの甘い響きが欲しかった。
「ビオレッタ……」
彼の囁く声が、頭を痺れさせる。
もうずっと待ち望んでいたもの。
彼が、自分を欲しがる声。
ラウレルはうっとりと、ビオレッタの頬へ指を滑らせた。
「ビオレッタ」
二人は目と目を合わせると、引き寄せられるように顔を寄せ合いキスをした。
「ラウレル様、好きです」
「俺の方が好きです──」
広く青い空に、風をきりながら二人きり。
プルガの背中は、二人をただの『ビオレッタ』と『ラウレル』にしてくれた。
繰り返されるキスは、終わることがなくて。
プルガがグリシナ村を通り過ぎたことも気付かず、二人は気持ちを確かめ合った。