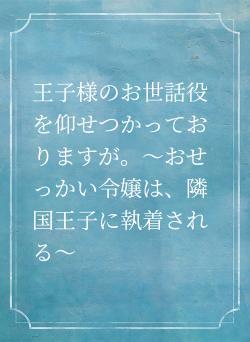そよぐ風に葉が揺れる音、鶏の鳴き声。
目を開けると、草原に囲まれた村の入り口に立っていた。
あたりいっぱいに広がるのは緑の香り。
同じ田舎でも、海風が吹くグリシナ村とはまた違った空気だ。
「ラウレル様、ここは……」
「ここはコリーナの村です」
ラウレルはビオレッタの手をひき、村の中へと歩きだした。
コリーナの村人達も、すれ違うたびにラウレルへ声をかける。彼は村民と挨拶を交わしながら、どんどん村の奥へと向かっていく。
「あの、どちらへ」
「この村に、ビオレッタさんへ見せたいものがあるんです」
迷いなく進むラウレルの足。見せたいものとは……一体、のどかなこの村に何があるというのだろうか。
手を引かれるがままについていくと、村の最奥にある小高い丘へと到着した。
そこから見えたものは……冴え渡る青空に、あたり一面の紫。
丘の上から見渡せば、眼下には地平線へ続くほどの花畑が広がっていた。これは……
「初めてここを訪れた時に、ビオレッタさんの色だ! と思いました」
空の水色と花の紫が、ビオレッタの色彩を思わせた。
淡いブルーの髪と、紫の瞳。まるでこの景色に溶け込むような――
「この花は、ビオレという花なんです」
「……私の名前と同じです」
「ご両親は、ビオレの花をご存知だったのでしょうね。もしかしたら行商の道中で、この丘に立ったことがあったのかもしれない」
紫の瞳の女の子だから、……ビオレ……ビオレッタ。
この紫の、花のように。
生まれた時に、両親はそう名付けてくれた。
お父さん。お母さん。
これまで大事にしてきた店を、これからはどうしたらいい?
自分一人ではどうしていいのか分からない。
教えてほしい。これからの生き方を。
会いたい、会いたい……
遠く、一面の紫を眺めた。ビオレッタの瞳からは、知らぬ間に涙がこぼれていた。
我慢していた心細さが、誰にも頼れない不安が、堰を切ったように溢れ出る。
「ビオレッタさんはご両親から望まれて産まれてきました」
ラウレルのあたたかな手のひらがビオレッタの頬を包み、流れる涙をそっと拭った。
「一人じゃありません。俺も、村の人も、皆ビオレッタさんの味方です」
彼は優し過ぎる。ビオレッタをとことん甘やかす。彼が涙を拭うたび、固くなっていた心が、ぐずぐずに解れていくようだった。
「一人で悩まずに、周りを頼ってみませんか」
ラウレルのやさしい瞳は、真っ直ぐにビオレッタを映す。
ビオレッタが泣き止むまで、二人はコリーナの丘で佇み続けていた。
目を開けると、草原に囲まれた村の入り口に立っていた。
あたりいっぱいに広がるのは緑の香り。
同じ田舎でも、海風が吹くグリシナ村とはまた違った空気だ。
「ラウレル様、ここは……」
「ここはコリーナの村です」
ラウレルはビオレッタの手をひき、村の中へと歩きだした。
コリーナの村人達も、すれ違うたびにラウレルへ声をかける。彼は村民と挨拶を交わしながら、どんどん村の奥へと向かっていく。
「あの、どちらへ」
「この村に、ビオレッタさんへ見せたいものがあるんです」
迷いなく進むラウレルの足。見せたいものとは……一体、のどかなこの村に何があるというのだろうか。
手を引かれるがままについていくと、村の最奥にある小高い丘へと到着した。
そこから見えたものは……冴え渡る青空に、あたり一面の紫。
丘の上から見渡せば、眼下には地平線へ続くほどの花畑が広がっていた。これは……
「初めてここを訪れた時に、ビオレッタさんの色だ! と思いました」
空の水色と花の紫が、ビオレッタの色彩を思わせた。
淡いブルーの髪と、紫の瞳。まるでこの景色に溶け込むような――
「この花は、ビオレという花なんです」
「……私の名前と同じです」
「ご両親は、ビオレの花をご存知だったのでしょうね。もしかしたら行商の道中で、この丘に立ったことがあったのかもしれない」
紫の瞳の女の子だから、……ビオレ……ビオレッタ。
この紫の、花のように。
生まれた時に、両親はそう名付けてくれた。
お父さん。お母さん。
これまで大事にしてきた店を、これからはどうしたらいい?
自分一人ではどうしていいのか分からない。
教えてほしい。これからの生き方を。
会いたい、会いたい……
遠く、一面の紫を眺めた。ビオレッタの瞳からは、知らぬ間に涙がこぼれていた。
我慢していた心細さが、誰にも頼れない不安が、堰を切ったように溢れ出る。
「ビオレッタさんはご両親から望まれて産まれてきました」
ラウレルのあたたかな手のひらがビオレッタの頬を包み、流れる涙をそっと拭った。
「一人じゃありません。俺も、村の人も、皆ビオレッタさんの味方です」
彼は優し過ぎる。ビオレッタをとことん甘やかす。彼が涙を拭うたび、固くなっていた心が、ぐずぐずに解れていくようだった。
「一人で悩まずに、周りを頼ってみませんか」
ラウレルのやさしい瞳は、真っ直ぐにビオレッタを映す。
ビオレッタが泣き止むまで、二人はコリーナの丘で佇み続けていた。