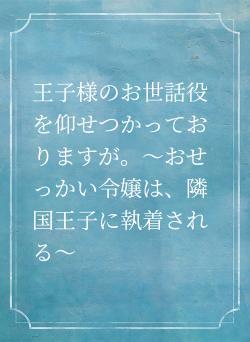「あ、シリオさん」
「おう、ラウレルおつかれ。じゃ、またなビオレッタ」
ラウレルが帰ってくるなり、シリオは手を振りながら道具屋を後にした。
以前ラウレルにビオレッタとの仲を誤解されかけてからというもの、彼なりに気を遣っているらしい。ラウレルの前では、誤解されるような状況を避けようとするのである。それはもう、わざとらしいほど。
「はは。シリオさん、気を遣ってくれてますね……やっぱり、妬けますけど」
「え?」
「お二人が特別な関係では無いと分かってはいるんです。でも、俺なんかには敵わない絆みたいなものが見えて」
「それは……」
天涯孤独のビオレッタにとって、隣に住むシリオは家族のような存在だった。みんな仲の良いグリシナ村の中でも、歳の近いシリオは気を遣わなくていい唯一の存在なのだ。
「シリオは、兄のようなものなので仕方がないですよ。ラウレル様にも、ご兄弟はいらっしゃるでしょう?」
「いえ、俺に家族はいないので」
「えっ……では、オルテンシアでは?」
「一人で暮らしていましたよ。物心ついた時には、一人きりだったんです」
それは初耳だった。
ラウレルいわく、都会であるオルテンシアにはそのような子供も多く、特に珍しいことでもないらしい。
「おう、ラウレルおつかれ。じゃ、またなビオレッタ」
ラウレルが帰ってくるなり、シリオは手を振りながら道具屋を後にした。
以前ラウレルにビオレッタとの仲を誤解されかけてからというもの、彼なりに気を遣っているらしい。ラウレルの前では、誤解されるような状況を避けようとするのである。それはもう、わざとらしいほど。
「はは。シリオさん、気を遣ってくれてますね……やっぱり、妬けますけど」
「え?」
「お二人が特別な関係では無いと分かってはいるんです。でも、俺なんかには敵わない絆みたいなものが見えて」
「それは……」
天涯孤独のビオレッタにとって、隣に住むシリオは家族のような存在だった。みんな仲の良いグリシナ村の中でも、歳の近いシリオは気を遣わなくていい唯一の存在なのだ。
「シリオは、兄のようなものなので仕方がないですよ。ラウレル様にも、ご兄弟はいらっしゃるでしょう?」
「いえ、俺に家族はいないので」
「えっ……では、オルテンシアでは?」
「一人で暮らしていましたよ。物心ついた時には、一人きりだったんです」
それは初耳だった。
ラウレルいわく、都会であるオルテンシアにはそのような子供も多く、特に珍しいことでもないらしい。