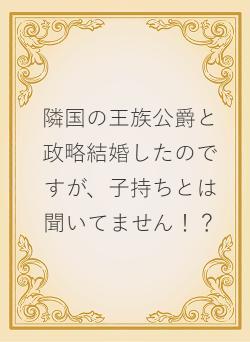3、ミュレン伯爵令息の噂と、新婚生活
よく晴れた日。
マリアンヌは、飼い猫に囲まれてのんびりと読書をしていた。
ハウスメイドが香り高い紅茶を淹れる湯音が、耳に心地よい。
「奥様、聞きました? ジエール・ミュレン伯爵令息がご病気らしいのですよ。それも性病なのですって」
ジエール・ミュレン伯爵令息は、元婚約者の名前だ。マリアンヌはびっくりした。
「えっ……」
「治療中とのことですが、ミュレン伯爵家も大変ですね。新しく婚約者になったご令嬢にも逃げられてしまったのですって」
「にゃぁお」
感情を持て余しているマリアンヌの膝に長毛の猫がそーっと寄ってくる。「乗ってもいーい?」と尋ねるみたいに前足をちょこんと膝にのせてくる。可愛い。
さらさらの毛を撫でながら、マリアンヌは言葉を探した。
「ご病気がよくなるといいですわね」
「まあ奥様、お優しい」
ハウスメイドの反応からすると、これは恐らく「元婚約者の醜聞を持ってきたので悪口を叩いて楽しんではいかが」という話題提供だったのかもしれない。
「ふふ、私の妻は優しいのだ」
扉の方角からおっとりとした声がして視線を向けると、エプロンをした夫ナーシュがいる。持っているトレイには、焼き菓子があった。食欲を刺激するバターの香りがふんわり漂う。なぜ貴い身分の夫がトレイを手に持っているのかと、マリアンヌは目を丸くした。
「私が焼いた。自信作だよ」
「えっ? 殿下がですか?」
使用人ではなく? 耳を疑うマリアンヌにナーシュは「私は変わり者で有名だろう、噂通りだろう」と笑った。
「妻のためにお菓子をつくる夫は嫌いかな」
「い、いえ。美味しいです、ありがとうございます」
焼き菓子はサクサクとした食感で甘さ控えめ。美味しい。
「うん、うん。よかった。ところで、名前で呼んでみるのはどう? 呼ばれてみたいな。私も名前を呼びたい」
「ナーシュ様」
「いいね。今日はマリアンヌが名前を呼んでくれた記念日だ」
ナーシュは嬉しそうに微笑み、ティータイムを共に過ごしてピアノをほろほろと弾いてくれた。木漏れ日のように降り注ぐ優しい旋律と、膝の上で丸くなって眠る猫の体温が眠気を誘う。うつらうつらしているとピアノが止まって、「庭を一緒に散策しようかと思ったのだけど、お昼寝もいいね」と言う声がきこえる。
「はっ……失礼いたしました」
「ぜんぜん失礼ではない。妻が私の前でリラックスしてくれているのだと思って、感動してしまった。嬉しい気持ちになったよ……妻の肩を抱いても構わないだろうか? 嫌?」
「それは当然、はい……嫌ではありません」
「ふふっ、夫の特権かな。天使のような君に堂々と触れられる」
夏の陽射しよりも眩しい笑顔で、ナーシュはマリアンヌの肩を抱いた。
「で、殿下は大袈裟です……」
「名前で言ってみよう?」
「……ナーシュ様は、大袈裟です」
ふわりと微笑むと、ナーシュの手にちょっと力がこもるのが感じられる。
「ティータイムも一緒に過ごそう。毎日ではないけど、お菓子をつくるから食べてほしいな」
ナーシュはマリアンヌに優しかった。好意を寄せてくれているのが、はっきりとわかる。
マリアンヌはそんな夫を好ましく思いながら公爵家に慣れていった。
使用人たちも親切で、猫たちは心を癒してくれて、夫は何かを義務づけることなく好意的に接してくれる。とても恵まれた生活だ。
「ナーシュ様に好意をお返ししたいのですけど、私が何かをする隙がありませんね……」
猫じゃらしで猫たちと遊びながら、マリアンヌは呟いた。とりあえずハンカチに刺繍でも、と思って少しずつ針を進めているが。
「何かしてくれるのかい?」
呟きひとつでナーシュが部屋までやってくる。耳ざとい。
「衣装を見立ててもらうのはどうかな。服飾工房から職人を呼ぼう」
それはマリアンヌが「何かした」になるのだろうか。疑問に思いつつも、夫婦は応接室に職人を招いた。
「このデコルテを出したドレスは素敵だけど、私の妻の魅力が引き立てられすぎて悪い虫がつかないか心配になってしまうよ」
ナーシュはデザイン画を一緒に覗き込み、コメントをした。
「ナーシュ様の衣装を……」
「私は妻の引き立て役さ。ついででいいよ」
ナーシュは楽しそうだった。
「このドレスは後ろが編み上げになっていてリボンで結んでいるだろう? 可愛らしくて、引っ張ったり解きたくなってしまうな……ああ、ごめんね。本当に引っ張ったりはしないよ。今のは失言だったかな、気持ち悪く思った? 謝るよ」
「いえ、大丈夫です」
お互いに生地やデザインを選び合い、採寸をしてもらう。工房の女性仕立て師が数人がかりで、緊張した顔で慎重に仕事をしてくれた。小柄な女性仕立て師が群れていると、夫の背の高さが際立って見えた。仕立て師が頬を染めているのが、マリアンヌの胸をくすぐる。夫は誰が見ても魅力的なのだ。
首の周りに巻く装飾用のクラヴァットを手に取り、ナーシュがイタズラな瞳を見せる。
「いいかい、このクラヴァットを買うだろう? 私が少し乱して付けるだろう? 妻が『あなた、クラヴァットが乱れていますよ、私が直して差し上げます』と直してくれるわけだ。最高ではないかな」
「よくわかりません」
「ちょっとやってみてほしい。だめかな」
「く、クラヴァットが乱れていますよ、私が直して差し上げます……?」
「あ、いいね。素晴らしい……マリアンヌのおかげで、私はとても楽しい時間を過ごせたよ。ありがとう」
感謝されてしまった。
マリアンヌは「私も楽しかったです」と感謝を返しつつ、ついでのように購入された指輪を指に填めてもらった。
「私が選んだ色が妻の美しさをいっそう引き立てる。これってとても幸せだね。そうそう、今度あらためて結婚式をしない? 結婚を急ぎすぎてしまったなって、後悔してるんだ……」
仕立て師たちが羨ましがるような表情を浮かべている。マリアンヌは極上の葡萄酒を飲んだようにふわふわとした幸せ気分になった。
(ナーシュ様って他の女性にもこうなのかしら?)
マリアンヌは胸のうちで鼓動を躍らせながら、一方でちょっぴり心配になった。
よく晴れた日。
マリアンヌは、飼い猫に囲まれてのんびりと読書をしていた。
ハウスメイドが香り高い紅茶を淹れる湯音が、耳に心地よい。
「奥様、聞きました? ジエール・ミュレン伯爵令息がご病気らしいのですよ。それも性病なのですって」
ジエール・ミュレン伯爵令息は、元婚約者の名前だ。マリアンヌはびっくりした。
「えっ……」
「治療中とのことですが、ミュレン伯爵家も大変ですね。新しく婚約者になったご令嬢にも逃げられてしまったのですって」
「にゃぁお」
感情を持て余しているマリアンヌの膝に長毛の猫がそーっと寄ってくる。「乗ってもいーい?」と尋ねるみたいに前足をちょこんと膝にのせてくる。可愛い。
さらさらの毛を撫でながら、マリアンヌは言葉を探した。
「ご病気がよくなるといいですわね」
「まあ奥様、お優しい」
ハウスメイドの反応からすると、これは恐らく「元婚約者の醜聞を持ってきたので悪口を叩いて楽しんではいかが」という話題提供だったのかもしれない。
「ふふ、私の妻は優しいのだ」
扉の方角からおっとりとした声がして視線を向けると、エプロンをした夫ナーシュがいる。持っているトレイには、焼き菓子があった。食欲を刺激するバターの香りがふんわり漂う。なぜ貴い身分の夫がトレイを手に持っているのかと、マリアンヌは目を丸くした。
「私が焼いた。自信作だよ」
「えっ? 殿下がですか?」
使用人ではなく? 耳を疑うマリアンヌにナーシュは「私は変わり者で有名だろう、噂通りだろう」と笑った。
「妻のためにお菓子をつくる夫は嫌いかな」
「い、いえ。美味しいです、ありがとうございます」
焼き菓子はサクサクとした食感で甘さ控えめ。美味しい。
「うん、うん。よかった。ところで、名前で呼んでみるのはどう? 呼ばれてみたいな。私も名前を呼びたい」
「ナーシュ様」
「いいね。今日はマリアンヌが名前を呼んでくれた記念日だ」
ナーシュは嬉しそうに微笑み、ティータイムを共に過ごしてピアノをほろほろと弾いてくれた。木漏れ日のように降り注ぐ優しい旋律と、膝の上で丸くなって眠る猫の体温が眠気を誘う。うつらうつらしているとピアノが止まって、「庭を一緒に散策しようかと思ったのだけど、お昼寝もいいね」と言う声がきこえる。
「はっ……失礼いたしました」
「ぜんぜん失礼ではない。妻が私の前でリラックスしてくれているのだと思って、感動してしまった。嬉しい気持ちになったよ……妻の肩を抱いても構わないだろうか? 嫌?」
「それは当然、はい……嫌ではありません」
「ふふっ、夫の特権かな。天使のような君に堂々と触れられる」
夏の陽射しよりも眩しい笑顔で、ナーシュはマリアンヌの肩を抱いた。
「で、殿下は大袈裟です……」
「名前で言ってみよう?」
「……ナーシュ様は、大袈裟です」
ふわりと微笑むと、ナーシュの手にちょっと力がこもるのが感じられる。
「ティータイムも一緒に過ごそう。毎日ではないけど、お菓子をつくるから食べてほしいな」
ナーシュはマリアンヌに優しかった。好意を寄せてくれているのが、はっきりとわかる。
マリアンヌはそんな夫を好ましく思いながら公爵家に慣れていった。
使用人たちも親切で、猫たちは心を癒してくれて、夫は何かを義務づけることなく好意的に接してくれる。とても恵まれた生活だ。
「ナーシュ様に好意をお返ししたいのですけど、私が何かをする隙がありませんね……」
猫じゃらしで猫たちと遊びながら、マリアンヌは呟いた。とりあえずハンカチに刺繍でも、と思って少しずつ針を進めているが。
「何かしてくれるのかい?」
呟きひとつでナーシュが部屋までやってくる。耳ざとい。
「衣装を見立ててもらうのはどうかな。服飾工房から職人を呼ぼう」
それはマリアンヌが「何かした」になるのだろうか。疑問に思いつつも、夫婦は応接室に職人を招いた。
「このデコルテを出したドレスは素敵だけど、私の妻の魅力が引き立てられすぎて悪い虫がつかないか心配になってしまうよ」
ナーシュはデザイン画を一緒に覗き込み、コメントをした。
「ナーシュ様の衣装を……」
「私は妻の引き立て役さ。ついででいいよ」
ナーシュは楽しそうだった。
「このドレスは後ろが編み上げになっていてリボンで結んでいるだろう? 可愛らしくて、引っ張ったり解きたくなってしまうな……ああ、ごめんね。本当に引っ張ったりはしないよ。今のは失言だったかな、気持ち悪く思った? 謝るよ」
「いえ、大丈夫です」
お互いに生地やデザインを選び合い、採寸をしてもらう。工房の女性仕立て師が数人がかりで、緊張した顔で慎重に仕事をしてくれた。小柄な女性仕立て師が群れていると、夫の背の高さが際立って見えた。仕立て師が頬を染めているのが、マリアンヌの胸をくすぐる。夫は誰が見ても魅力的なのだ。
首の周りに巻く装飾用のクラヴァットを手に取り、ナーシュがイタズラな瞳を見せる。
「いいかい、このクラヴァットを買うだろう? 私が少し乱して付けるだろう? 妻が『あなた、クラヴァットが乱れていますよ、私が直して差し上げます』と直してくれるわけだ。最高ではないかな」
「よくわかりません」
「ちょっとやってみてほしい。だめかな」
「く、クラヴァットが乱れていますよ、私が直して差し上げます……?」
「あ、いいね。素晴らしい……マリアンヌのおかげで、私はとても楽しい時間を過ごせたよ。ありがとう」
感謝されてしまった。
マリアンヌは「私も楽しかったです」と感謝を返しつつ、ついでのように購入された指輪を指に填めてもらった。
「私が選んだ色が妻の美しさをいっそう引き立てる。これってとても幸せだね。そうそう、今度あらためて結婚式をしない? 結婚を急ぎすぎてしまったなって、後悔してるんだ……」
仕立て師たちが羨ましがるような表情を浮かべている。マリアンヌは極上の葡萄酒を飲んだようにふわふわとした幸せ気分になった。
(ナーシュ様って他の女性にもこうなのかしら?)
マリアンヌは胸のうちで鼓動を躍らせながら、一方でちょっぴり心配になった。