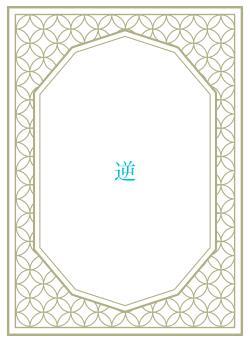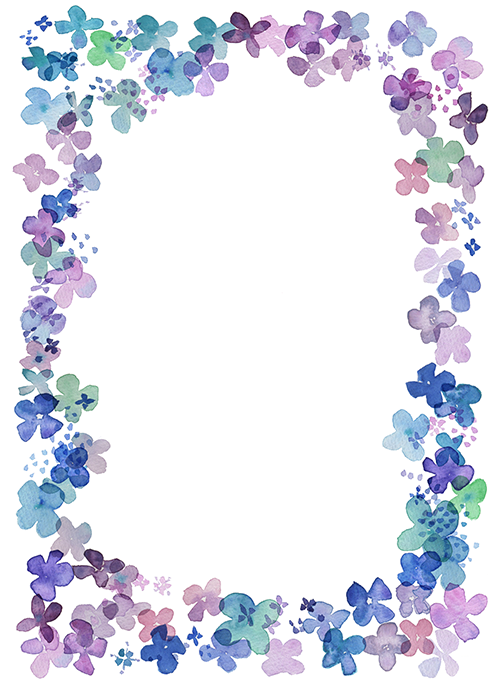コンコン。
「海都ー。凛花だけど」
水色の木の扉をノックして声をかける。
ここは海都の家の二階。
我が家と同じく海都の家も二階建てで、一階が「fu-rin」のスペース、二階が居住スペースとなっている。
大雨の中帰宅したわたしと海都は、おたがいの家でシャワーを浴びるために一旦別れた。
そして今、わたしは海都の部屋の前にいる。
「凛花ちゃん? どーぞー」
明るい返事が聞こえたので、片手でトレイを持って扉をゆっくりと押す。
真っ白なTシャツにジーンズ姿の海都が、からりとした笑顔で迎えてくれた。
シンプルな格好は、彼のスタイルの良さを際立たせている。
美しい所作でタオルを使い、部屋の真ん中で髪についた水を拭き取っていた。
海都はわたしが持っているトレイに気づきつつも、話し始めた。
「いやー、ビックリしたね。まさかあんなに降るなんて思わなかったよ」
「だよね。予報では明日って言ってたから、油断しちゃった」
うしろ手で扉をはめて部屋の中に入る。
すると海都は勉強机のイスをひっぱりだし、わたしの背後にイスを置いてくれた。
こういうさりげなく親切なところが、モテる理由なんだろうなあ。
「ありがとう」
「ごめんね、傘とか持ってきてなかったから……。体調はおかしくなってない?」
眉をハの字にして、しゅんとした瞳であやまってきた。
わたしは海都を振り返って微笑み返す。
「ぜんぜん! わたしはどこも問題ないよ。海都は大丈夫?」
勉強机にトレイを置いて、今度はわたしがたずねる。
「うん! お母さんに、女の子を雨でびしょ濡れにさせるんじゃないって怒られちゃった。あはは」
ぺろっと舌を出して軽い調子で言う。
おばさん、女の子のことは大切にしなさい! って、小さいころから海都にずっと言ってたからなあ。
十何年と一緒にいるわたしのことも、女の子の一人として扱ってくれるのは嬉しい。
「明日の体育祭、大丈夫かな? グラウンドで開催されるんだよね?」
「いやあ、さすがに中止じゃない? びったびたの地面を走ったら転びまくるよ」
「あー、そっかー」
「ねえ、そのトレイに載ってるのはなに?」
「あ、そうそう! 体冷えたから、ホットミルク作ったの」
そう言ったら、海都のガラス玉みたいに澄んだ瞳が輝いた。
(お、これは)
いつも「三日月うさぎ」で使っているマグを手に取る。
(欲しそうな顔してる!)
「飲む?」
「飲みます」
真面目な顔で即答してくれた。
両手を伸ばしてくる海都にホットミルクの入ったマグを手渡す。
自分の手の中にマグが入って、嬉しそうにニコリと笑みを浮かべた。
……かと思ったら、今度は伏し目で不安そうな表情になった。
「あの、凛花ちゃん」
「ん?」
「……念のため、言っておくけど」
「え、なに?」
海都はホットミルクには口をつけず、ベッドに腰かけながらもう一度口を開く。
「あんまりほいほい男子の部屋に入っちゃダメだからね?」
「……」
ようやくホットミルクを一口飲みこんだ。
それを見はからって、答える。
「うん、入らないよ。海都は特別枠でしょ」
「とっ……⁉︎」
どんよりしていた海都の背中が、はじかれたようにぴんっとなった。
「どういう意味? それ」
「やっぱり、親近感? 距離感? わたしが自然体でいられるから」
「ほかの男の子の部屋には、誘われてもちゃんと断るよ。てか、海都の部屋はおばさんにも許可とったし」
話しながらイスから降りて、ベッドの横の窓に近づく。
雨はさっきよりは静かになったけれど、何度もしとしとと落ちている。
「なに? 心配してくれたの?」
「そりゃ……心配するよ」
海都はすねたような顔をしていた。
……どうしたんだろう。
「このマグ、お店に一つしかないやつだよね」
「えっ?」
ぽんっと放たれた海都の言葉に、驚いてかたまる。
「知ってたの?」
「わりと前から」
(マジか)
赤い毛糸のハートがプリントされたマグを見つめ、ただ驚いてかたまる。
わたしは教えてないから、となると……。
「凛花ちゃんのお母さんから聞いたんだー。これ、凛花ちゃんのお気に入りのマグなんでしょ?」
(やっぱり!)
全力でかくすつもりではなかったけど、知ってたんだって思うとなんだか恥ずかしい。
お父さんは話したりしないだろうし。というか知ってるのかな。
「僕が使っちゃっていいのかなって思ったんだけどね。凛花ちゃん、いつもこれで出してくれるから、」
さっきまでのすねたような顔が、話をするにつれて少しずつ甘くほどけていく。
「まあいっかって」
海都がマグを勉強机に置き、こっちに近づいてきて。
———抱きしめられた。
「うみ……⁉︎」
「抱きしめちゃダメなんて言わないでよ」
普段の海都ならきっと言わないような、少し強引な口調。
背中と首に巻きついた海都の腕の力の強さに、海都は男の子なんだって思った。
ブランコのときと違って、今はおたがいの体が密着しているから、余計にそう感じる。
じんわりとした体温が伝わってきて、思考がうまく回らなくなっている。
「って、それはさすがにひどいか。勝手に抱きついてごめんね」
そう、薄いガラスに触れるみたいに繊細な声で言って、さっとわたしから離れた。
わたしの両手をとり、イスの前まで導いてくれる。
ゆっくりと座らせて、そして繋ぐ手の力を強める。
……ああ。
こういうところが、たまらなく愛おしいんだよなあ。
優しくて、あっさりさっぱりと軽やかで、温かい。
「海都ー。凛花だけど」
水色の木の扉をノックして声をかける。
ここは海都の家の二階。
我が家と同じく海都の家も二階建てで、一階が「fu-rin」のスペース、二階が居住スペースとなっている。
大雨の中帰宅したわたしと海都は、おたがいの家でシャワーを浴びるために一旦別れた。
そして今、わたしは海都の部屋の前にいる。
「凛花ちゃん? どーぞー」
明るい返事が聞こえたので、片手でトレイを持って扉をゆっくりと押す。
真っ白なTシャツにジーンズ姿の海都が、からりとした笑顔で迎えてくれた。
シンプルな格好は、彼のスタイルの良さを際立たせている。
美しい所作でタオルを使い、部屋の真ん中で髪についた水を拭き取っていた。
海都はわたしが持っているトレイに気づきつつも、話し始めた。
「いやー、ビックリしたね。まさかあんなに降るなんて思わなかったよ」
「だよね。予報では明日って言ってたから、油断しちゃった」
うしろ手で扉をはめて部屋の中に入る。
すると海都は勉強机のイスをひっぱりだし、わたしの背後にイスを置いてくれた。
こういうさりげなく親切なところが、モテる理由なんだろうなあ。
「ありがとう」
「ごめんね、傘とか持ってきてなかったから……。体調はおかしくなってない?」
眉をハの字にして、しゅんとした瞳であやまってきた。
わたしは海都を振り返って微笑み返す。
「ぜんぜん! わたしはどこも問題ないよ。海都は大丈夫?」
勉強机にトレイを置いて、今度はわたしがたずねる。
「うん! お母さんに、女の子を雨でびしょ濡れにさせるんじゃないって怒られちゃった。あはは」
ぺろっと舌を出して軽い調子で言う。
おばさん、女の子のことは大切にしなさい! って、小さいころから海都にずっと言ってたからなあ。
十何年と一緒にいるわたしのことも、女の子の一人として扱ってくれるのは嬉しい。
「明日の体育祭、大丈夫かな? グラウンドで開催されるんだよね?」
「いやあ、さすがに中止じゃない? びったびたの地面を走ったら転びまくるよ」
「あー、そっかー」
「ねえ、そのトレイに載ってるのはなに?」
「あ、そうそう! 体冷えたから、ホットミルク作ったの」
そう言ったら、海都のガラス玉みたいに澄んだ瞳が輝いた。
(お、これは)
いつも「三日月うさぎ」で使っているマグを手に取る。
(欲しそうな顔してる!)
「飲む?」
「飲みます」
真面目な顔で即答してくれた。
両手を伸ばしてくる海都にホットミルクの入ったマグを手渡す。
自分の手の中にマグが入って、嬉しそうにニコリと笑みを浮かべた。
……かと思ったら、今度は伏し目で不安そうな表情になった。
「あの、凛花ちゃん」
「ん?」
「……念のため、言っておくけど」
「え、なに?」
海都はホットミルクには口をつけず、ベッドに腰かけながらもう一度口を開く。
「あんまりほいほい男子の部屋に入っちゃダメだからね?」
「……」
ようやくホットミルクを一口飲みこんだ。
それを見はからって、答える。
「うん、入らないよ。海都は特別枠でしょ」
「とっ……⁉︎」
どんよりしていた海都の背中が、はじかれたようにぴんっとなった。
「どういう意味? それ」
「やっぱり、親近感? 距離感? わたしが自然体でいられるから」
「ほかの男の子の部屋には、誘われてもちゃんと断るよ。てか、海都の部屋はおばさんにも許可とったし」
話しながらイスから降りて、ベッドの横の窓に近づく。
雨はさっきよりは静かになったけれど、何度もしとしとと落ちている。
「なに? 心配してくれたの?」
「そりゃ……心配するよ」
海都はすねたような顔をしていた。
……どうしたんだろう。
「このマグ、お店に一つしかないやつだよね」
「えっ?」
ぽんっと放たれた海都の言葉に、驚いてかたまる。
「知ってたの?」
「わりと前から」
(マジか)
赤い毛糸のハートがプリントされたマグを見つめ、ただ驚いてかたまる。
わたしは教えてないから、となると……。
「凛花ちゃんのお母さんから聞いたんだー。これ、凛花ちゃんのお気に入りのマグなんでしょ?」
(やっぱり!)
全力でかくすつもりではなかったけど、知ってたんだって思うとなんだか恥ずかしい。
お父さんは話したりしないだろうし。というか知ってるのかな。
「僕が使っちゃっていいのかなって思ったんだけどね。凛花ちゃん、いつもこれで出してくれるから、」
さっきまでのすねたような顔が、話をするにつれて少しずつ甘くほどけていく。
「まあいっかって」
海都がマグを勉強机に置き、こっちに近づいてきて。
———抱きしめられた。
「うみ……⁉︎」
「抱きしめちゃダメなんて言わないでよ」
普段の海都ならきっと言わないような、少し強引な口調。
背中と首に巻きついた海都の腕の力の強さに、海都は男の子なんだって思った。
ブランコのときと違って、今はおたがいの体が密着しているから、余計にそう感じる。
じんわりとした体温が伝わってきて、思考がうまく回らなくなっている。
「って、それはさすがにひどいか。勝手に抱きついてごめんね」
そう、薄いガラスに触れるみたいに繊細な声で言って、さっとわたしから離れた。
わたしの両手をとり、イスの前まで導いてくれる。
ゆっくりと座らせて、そして繋ぐ手の力を強める。
……ああ。
こういうところが、たまらなく愛おしいんだよなあ。
優しくて、あっさりさっぱりと軽やかで、温かい。