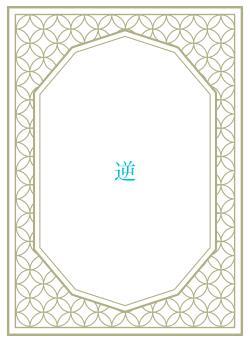ピンポーン。
「ん?」
お昼ご飯を食べ終わり、ランチタイムの混雑がピークになってきた十二時四十分。
二階に鳴り響いたチャイムに、首をかしげる。
廊下を移動し、階段の上からカフェスペースにいるお母さんに話しかけた。
「お母さーん、今日なんか届くものあったー?」
「ええっ? 凛花、なんて言った? あっ、はーい! 今行きますね〜」
(聞こえてないな)
注文を取りに走り出す母を見送り、はあっとため息をつく。
廊下を移動しながら言ったから、ちゃんと聞こえなかったみたい。
どうもこの家の階段は、声の通りがあまりよくないのだ。
とりあえずインターホンのボタンを押してみたら……。
「えっ、海都?」
小さな画面には、カメラに顔を近づける海都が映っていた。
(出るのがおそかったからか!)
あわてて通話ボタンを押す。
「ごめん、おそくなっちゃった」
『あ! よかったー、出てくれて。急にごめんね』
「ううん。ぜんぜん大丈夫だけど、うちになにか用事?」
『ちょっと、外来てくれない?』
海都はそう言うと、見えていなかった紙袋を自分の顔の横に持ち上げた。
「ん?」
お昼ご飯を食べ終わり、ランチタイムの混雑がピークになってきた十二時四十分。
二階に鳴り響いたチャイムに、首をかしげる。
廊下を移動し、階段の上からカフェスペースにいるお母さんに話しかけた。
「お母さーん、今日なんか届くものあったー?」
「ええっ? 凛花、なんて言った? あっ、はーい! 今行きますね〜」
(聞こえてないな)
注文を取りに走り出す母を見送り、はあっとため息をつく。
廊下を移動しながら言ったから、ちゃんと聞こえなかったみたい。
どうもこの家の階段は、声の通りがあまりよくないのだ。
とりあえずインターホンのボタンを押してみたら……。
「えっ、海都?」
小さな画面には、カメラに顔を近づける海都が映っていた。
(出るのがおそかったからか!)
あわてて通話ボタンを押す。
「ごめん、おそくなっちゃった」
『あ! よかったー、出てくれて。急にごめんね』
「ううん。ぜんぜん大丈夫だけど、うちになにか用事?」
『ちょっと、外来てくれない?』
海都はそう言うと、見えていなかった紙袋を自分の顔の横に持ち上げた。