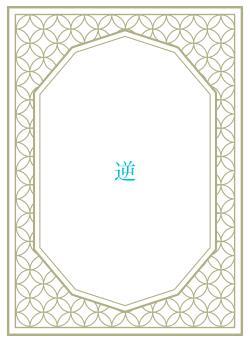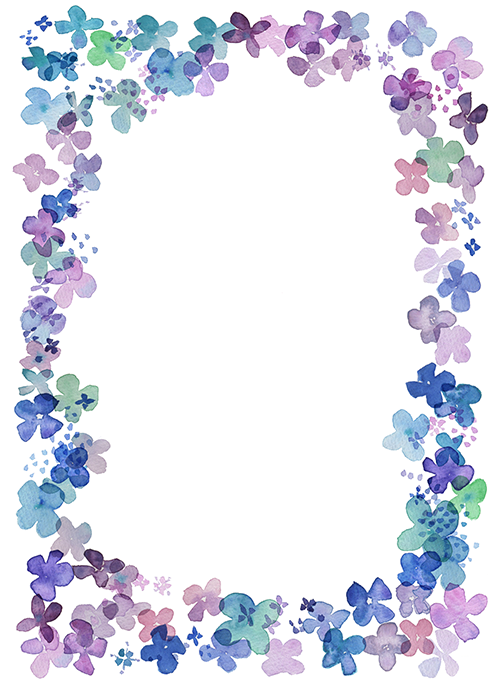「ねえー、ほかになんかないの? 『幼なじみ』とかさ」
海都がむうっとほっぺたをふくらませている。
なんだこいつ、そこらの女子高生がプリクラ撮るときよりかわいい仕草してるぞ。
わたしが尊敬を通り越して、もはやあきれていることを、この純粋な目の少年は知らない。
「それで言ったら、海都だっていつもホットミルクしか頼まないよね。そんなに好きなの?」
今は四時半、比較的お客さんが少ない時間帯。
ほかのお客さんは奥の席にいるから実質二人きりのような状態だから、いつもこんな感じでだべっている。
「いつも」というのは、海都が必ずと言っていいほどお客さんの少ない時間帯にやってくるからだ。
「好きだよ! おいしいんだもん、凛花ちゃんが作るホットミルク」
「いや、うちのお母さんとかが作っても変わんないと思うよ?」
「そりゃ変わらずおいしいけどさぁ……。『凛花ちゃんが』っていうのが重要なの!」
「そんなに重要?」
「そんなに重要! もー、なんでわかんないかなあ」
海都の言いぶんに首をかしげつつ、三つ編みおだんごをほどいて、ただの三つ編みにもどす。とくに意味はない。
「ふーん……? まあわたしも好きだけどね、ホットミルクは」
「凛花ちゃんも好きなんじゃん。やったー!」
なにが嬉しいのかサッパリだけど、マグを大切そうに両手で包んでいるのが微笑ましくなる。
海都が持つマグは、赤い毛糸がハートの輪を一つ作りながら、ぐるっと壁面を一周している。
かわいいデザインだから、わたしも気に入っているんだ。
閉店後なんかにときどき使ったりしている。
一つしかないから、お客さんに出すことは滅多にないんだ。でも、海都にはこれで出している。
なんとなく教えない方がいい気がして、海都には言っていないけど。
「とくに『三日月うさぎ』は、トッピングできるのもうれしいんだよねー♪」
そういうわけでドライフルーツください! と、とびきりスマイルでカウンターに乗り出してくる。
「はーい。なんにする? 三種類まで選べるけど」
「知ってるよ。週に何回来てると思ってるの」
「それもそうだね」
わたしの「幼なじみ」は、ホットミルクしか頼まない。
九月の半ばで、まだ残暑が残る季節であっても。
「じゃ〜あ〜。苺とブルーベリーで!」
「了解。作りたてのだから、きっとおいしいよ」
「そうなの⁉︎ 楽しみだなあ〜」
作りたてという言葉に、海都の瞳がきらんと光った。
ほんと、十五歳とは思えないくらいの純粋さだなあ。
キッチンスペースに引っこんで、冷蔵庫からドライフルーツを取りに行く。
わたしも試食したけど、お父さんが作るドライフルーツは絶品だ。
海都、どんな顔するかなって、思わず笑みがこぼれる。
「……凛花ちゃん、気づいてくれないかな」
海都の小さなひとりごとなんて、聞こえるわけがなかった。
海都がむうっとほっぺたをふくらませている。
なんだこいつ、そこらの女子高生がプリクラ撮るときよりかわいい仕草してるぞ。
わたしが尊敬を通り越して、もはやあきれていることを、この純粋な目の少年は知らない。
「それで言ったら、海都だっていつもホットミルクしか頼まないよね。そんなに好きなの?」
今は四時半、比較的お客さんが少ない時間帯。
ほかのお客さんは奥の席にいるから実質二人きりのような状態だから、いつもこんな感じでだべっている。
「いつも」というのは、海都が必ずと言っていいほどお客さんの少ない時間帯にやってくるからだ。
「好きだよ! おいしいんだもん、凛花ちゃんが作るホットミルク」
「いや、うちのお母さんとかが作っても変わんないと思うよ?」
「そりゃ変わらずおいしいけどさぁ……。『凛花ちゃんが』っていうのが重要なの!」
「そんなに重要?」
「そんなに重要! もー、なんでわかんないかなあ」
海都の言いぶんに首をかしげつつ、三つ編みおだんごをほどいて、ただの三つ編みにもどす。とくに意味はない。
「ふーん……? まあわたしも好きだけどね、ホットミルクは」
「凛花ちゃんも好きなんじゃん。やったー!」
なにが嬉しいのかサッパリだけど、マグを大切そうに両手で包んでいるのが微笑ましくなる。
海都が持つマグは、赤い毛糸がハートの輪を一つ作りながら、ぐるっと壁面を一周している。
かわいいデザインだから、わたしも気に入っているんだ。
閉店後なんかにときどき使ったりしている。
一つしかないから、お客さんに出すことは滅多にないんだ。でも、海都にはこれで出している。
なんとなく教えない方がいい気がして、海都には言っていないけど。
「とくに『三日月うさぎ』は、トッピングできるのもうれしいんだよねー♪」
そういうわけでドライフルーツください! と、とびきりスマイルでカウンターに乗り出してくる。
「はーい。なんにする? 三種類まで選べるけど」
「知ってるよ。週に何回来てると思ってるの」
「それもそうだね」
わたしの「幼なじみ」は、ホットミルクしか頼まない。
九月の半ばで、まだ残暑が残る季節であっても。
「じゃ〜あ〜。苺とブルーベリーで!」
「了解。作りたてのだから、きっとおいしいよ」
「そうなの⁉︎ 楽しみだなあ〜」
作りたてという言葉に、海都の瞳がきらんと光った。
ほんと、十五歳とは思えないくらいの純粋さだなあ。
キッチンスペースに引っこんで、冷蔵庫からドライフルーツを取りに行く。
わたしも試食したけど、お父さんが作るドライフルーツは絶品だ。
海都、どんな顔するかなって、思わず笑みがこぼれる。
「……凛花ちゃん、気づいてくれないかな」
海都の小さなひとりごとなんて、聞こえるわけがなかった。