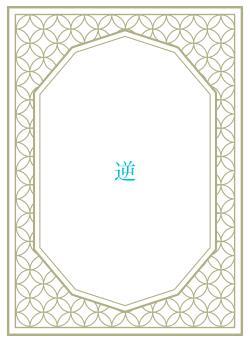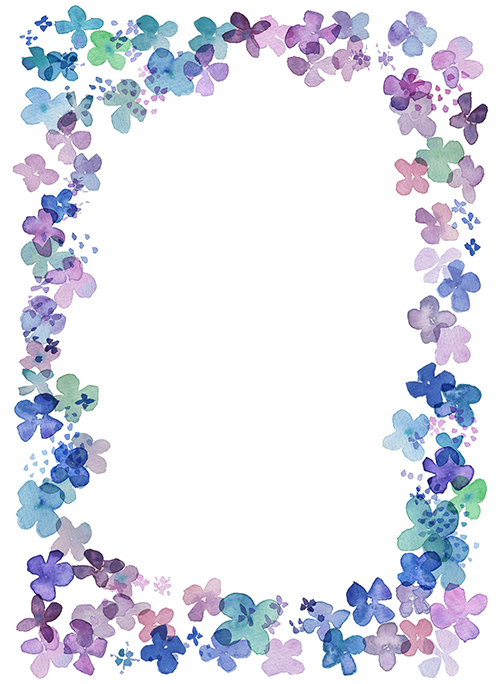「凛花ちゃん」
海都が悩むようにうつむいていた顔をぱっと上げた。
勢いで目が合って、ドキッとする。
「今まで言えなかったけど、ちゃんと伝えるね」
海都は真剣な眼差しで、まっすぐに宣言した。
「僕、ずっと、」
先の言葉を待つけれど、なかなか聞こえてこない。
「海都……?」
「ごめん。こんな状態で言うことかなあって思っちゃって。情けないなあ……」
こんなにも弱々しくて、不安そうな海都は、見たことがない。
力がゆるく抜けた海都の手のひらを、わたしからにぎり直した。
下を向いていた海都と、また視線がぶつかった。
「……大丈夫。なんでも言ってよ」
海都がもう一度、わたしを上から抱きしめる。
今度は驚かなかった。
わたしも、海都の背中に両腕をまわして、ぎゅっとする。
しばらくの沈黙のあと。
「ずっと、凛花ちゃんのことが好きだったんだ」
顔を見られなくてよかったって思った。
だって、きっと真っ赤になってるから。
高ぶっていく感情を静かにさせようと思っていたけれど、どうやら難しいみたいだ。
顔に、出てしまう。
「うん」
「ただの常連でもお隣さんでもなくて、恋人になってほしいんだけど、だめ?」
ひと息に話した声がどこか苦しそうだったのは、緊張してる、から?
海都の気持ちを、真摯に、ちゃんと受けとめてあげなきゃって思った。
「……ううん。だめじゃないよ」
初めて、告白っていうのをされた。
しかも相手は、人生のほとんどを一緒に生きてきた幼なじみ。
想いに対する緊張が、心臓に、声に、指先にめぐっていく。
「じゃあさ」
海都がわたしの首から腕をはずして、膝立ちになった。
目線が同じ高さになる。
至近距離に見える熱っぽい瞳が、炎のようにゆらりと動いた気がした。
「僕たちってどんな関係?」
何度も聞いてきた質問。
わたしの返答は、今日、海都によって変えられた。
「……恋人同士、でしょ」
消えいりそうなくらい小さな声になっちゃったけど、それでもはっきり伝えたかった。
「本当にそうなんだよね?」
「嘘の返事なんてしないよ」
間髪入れずに疑われちゃって、なぜか安堵の笑みがこぼれた。
「ああー……!」
海都は幸せそうな声を上げて、そのままぺたんと床に座ってしまった。
海都が悩むようにうつむいていた顔をぱっと上げた。
勢いで目が合って、ドキッとする。
「今まで言えなかったけど、ちゃんと伝えるね」
海都は真剣な眼差しで、まっすぐに宣言した。
「僕、ずっと、」
先の言葉を待つけれど、なかなか聞こえてこない。
「海都……?」
「ごめん。こんな状態で言うことかなあって思っちゃって。情けないなあ……」
こんなにも弱々しくて、不安そうな海都は、見たことがない。
力がゆるく抜けた海都の手のひらを、わたしからにぎり直した。
下を向いていた海都と、また視線がぶつかった。
「……大丈夫。なんでも言ってよ」
海都がもう一度、わたしを上から抱きしめる。
今度は驚かなかった。
わたしも、海都の背中に両腕をまわして、ぎゅっとする。
しばらくの沈黙のあと。
「ずっと、凛花ちゃんのことが好きだったんだ」
顔を見られなくてよかったって思った。
だって、きっと真っ赤になってるから。
高ぶっていく感情を静かにさせようと思っていたけれど、どうやら難しいみたいだ。
顔に、出てしまう。
「うん」
「ただの常連でもお隣さんでもなくて、恋人になってほしいんだけど、だめ?」
ひと息に話した声がどこか苦しそうだったのは、緊張してる、から?
海都の気持ちを、真摯に、ちゃんと受けとめてあげなきゃって思った。
「……ううん。だめじゃないよ」
初めて、告白っていうのをされた。
しかも相手は、人生のほとんどを一緒に生きてきた幼なじみ。
想いに対する緊張が、心臓に、声に、指先にめぐっていく。
「じゃあさ」
海都がわたしの首から腕をはずして、膝立ちになった。
目線が同じ高さになる。
至近距離に見える熱っぽい瞳が、炎のようにゆらりと動いた気がした。
「僕たちってどんな関係?」
何度も聞いてきた質問。
わたしの返答は、今日、海都によって変えられた。
「……恋人同士、でしょ」
消えいりそうなくらい小さな声になっちゃったけど、それでもはっきり伝えたかった。
「本当にそうなんだよね?」
「嘘の返事なんてしないよ」
間髪入れずに疑われちゃって、なぜか安堵の笑みがこぼれた。
「ああー……!」
海都は幸せそうな声を上げて、そのままぺたんと床に座ってしまった。