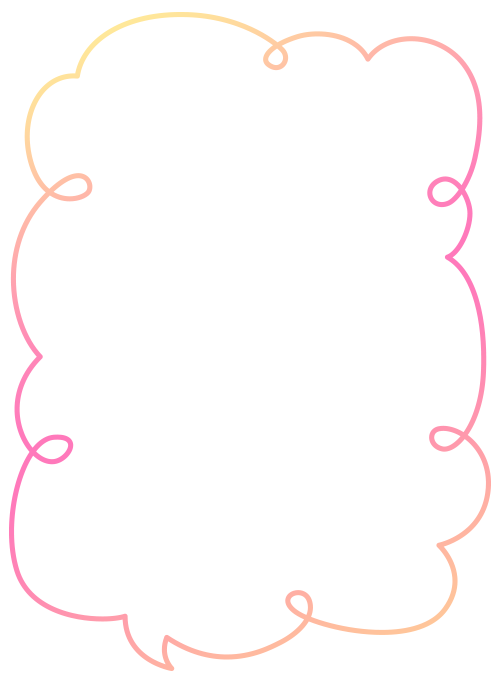「——そっちの方が、俺のこと知ってると思うよ」
あんな子よりも、と付け加えた彼は、どこか怖くて、鋭くて、なにを考えているのか分からない危うさを持っていて。
これも演技なのだろうか。そんなことを思ってしまう。
「……そんなわけない」
「そう?」
「知らないよ、あなたのことなんて」
「じゃあ知ってよ。あと、別に俺、朝弱くないから」
「……教えてもらわなくていい」
こういうのは、教えてもらいたいんじゃない。
教えられたものを、信じたいんじゃない。
「……知っていきたい、から」
与えられるものだけじゃなくて、自分で見つけていきたい。
「……そっか」
くすり、笑う彼に「なに?」とすこしむっとすれば、
「いや、俺が思ってる以上に、俺のこと好きなんだなって」
「……っ、ち、がう、から」
わたしの気持ちばかり、いつだって奪っていく。自分の感情なんてさらけ出さないで。
「撮影がんばって」
自分から掴んできたくせに、手放すときはいつもあっさりと。
掴まれていた熱が、引いたはずなのに、まだ名残惜しく残っているような気がして気に食わない。
「……勝手ばっか」
「ありがと」
「褒めてない」
なのに、うれしいと思ってしまうんだ。
ほんとうは、こうして飄々としていたり、話し方が柔らかくなかったり、どこかいたずら好きだったり。
そんなのも、わたしだけが知ってるのだろうか。わたしだけが、知れているのだろうか。
誑かされて、弄ばれて、それから——
「いいよ、どんどん俺のこと好きになって」
「……っ」
翻弄されていく。どこまでも、引きずられていく。彼の心の中に。
あんな子よりも、と付け加えた彼は、どこか怖くて、鋭くて、なにを考えているのか分からない危うさを持っていて。
これも演技なのだろうか。そんなことを思ってしまう。
「……そんなわけない」
「そう?」
「知らないよ、あなたのことなんて」
「じゃあ知ってよ。あと、別に俺、朝弱くないから」
「……教えてもらわなくていい」
こういうのは、教えてもらいたいんじゃない。
教えられたものを、信じたいんじゃない。
「……知っていきたい、から」
与えられるものだけじゃなくて、自分で見つけていきたい。
「……そっか」
くすり、笑う彼に「なに?」とすこしむっとすれば、
「いや、俺が思ってる以上に、俺のこと好きなんだなって」
「……っ、ち、がう、から」
わたしの気持ちばかり、いつだって奪っていく。自分の感情なんてさらけ出さないで。
「撮影がんばって」
自分から掴んできたくせに、手放すときはいつもあっさりと。
掴まれていた熱が、引いたはずなのに、まだ名残惜しく残っているような気がして気に食わない。
「……勝手ばっか」
「ありがと」
「褒めてない」
なのに、うれしいと思ってしまうんだ。
ほんとうは、こうして飄々としていたり、話し方が柔らかくなかったり、どこかいたずら好きだったり。
そんなのも、わたしだけが知ってるのだろうか。わたしだけが、知れているのだろうか。
誑かされて、弄ばれて、それから——
「いいよ、どんどん俺のこと好きになって」
「……っ」
翻弄されていく。どこまでも、引きずられていく。彼の心の中に。