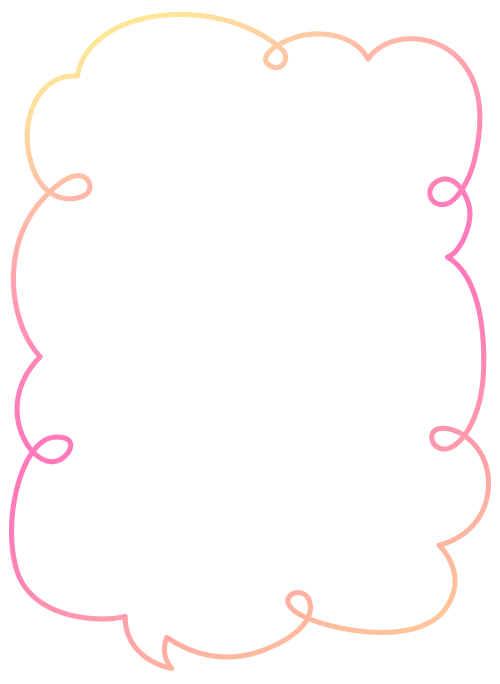「——来栖凪が主演に決まってるって」
「……えっ」
よりにもよって、その主演が来栖凪なのだから、運命のいたずらというのは本当に厄介だなと思う。
こんな偶然があるのかと思う反面、あってたまるかとも思う。
「どうする? 引き受ける?」
「……いや、やめときます」
運命に翻弄されっぱなし。そのいたずらに振り回されたくない。
「あら、どうして?」
「……お芝居とかしたことないですし、いくらグラドルの役だとしても、その……セリフとか覚えられる自信もないというか……そもそも演技出来る自信がない、です」
ポーズをとることは出来る。カメラの前で、色っぽい顔をしろと要求されても出来る。
けれど、それがセリフつきのお芝居となれば話は別だ。
いくらお色気担当といっても、誘惑なんて……しかもあの来栖凪にしかけるのだから、簡単にイエスとは言えない。
「残念、本当に断っていいの?」
「はい……わたしには荷が重いというか」
「——ねえ、うた」
肩が丸くなっていき、姿勢が悪くなっていく。前屈みになっていたわたしの手を、夢さんがそっと手を握る。
「この仕事するときも、同じようなこと言ってたわね」
「……っ」
「〝わたしにグラビアなんて無理です……自信がないです〟って。覚えてる?」
「……覚えてます」
忘れるわけがない。
わたしが正式にグラビアとして活動が決まってしまったとき、弱音しか吐けなかった。
無理です、出来ません、自信がないです、撮影なんて、水着なんて。
そんな言葉ばかりを並べて、人目に触れたくなくて、事務所のトイレに閉じこもって。
いやだった。水着を身につけてカメラの前に立つなんて。しかも、大胆なポーズをするなんて。
「……えっ」
よりにもよって、その主演が来栖凪なのだから、運命のいたずらというのは本当に厄介だなと思う。
こんな偶然があるのかと思う反面、あってたまるかとも思う。
「どうする? 引き受ける?」
「……いや、やめときます」
運命に翻弄されっぱなし。そのいたずらに振り回されたくない。
「あら、どうして?」
「……お芝居とかしたことないですし、いくらグラドルの役だとしても、その……セリフとか覚えられる自信もないというか……そもそも演技出来る自信がない、です」
ポーズをとることは出来る。カメラの前で、色っぽい顔をしろと要求されても出来る。
けれど、それがセリフつきのお芝居となれば話は別だ。
いくらお色気担当といっても、誘惑なんて……しかもあの来栖凪にしかけるのだから、簡単にイエスとは言えない。
「残念、本当に断っていいの?」
「はい……わたしには荷が重いというか」
「——ねえ、うた」
肩が丸くなっていき、姿勢が悪くなっていく。前屈みになっていたわたしの手を、夢さんがそっと手を握る。
「この仕事するときも、同じようなこと言ってたわね」
「……っ」
「〝わたしにグラビアなんて無理です……自信がないです〟って。覚えてる?」
「……覚えてます」
忘れるわけがない。
わたしが正式にグラビアとして活動が決まってしまったとき、弱音しか吐けなかった。
無理です、出来ません、自信がないです、撮影なんて、水着なんて。
そんな言葉ばかりを並べて、人目に触れたくなくて、事務所のトイレに閉じこもって。
いやだった。水着を身につけてカメラの前に立つなんて。しかも、大胆なポーズをするなんて。