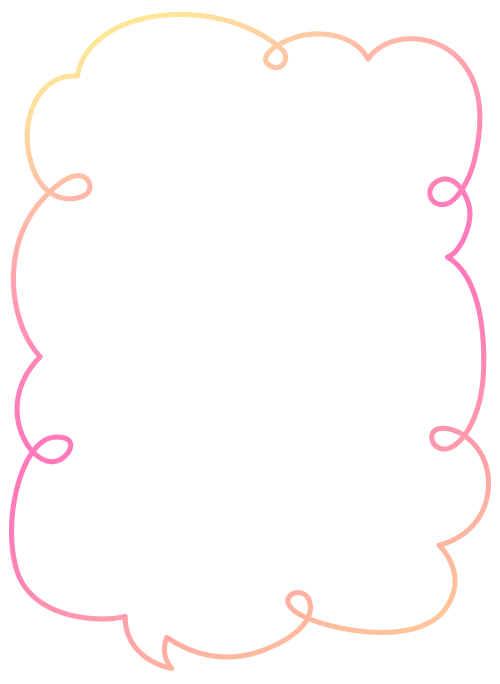あの男からどう守ってあげられるだろうかと、そんなことばかりを考えていた俺に、
『あ、そうですね、かじかんで痛いです』
少し驚きを見せながらも、うれしさを滲ませた彼女の顔にやられてしまった。
なんだ、そのかわいいはにかみかたは……!
心臓がもぎとられるかと思った。あぶない、たしかに襲われてもおかしくない。
動悸にも似た息苦しさを覚えながらも、どうしたらあの男から遠ざけられるだろうかと再び考え、まだ確定でもなかった仕事を引っ張りだした。
「ギターの役をすることになったから教えて」などと言った誘い文句を、彼女はなにひとつ疑うこともせず引き受けてくれた。
そのピュアさが、逆に心配だった。変なことに巻き込まれそうな匂いが強く香って、守りたい──いや、ぜんぶ俺だけのものしたいという支配欲が生まれていた。
歌声も、話し方も、笑い方も、仕草一つとっても、そのどれもが惹かれるものでしかなかった。
たくさん女を見てきたけれど、本能的に心が惹かれていくという意味では初めての経験で、どうにかして彼女と一緒にいたいと思ってしまった。
あの男は佐光に始末してもらった。変な奴がうろついてるから警察に通報してと伝えれば「なんでお前がまずそこをうろついているんだ」と鋭い指摘が入りスルーを貫いた。
警察が巡回するようになり、男も無事に消え、定期的に彼女に会いに行くようにした。
仕事のためにギター、というよりは、彼女に好いてもらうためにギターを習得したと言ってもおかしくはなかった。
彼女はギターのことになると周りが見えなくなるタイプらしく、俺にコードを教えようとするときも無意識で俺の指ごと握ったり、体をぐっと寄せ真剣な眼差しで教えてくれようとするものだから、俺はどれだけ理性を殺したかわからない。
どれだけ寒くても、手がかじかんで次の日の撮影で使い物にならなくても、それでも彼女に会いに行くのをやめなかった。
そんな日々を過ごしている中、仕事の合間ですら仕事になるような時期が続き、彼女に会いに行けなかったときがあった。
あの男は大丈夫だろうか、と。別の男には言い寄られていないだろうか。
そんな不安ばかりが募り、ようやくあの場所に戻ってこれたときには、もう彼女はそこにはいなかった。