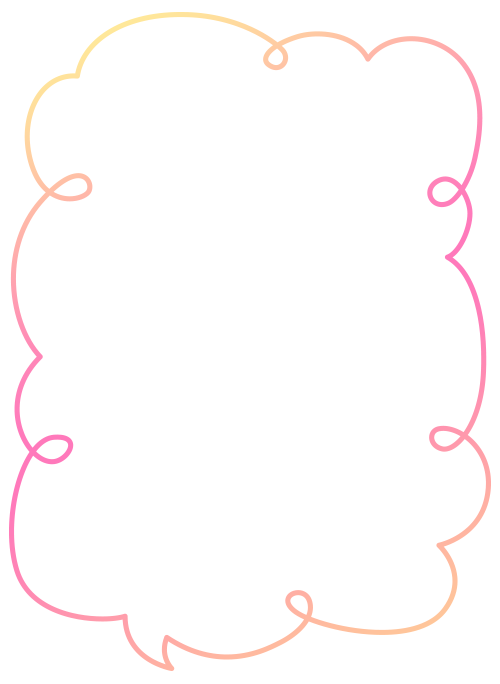氷の鞭のように吹き荒れる風の中、ギターをかきならすとある少女を見て、まじでどんな強者だよ、と思った。
彼女に抱いた最初の感情は、言うなれば興味本位。
それから襲いかかってくるかのように、彼女のまっすぐな歌声が鼓膜を震わせたとき、正直心まで震えた。大袈裟じゃなくて、本気で。
きっかけはなんだってよかった。けれど、とりあえず、彼女の存在に触れてみたいと思った。
冬の寒空の下、天使に会ったと思ったぐらいには、彼女に魅了されていたのだと今なら思う。
どう話を切り出したらいいかなんて分からないし、彼女に近づく手段がわからなかった。
いつも、数人の客に混じってちょろっと聞いては、そこからすこし離れ本格的に聞く。
そんな根性無しともとれる行動には自分でも呆れて苦笑が滲んでしまうほどだった。
おかしいな、女の扱いには慣れてるはずなのに、なんて調子のいいことを思うものの。
振り返れば、女のあしらい方、スルーの仕方だけを極めてやり過ごしてきたことが判明して愕然とする。
なんだ、ぜんぜんじゃん、俺。
そんな情けないことに気づかされているというのに、彼女は一向に俺に気付かない。
いや、俺という存在にはもしかしたら気付いているのかもしれないけれど、俺が誰なのかということは知らないようにも見えた。
仕事の合間を塗っては、くそ寒い外へと繰り出し、彼女の歌声を聞きに行く。そんな生活をしばらく続けている中で、見つけてしまったのは俺と同じぐらいにやばい奴。
彼女の演奏をじっと黙って見つめるあの男は、決まってこうして少し離れたところを歌を聞いていた。
……いや、聞いていた、というよりは。
狙っていた、という表現の方が正しかったのかもしれない。
全身黒で統一されたその風貌から、生気というものが感じられなくて、時折ぶつぶつと呟いていた。
その男が「今日だ……絶対今日、お、そう」と言っているのを聞いて、これは本気でまずいかもしれないと察したわけで。
俺の勘違いでなければ、男は「襲う」と言っていたのだと思う。
そんなわけで、黙って彼女の歌声を聞いていた群衆の一人から、ようやく抜け出す決心がつき、あの男が近づくよりも前に彼女に話しかけた。
『こんな寒いのに、指痛くないの?』
路上ライブ後の彼女に話しかけたとき、なかなか緊張していたことを彼女は知っていただろうか。
彼女に抱いた最初の感情は、言うなれば興味本位。
それから襲いかかってくるかのように、彼女のまっすぐな歌声が鼓膜を震わせたとき、正直心まで震えた。大袈裟じゃなくて、本気で。
きっかけはなんだってよかった。けれど、とりあえず、彼女の存在に触れてみたいと思った。
冬の寒空の下、天使に会ったと思ったぐらいには、彼女に魅了されていたのだと今なら思う。
どう話を切り出したらいいかなんて分からないし、彼女に近づく手段がわからなかった。
いつも、数人の客に混じってちょろっと聞いては、そこからすこし離れ本格的に聞く。
そんな根性無しともとれる行動には自分でも呆れて苦笑が滲んでしまうほどだった。
おかしいな、女の扱いには慣れてるはずなのに、なんて調子のいいことを思うものの。
振り返れば、女のあしらい方、スルーの仕方だけを極めてやり過ごしてきたことが判明して愕然とする。
なんだ、ぜんぜんじゃん、俺。
そんな情けないことに気づかされているというのに、彼女は一向に俺に気付かない。
いや、俺という存在にはもしかしたら気付いているのかもしれないけれど、俺が誰なのかということは知らないようにも見えた。
仕事の合間を塗っては、くそ寒い外へと繰り出し、彼女の歌声を聞きに行く。そんな生活をしばらく続けている中で、見つけてしまったのは俺と同じぐらいにやばい奴。
彼女の演奏をじっと黙って見つめるあの男は、決まってこうして少し離れたところを歌を聞いていた。
……いや、聞いていた、というよりは。
狙っていた、という表現の方が正しかったのかもしれない。
全身黒で統一されたその風貌から、生気というものが感じられなくて、時折ぶつぶつと呟いていた。
その男が「今日だ……絶対今日、お、そう」と言っているのを聞いて、これは本気でまずいかもしれないと察したわけで。
俺の勘違いでなければ、男は「襲う」と言っていたのだと思う。
そんなわけで、黙って彼女の歌声を聞いていた群衆の一人から、ようやく抜け出す決心がつき、あの男が近づくよりも前に彼女に話しかけた。
『こんな寒いのに、指痛くないの?』
路上ライブ後の彼女に話しかけたとき、なかなか緊張していたことを彼女は知っていただろうか。