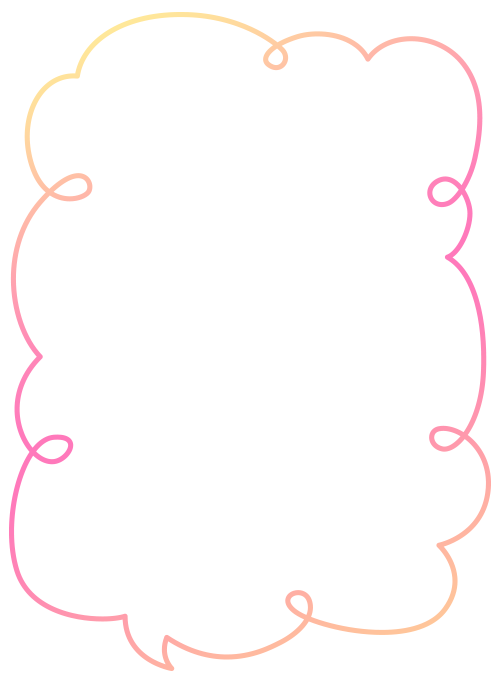「……思い出したんです。俺、あの歌声を聞いて路上ライブしようって決めたの」
「え……」
「2年前、俺あなたの歌声を聞いたんです。路上で歌ってた桜井さんの声を。あまりにもうますぎて、絶対上京してこの人みたいに歌おうって誓って。だから必死にバイトして金貯めて上京資金作って、それで──」
驚いた。足を止めてくれた人の中に、まさか彼がいたなんて。
わたしの声がきっかけで、この地にやってきたなんて。
黒く、純粋で真剣な瞳が、ぐっとわたしを捉える。
「くれませんか、その片思い」
「……っ」
「俺はアイドルじゃないから、桜井さんのこと傷つけたりしないです。なにか言ってくる人もいないです。あと、桜井さんの声、俺はだれよりも好きな自信あります。同じ歌い手だから、あのやるせない声、俺ならよく分かります。誰かを引き止めたいっていう、あの声、俺もずっと出してたから。多分、桜井さんのこと理解出来るの俺ぐらいだと思います。そういう自信しかないんです」
なんて、無責任なことを言うのだろう。この深く染み込んだ想いは簡単にあげられるものでもないのに。
歌手としてスタートラインに立った彼とわたしとでは、ぜんぜん世界が違うのに。
「俺のことだけ考えてくれませんか」
どうして、さっきからぐさぐさと彼の言葉が刺さり続けてしまうのだろう。
「俺なら、そんな風に笑わせたりしません。傷つけたりしません。たくさんの女の子じゃなくて、桜井さんだけを見てます」
──きっと、ほしかった言葉をくれるから。わたしだけを見てほしいと、そう願っていたことを彼に奪われてしまったから。だからこんなにも、胸が熱くなってしまうのかもしれない。
「え……」
「2年前、俺あなたの歌声を聞いたんです。路上で歌ってた桜井さんの声を。あまりにもうますぎて、絶対上京してこの人みたいに歌おうって誓って。だから必死にバイトして金貯めて上京資金作って、それで──」
驚いた。足を止めてくれた人の中に、まさか彼がいたなんて。
わたしの声がきっかけで、この地にやってきたなんて。
黒く、純粋で真剣な瞳が、ぐっとわたしを捉える。
「くれませんか、その片思い」
「……っ」
「俺はアイドルじゃないから、桜井さんのこと傷つけたりしないです。なにか言ってくる人もいないです。あと、桜井さんの声、俺はだれよりも好きな自信あります。同じ歌い手だから、あのやるせない声、俺ならよく分かります。誰かを引き止めたいっていう、あの声、俺もずっと出してたから。多分、桜井さんのこと理解出来るの俺ぐらいだと思います。そういう自信しかないんです」
なんて、無責任なことを言うのだろう。この深く染み込んだ想いは簡単にあげられるものでもないのに。
歌手としてスタートラインに立った彼とわたしとでは、ぜんぜん世界が違うのに。
「俺のことだけ考えてくれませんか」
どうして、さっきからぐさぐさと彼の言葉が刺さり続けてしまうのだろう。
「俺なら、そんな風に笑わせたりしません。傷つけたりしません。たくさんの女の子じゃなくて、桜井さんだけを見てます」
──きっと、ほしかった言葉をくれるから。わたしだけを見てほしいと、そう願っていたことを彼に奪われてしまったから。だからこんなにも、胸が熱くなってしまうのかもしれない。