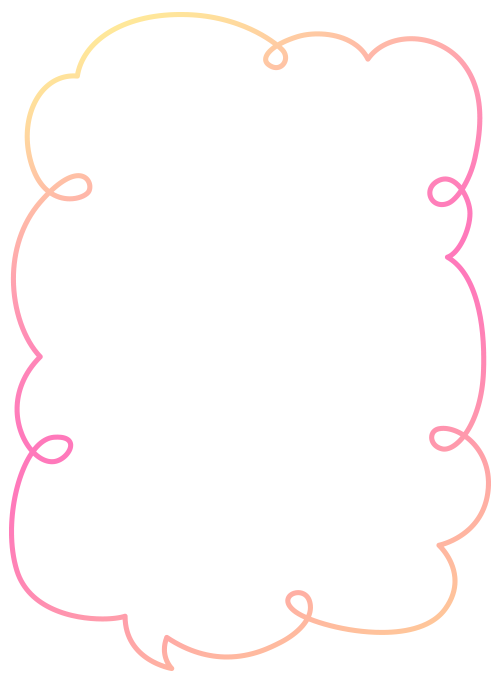「千野さん、とにかくこのままでは進学どころか留年です」
「やった、そしたらまた一緒にいられるね」
「勘弁してください。あなたはさっさと大学にいき、それ相応の彼氏を見つけて落ち着くべきです」
「いっくん……じゃなかった、一架くんがお嫁さんにしてくれるでしょ?」
「”先生”です。あと結婚はしない主義なので」
そういって、手元のプリントに視線を落とす。
夕日が差し込む教室で、睫毛がきらりと輝いて見えて、ついうっとりしてしまう。
長いなぁ、わたしより長いからうらやましい。目もぱっちり二重だし、顔の輪郭もシャープで、なにより顔が天才だ。
この顔なら彼女なんて作り放題なのに。
……あ、でも、彼女はいたっけ。一架くんが高校生のときは、毎日ちがう女の子と歩いているのを見た。
「?どうしたんですか、急に大人しくなって」
「嫌なことを思い出したんです~、せんせーが女遊びに精を出してたときの」
「ああ、そんなこともありましたね」
「あっさり認めないで!わたしはすっごい嫌だったんだから、毎日怒ってたの知らないでしょ」
「知りませんね、お子様には興味がないので」
「今はお子様じゃないもん」
これでも、それなりに可愛くなれるように努力はしている。
あのとき一架くんの彼女らしき人たちがずっと頭の中に残っていて、高校に入ってメイクを覚えたタイミングで真似するようになった。
少しでも一架くんのタイプの女の子になれるように。
でも、全然振り向いてくれない。
いつだってわたしのことをお子様扱いする。
「やった、そしたらまた一緒にいられるね」
「勘弁してください。あなたはさっさと大学にいき、それ相応の彼氏を見つけて落ち着くべきです」
「いっくん……じゃなかった、一架くんがお嫁さんにしてくれるでしょ?」
「”先生”です。あと結婚はしない主義なので」
そういって、手元のプリントに視線を落とす。
夕日が差し込む教室で、睫毛がきらりと輝いて見えて、ついうっとりしてしまう。
長いなぁ、わたしより長いからうらやましい。目もぱっちり二重だし、顔の輪郭もシャープで、なにより顔が天才だ。
この顔なら彼女なんて作り放題なのに。
……あ、でも、彼女はいたっけ。一架くんが高校生のときは、毎日ちがう女の子と歩いているのを見た。
「?どうしたんですか、急に大人しくなって」
「嫌なことを思い出したんです~、せんせーが女遊びに精を出してたときの」
「ああ、そんなこともありましたね」
「あっさり認めないで!わたしはすっごい嫌だったんだから、毎日怒ってたの知らないでしょ」
「知りませんね、お子様には興味がないので」
「今はお子様じゃないもん」
これでも、それなりに可愛くなれるように努力はしている。
あのとき一架くんの彼女らしき人たちがずっと頭の中に残っていて、高校に入ってメイクを覚えたタイミングで真似するようになった。
少しでも一架くんのタイプの女の子になれるように。
でも、全然振り向いてくれない。
いつだってわたしのことをお子様扱いする。