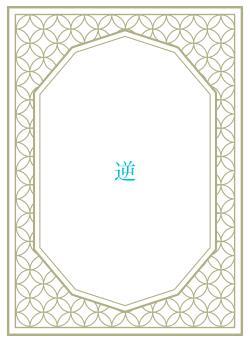「あやちゃん。て、つなごう」
幼なじみというには少し遠くて、友達というには少し近い。
それが、私と涼の関係だった。
のらりくらりと幼稚園、小学校、中学校が同じで、この春、同じ高校に入学した。
お互いの両親もときどき世間話するくらいで、きっと「これくらいがちょうどいい」という仲。
幼稚園は男女ごちゃまぜで遊ぶのはよくあることで、鬼ごっこで私の手をひいて一緒に逃げてくれた。
今思えば、まだ小さいのに優しくて、頼りがいのある男の子だったなって思う。
私の手をひいてくれた涼の手はやわらかくて、かわいい小さな手。
身長も私とほとんど変わらないくらいだった。
小さい頃からなんとなく好きだったけど、はっきりと自覚したのは、小学校六年生の修学旅行のときかな。
修学旅行と言っても学校に帰ったら事後学習がある行事で、移動教室っていうのが正しいかも。
そのときに泊まった宿で、肝試しをしたんだ。
肝試し担当の児童がいろんなところに待機してて、照明を落とした館内でおどかしてくるの。
班ごとにめぐるわけじゃなくて、肝試し担当の子以外は全員好きに移動するって感じだった。
懐中電灯を持っている子は数人いたけど、子どもの声が聞こえるだけで、あたりは暗くて。
どうしよう、って壁に寄りかかったまま、動けなかった。
いつおどかされるかわからない怖さよりも、真っ暗の中歩くことの方が怖かったんだ。
このまま動かずに、時間が過ぎるのを待とうと思っていたら。
「彩奈」
私とは違うクラスの、涼の声が聞こえた。
「え……」
気のせいかと思った。
「彩奈、大丈夫か?」
気のせいじゃないって気づいた。
暗い廊下で、声のしたほうに目を凝らす。
涼は私の右側に立って、心配そうに、でも凛々しい顔で私の目を見ていたんだ。
「りょ、涼……? え、なんでこんなとこいるの……?」
(涼って、こんなに背、高かったっけ?)
暗闇の中彼の横顔を見上げたとき、ビックリしたのはそれだけじゃなかった。
昔は、私のこと「あやちゃん」って呼んでたのに、今、涼は「彩奈」と名前で呼んだからだ。
昔って言っても、私と涼が幼稚園に通ってたころの話だから、七、八年前くらい前だけど。
それまでに涼と関わりがなかったわけじゃない。
でも、幼稚園の頃からこんなにも雰囲気が変わるんだって、ギャップを感じてしまったんだ。
「なんでって、捜したから」
「えっ」
さらっと言われて、反射的に声が出ちゃった。
「さ、捜してくれたの?」
「うん」
うん、って。
そんな当然のように言わないでよ。
「彩奈って、こういう暗いの苦手だろ」
「!」
驚いてかたまっていたら、
「あれ、違った? ごめん、心配になって……」
と、気まずそうに謝られちゃった。
「ううん。そんなことないよ……! ちょっと、怖かった」
心配してくれてありがとう、とだけは言えなくて。
でも、嬉しかった。
「ほんと? 歩ける?」
「たぶん。オバケとかは、大丈夫だから……」
「ははっ、頼りになるね」
「どういう意味よ」
涼は心配してくれるだけじゃなくて、笑わせてくれた。
涼の恋人になる人は幸せだなあ、なんて。
そう思ったのはなんでだろう。
「下の階行くか」
涼はあたりを見回し、階段を指差した。
「行こう」
うん、って返事をしようとしたの。
できなかったのは、涼が私の手を優しくつかんだから。
幼稚園の頃のやわらかさが信じられないくらい、男の子のかたくてまっすぐな手指になっていた。
手が昔とかわってて、どきっとしたんだ。
「涼、手……」
「どうせだれにも見えないよ。いざとなったら離せばいいんだし」
それはそうだけど!
ドギマギしているのは私だけなの? って、階段を下りながらほおをふくらませていた。
すると突然、涼が踊り場で立ち止まって振り返ったんだ。
ほっぺの中の空気を急いで吹き出す。
(く、暗いし、わからなかったよね)
「手、繋ごう」
涼はそう言った。
いつか、鬼ごっこで私の手をひいてくれたときと同じように。
はっきりした意志を感じる声音に、息をするのを忘れそうになった。
下の階の薄明かりが涼の瞳に光を入れて、ゆらゆらと揺れる。
さっき、涼の恋人になる人は幸せだなあって思った理由。
涼の声と優しい手にふれて、確信した。
——私が、涼の恋人になりたいからだ。
その修学旅行以来、涼と話す機会が少し増えた。
高校生となった今、同じ教室で彼の笑う横顔をながめている。
友達よりは親密で、でもあまり話すことはなくて。
幼なじみって感じじゃないけど、心のどこかでとても信頼している、そんな絆がある関係。
こう思っているのは私だけかもしれないけど。
(涼といるときの私は、すごく心地いいの)
ちょっぴり不器用で、人見知りなところがあって、でも私のことを笑わせてくれて。
そして、とても、とても優しい。
あとちょっと。
ほかの誰かに取られそうになるまでは、この想いを育てよう。
いつか、その手を私から繋げる日を信じて。
幼なじみというには少し遠くて、友達というには少し近い。
それが、私と涼の関係だった。
のらりくらりと幼稚園、小学校、中学校が同じで、この春、同じ高校に入学した。
お互いの両親もときどき世間話するくらいで、きっと「これくらいがちょうどいい」という仲。
幼稚園は男女ごちゃまぜで遊ぶのはよくあることで、鬼ごっこで私の手をひいて一緒に逃げてくれた。
今思えば、まだ小さいのに優しくて、頼りがいのある男の子だったなって思う。
私の手をひいてくれた涼の手はやわらかくて、かわいい小さな手。
身長も私とほとんど変わらないくらいだった。
小さい頃からなんとなく好きだったけど、はっきりと自覚したのは、小学校六年生の修学旅行のときかな。
修学旅行と言っても学校に帰ったら事後学習がある行事で、移動教室っていうのが正しいかも。
そのときに泊まった宿で、肝試しをしたんだ。
肝試し担当の児童がいろんなところに待機してて、照明を落とした館内でおどかしてくるの。
班ごとにめぐるわけじゃなくて、肝試し担当の子以外は全員好きに移動するって感じだった。
懐中電灯を持っている子は数人いたけど、子どもの声が聞こえるだけで、あたりは暗くて。
どうしよう、って壁に寄りかかったまま、動けなかった。
いつおどかされるかわからない怖さよりも、真っ暗の中歩くことの方が怖かったんだ。
このまま動かずに、時間が過ぎるのを待とうと思っていたら。
「彩奈」
私とは違うクラスの、涼の声が聞こえた。
「え……」
気のせいかと思った。
「彩奈、大丈夫か?」
気のせいじゃないって気づいた。
暗い廊下で、声のしたほうに目を凝らす。
涼は私の右側に立って、心配そうに、でも凛々しい顔で私の目を見ていたんだ。
「りょ、涼……? え、なんでこんなとこいるの……?」
(涼って、こんなに背、高かったっけ?)
暗闇の中彼の横顔を見上げたとき、ビックリしたのはそれだけじゃなかった。
昔は、私のこと「あやちゃん」って呼んでたのに、今、涼は「彩奈」と名前で呼んだからだ。
昔って言っても、私と涼が幼稚園に通ってたころの話だから、七、八年前くらい前だけど。
それまでに涼と関わりがなかったわけじゃない。
でも、幼稚園の頃からこんなにも雰囲気が変わるんだって、ギャップを感じてしまったんだ。
「なんでって、捜したから」
「えっ」
さらっと言われて、反射的に声が出ちゃった。
「さ、捜してくれたの?」
「うん」
うん、って。
そんな当然のように言わないでよ。
「彩奈って、こういう暗いの苦手だろ」
「!」
驚いてかたまっていたら、
「あれ、違った? ごめん、心配になって……」
と、気まずそうに謝られちゃった。
「ううん。そんなことないよ……! ちょっと、怖かった」
心配してくれてありがとう、とだけは言えなくて。
でも、嬉しかった。
「ほんと? 歩ける?」
「たぶん。オバケとかは、大丈夫だから……」
「ははっ、頼りになるね」
「どういう意味よ」
涼は心配してくれるだけじゃなくて、笑わせてくれた。
涼の恋人になる人は幸せだなあ、なんて。
そう思ったのはなんでだろう。
「下の階行くか」
涼はあたりを見回し、階段を指差した。
「行こう」
うん、って返事をしようとしたの。
できなかったのは、涼が私の手を優しくつかんだから。
幼稚園の頃のやわらかさが信じられないくらい、男の子のかたくてまっすぐな手指になっていた。
手が昔とかわってて、どきっとしたんだ。
「涼、手……」
「どうせだれにも見えないよ。いざとなったら離せばいいんだし」
それはそうだけど!
ドギマギしているのは私だけなの? って、階段を下りながらほおをふくらませていた。
すると突然、涼が踊り場で立ち止まって振り返ったんだ。
ほっぺの中の空気を急いで吹き出す。
(く、暗いし、わからなかったよね)
「手、繋ごう」
涼はそう言った。
いつか、鬼ごっこで私の手をひいてくれたときと同じように。
はっきりした意志を感じる声音に、息をするのを忘れそうになった。
下の階の薄明かりが涼の瞳に光を入れて、ゆらゆらと揺れる。
さっき、涼の恋人になる人は幸せだなあって思った理由。
涼の声と優しい手にふれて、確信した。
——私が、涼の恋人になりたいからだ。
その修学旅行以来、涼と話す機会が少し増えた。
高校生となった今、同じ教室で彼の笑う横顔をながめている。
友達よりは親密で、でもあまり話すことはなくて。
幼なじみって感じじゃないけど、心のどこかでとても信頼している、そんな絆がある関係。
こう思っているのは私だけかもしれないけど。
(涼といるときの私は、すごく心地いいの)
ちょっぴり不器用で、人見知りなところがあって、でも私のことを笑わせてくれて。
そして、とても、とても優しい。
あとちょっと。
ほかの誰かに取られそうになるまでは、この想いを育てよう。
いつか、その手を私から繋げる日を信じて。