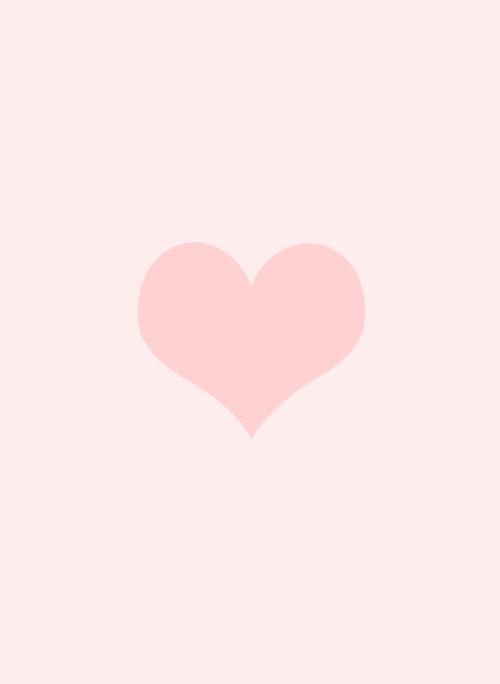離れた位置にある街灯の明かりが、真っ暗な一本道を薄く照らす。
その頼りない光を背に突き進めば、薄い暗闇の中にぽつんとひとつ古びたベンチが佇んでいる。
公園と呼ぶにはあまりにも寂しい、余った土地にただ置かれただけというのが相応しいようなそこには、珍しく先客がいて。
「よぉ」
「……ぇ」
月の光が淡く照らすその顔は、とても見覚えのある、というよりもむしろ見覚えしかなかった。
「……歩」
進藤歩。
隣の家の幼なじみだ。
「……なにしてんの」
「そりゃこっちのセリフだっての」
こちらを向いたまま、ベンチの真ん中に居座っていた歩が身体をずらしてスペースを空けたことに気づいたけれど、私はその場から動けなかった。
至極真っ当な返事だった。