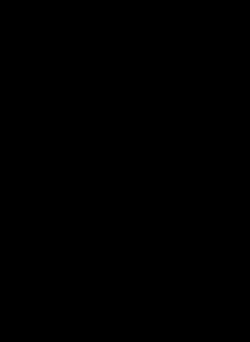第4章 明かされる秘密
最近、真の様子が変だ。なんか、ぼーっとしている感じ。授業もなんか気が乗らないのか板書もしていない。先生に指名されてもまるで聞こえていないかのように無視している。目を見ているとじぃーっと遠くを見ている遠い目をしていた。何?どうしたの?
そんな気持ちを持ったまま、私の大嫌いな体育の時間が来た。真のほうに気が散って私は体育どころではなかった。蕁麻疹が出るより、真が気になってしまった。ずっと、真を観察していると、あることに気が付いた。何か、痛かったのか顔をしかめた。
ドサッと嫌な音がした。
振り向くと、真が頭を抱えて倒れていた。それに気が付いた先生が私と真と仲のいい相川さんを呼び、保健室に連れていくよう、促された。保健室に連れて来たが、山本先生はいなかった。どこにいるか書いてあるとこを見ると見回り中と書いてあった。こんな時に…。困るよ…。真の体を見ると、全身汗だくだった。もしかして、熱中症かも。熱中症は、意識障害とか失神とか起こると聞いたことがある。とりあえず、冷やそう。
「相川さん。」
「どうした?立森さん。」
「真、熱中症の疑いがあるので、冷やしましょう。手伝ってください。」
「分かった。」
「そのタオルを、濡らして額に載せてください。」
私が知っている知識を使って、真の火照った体を冷やした。
しばらくして、真が目を覚ました。
「あれ?ここは?」
「保健室。」
「そっか。由希、ありがとう。」
「私だけじゃなくて、相川さんにもお礼を言って。」
「そっか。務、ありがとうな。」
「どういたしまして。」
これで、大丈夫。
そんな気持ちとは裏腹に私の心と頭の隅に「真は、病気なんじゃないのか」という考えが芽生えてきた。いつか、その考えが大きくなって、それが事実だったら怖い、と思ったので今はそっと胸にしまった。
でもね、私の予感や考えは基本的に当たってしまう。嘘だと願っても、多分これは逃れることのできない事実になってしまうだろう。
この、事実はまだ先のお話。それまでの、時間を大切にしなくてはならない。
真ともっと一緒にいたかったという未来の後悔を少しでもなくすためにー。
ー秘密ー
今日は、3ヶ月に1回の定期健診の日。しかも、今日は採血をしなくてはならない…。地獄…。アレルギーについて調べるのはかまわないけど、やっぱり採血は嫌だ。あぁ、このまま逃げたい。
採血室に向かっているときだった。
真に似ている人がいた。背格好とか髪型とかほとんど真にそっくり。その人は、入院着を着ていた。真、じゃないよね?病院に入院しているなんて聞いたこともない。入院しているなら、彼女の私にはいうはず…。でも、もし秘密で知られたくない事だったら…?怖い。
そんな気持ちのまま、採血室に入った。私は、すぐ呼ばれた。はぁ、気が重い。
「はーい。消毒しますね。」
ひゃっとする冷たい消毒は、何年たっても慣れない。しかも、これから痛いのが始まると思うと、逃げ出したくなる。
いや!しっかりするんだ、由希!14歳になっても注射が怖いというのは恥ずかしいと思うぞ!
自分の気持ちを奮い立たせて、やる決心がついた。
「はーい。チクっとしますね。」
お姉さんの声が遠く感じるよ…。
チクとする音が、した気がする。だって、痛いもん。まだ?まだ終わらないの?はやく、終わってよ!
気が付くと、採血は終わっていた。はぁ、やっと終わった。
採血の疲れで、トボトボしながら部屋を出たとき、また真そっくりな人がいた。ちょっと、悪いけど尾行させてもらおう。
着いた先は、庭園だった。綺麗で、秋桜とか沢山のお花が咲いていた。きれーい。って!真そっくりさんは⁉
捜していると、その人は私と同じように花を眺めていた。お花を見ている横顔は、やっぱり真だった。
「真?」
気が付くと、ポツリと言ってしまった。どうしよう、赤の他人だったら…。
「由希?」
その人は、正真正銘の真だった。
「え、なんで、ここにいるんだ?」
驚いた。その驚きは、隠せなかった。真も、驚いている。顔がもう、驚いているから。
「なんでって、こっちのセリフだよ。」
「あぁ、そうか。ごめん。でも、俺後で言うから先、言ってくれないか?」
「分かった。
私は、アレルギー科にお邪魔したの。今後のこととか、薬の件とか色々。」
「あぁ、なんか言ってたな。え、でもちょっと待って、薬って?」
「え、言ってなかったっけ?」
私は、まずそこに驚いた。
「アレルギーを抑えたりする薬とかお肌のコントロールに必要なの。」
「あぁ、そうなのか。」
「私は、話したから次真が言って。」
「そう、だな。俺もいつか言わなくちゃいけないと思っていた。」
「うん。」
「ショックを受けるかも知れないけれど、聞いてくれるか?」
真が言った言葉の語尾は震えていた。しかも、真の頬はビクビク震えている。
「うん。分かった。」
「じゃあ、話す。俺はー
病気なんだ。単心室症って言って。ごめん、黙っていて。」
確かに、ショックを受ける話だ。
「ううん。ねぇ、治る、んだよね?」
真の病気について知っておきたかった、というのもあるから聞いてみた。
「単身室状態の根本的な手術はない。」
いつの間にか、真も辛い顔をしていた。
「ねぇ、真。説明してくれてありがとう。実は、私もまだ隠し事をしていた。」
今まで、恐れていたことが今は言える。真にだったら、言える。
「え?」
「私は、食物アレルギーの他にもね、持病があるんだ。
それはね、コリン性蕁麻疹っていうの。」
ー 真sideー
コリン性蕁麻疹ー。聞きなれない名前だった。
はっきり言って、何それ?という気持ちだった。その気持ちが由希には分かったのか詳細を教えてくれた。
「コリン性蕁麻疹は、運動した後や入浴後に発汗をするでしょう?私の体は、それに反応して蕁麻疹が出てしまうんだ。それで、アレロックとアレグラとかを飲んでる。これ、真に比べたらなんてことないかも知れないけれど、自分の中では結構辛かったんだ。辛くて辛くて、夜明日体育とかがあったらベットで1人で泣いていたよ。」
ギュッと、抱きしめた。自然とだった。自分の彼女が辛くて、怖さと戦っている。その姿に、胸が押しつぶされた。
「ま、真?」
「えらい。よく頑張っているね。えらいよ。」
「ふぐっ。ふぐっ。」
由希は、可愛い顔をくしゃくしゃにして泣いた。由希が泣き終わるまで、俺は由希のそばにいる、と決めた。
抱きしめながら、俺は祈る。
神様。どうか、俺を、いや由希とよぼよぼの爺さん婆さんになるまで一緒に生きさせてください。それが、出来ないのなら俺はあなた達を恨むかもしれません。せめて、彼女のそばに長くいられますように。お願いします、神様。
ギュッと抱きしめ続けていると、由希はさらに声を上げた。その泣き声が庭園に響いた。
由希が帰った後、俺は自分のスマホで由希のコリン性蕁麻疹について調べた。
色々調べていくと、由希が教えてくれなかった事が沢山載っていた。
持っている人の割合を調べてみると、手が震えた。
〈コリン性蕁麻疹 約7%〉
約7%。これを知った時、由希はどんな気持ちだったのだろう。絶望?悲しみ?本人じゃ分からない気持ちに、触れたら嫌かもしれないから、言わないでおこう。
「早川真さん。お夕飯です。」
気が付くと、お夕飯時になっていた。でも、由希のコリン性蕁麻疹のことがショックだったからか食欲が失せ、半分も食べれずそのまま片づけた。申し訳ない、と思いながら。
消灯時間まで、あと30分の時だった。本を読んでいたら、スマホに着信が鳴った。誰だろう?と思って見てみると、由希だった。
〈今日は、突然ごめんね。〉
〈なんで謝るの?〉
〈だって、辛い思いをさせてしまったでしょう?〉
〈それは、こっちのセリフだ。由希、ごめんな。〉
〈大丈夫だよ。〉
〈そうか。〉
〈おやすみなさい、真。〉
〈あぁ、おやすみ由希。〉
由希との連絡をした後、俺は目が冴えて仕方がなかった。眠くなくて、目を瞑っても眠れなかった。
気が付くと、12時を回っていた。
「俺は、由希に何をしてあげられるのだろう?」
心の中の声がポツリ、と零れ出てしまったみたいだった。でも、個室だったからか誰も注意はしなかった。そのあと、俺は声を押し殺して泣いた。泣きまくった。泣きまくって疲れたからか、すぐに眠れた。
最近、真の様子が変だ。なんか、ぼーっとしている感じ。授業もなんか気が乗らないのか板書もしていない。先生に指名されてもまるで聞こえていないかのように無視している。目を見ているとじぃーっと遠くを見ている遠い目をしていた。何?どうしたの?
そんな気持ちを持ったまま、私の大嫌いな体育の時間が来た。真のほうに気が散って私は体育どころではなかった。蕁麻疹が出るより、真が気になってしまった。ずっと、真を観察していると、あることに気が付いた。何か、痛かったのか顔をしかめた。
ドサッと嫌な音がした。
振り向くと、真が頭を抱えて倒れていた。それに気が付いた先生が私と真と仲のいい相川さんを呼び、保健室に連れていくよう、促された。保健室に連れて来たが、山本先生はいなかった。どこにいるか書いてあるとこを見ると見回り中と書いてあった。こんな時に…。困るよ…。真の体を見ると、全身汗だくだった。もしかして、熱中症かも。熱中症は、意識障害とか失神とか起こると聞いたことがある。とりあえず、冷やそう。
「相川さん。」
「どうした?立森さん。」
「真、熱中症の疑いがあるので、冷やしましょう。手伝ってください。」
「分かった。」
「そのタオルを、濡らして額に載せてください。」
私が知っている知識を使って、真の火照った体を冷やした。
しばらくして、真が目を覚ました。
「あれ?ここは?」
「保健室。」
「そっか。由希、ありがとう。」
「私だけじゃなくて、相川さんにもお礼を言って。」
「そっか。務、ありがとうな。」
「どういたしまして。」
これで、大丈夫。
そんな気持ちとは裏腹に私の心と頭の隅に「真は、病気なんじゃないのか」という考えが芽生えてきた。いつか、その考えが大きくなって、それが事実だったら怖い、と思ったので今はそっと胸にしまった。
でもね、私の予感や考えは基本的に当たってしまう。嘘だと願っても、多分これは逃れることのできない事実になってしまうだろう。
この、事実はまだ先のお話。それまでの、時間を大切にしなくてはならない。
真ともっと一緒にいたかったという未来の後悔を少しでもなくすためにー。
ー秘密ー
今日は、3ヶ月に1回の定期健診の日。しかも、今日は採血をしなくてはならない…。地獄…。アレルギーについて調べるのはかまわないけど、やっぱり採血は嫌だ。あぁ、このまま逃げたい。
採血室に向かっているときだった。
真に似ている人がいた。背格好とか髪型とかほとんど真にそっくり。その人は、入院着を着ていた。真、じゃないよね?病院に入院しているなんて聞いたこともない。入院しているなら、彼女の私にはいうはず…。でも、もし秘密で知られたくない事だったら…?怖い。
そんな気持ちのまま、採血室に入った。私は、すぐ呼ばれた。はぁ、気が重い。
「はーい。消毒しますね。」
ひゃっとする冷たい消毒は、何年たっても慣れない。しかも、これから痛いのが始まると思うと、逃げ出したくなる。
いや!しっかりするんだ、由希!14歳になっても注射が怖いというのは恥ずかしいと思うぞ!
自分の気持ちを奮い立たせて、やる決心がついた。
「はーい。チクっとしますね。」
お姉さんの声が遠く感じるよ…。
チクとする音が、した気がする。だって、痛いもん。まだ?まだ終わらないの?はやく、終わってよ!
気が付くと、採血は終わっていた。はぁ、やっと終わった。
採血の疲れで、トボトボしながら部屋を出たとき、また真そっくりな人がいた。ちょっと、悪いけど尾行させてもらおう。
着いた先は、庭園だった。綺麗で、秋桜とか沢山のお花が咲いていた。きれーい。って!真そっくりさんは⁉
捜していると、その人は私と同じように花を眺めていた。お花を見ている横顔は、やっぱり真だった。
「真?」
気が付くと、ポツリと言ってしまった。どうしよう、赤の他人だったら…。
「由希?」
その人は、正真正銘の真だった。
「え、なんで、ここにいるんだ?」
驚いた。その驚きは、隠せなかった。真も、驚いている。顔がもう、驚いているから。
「なんでって、こっちのセリフだよ。」
「あぁ、そうか。ごめん。でも、俺後で言うから先、言ってくれないか?」
「分かった。
私は、アレルギー科にお邪魔したの。今後のこととか、薬の件とか色々。」
「あぁ、なんか言ってたな。え、でもちょっと待って、薬って?」
「え、言ってなかったっけ?」
私は、まずそこに驚いた。
「アレルギーを抑えたりする薬とかお肌のコントロールに必要なの。」
「あぁ、そうなのか。」
「私は、話したから次真が言って。」
「そう、だな。俺もいつか言わなくちゃいけないと思っていた。」
「うん。」
「ショックを受けるかも知れないけれど、聞いてくれるか?」
真が言った言葉の語尾は震えていた。しかも、真の頬はビクビク震えている。
「うん。分かった。」
「じゃあ、話す。俺はー
病気なんだ。単心室症って言って。ごめん、黙っていて。」
確かに、ショックを受ける話だ。
「ううん。ねぇ、治る、んだよね?」
真の病気について知っておきたかった、というのもあるから聞いてみた。
「単身室状態の根本的な手術はない。」
いつの間にか、真も辛い顔をしていた。
「ねぇ、真。説明してくれてありがとう。実は、私もまだ隠し事をしていた。」
今まで、恐れていたことが今は言える。真にだったら、言える。
「え?」
「私は、食物アレルギーの他にもね、持病があるんだ。
それはね、コリン性蕁麻疹っていうの。」
ー 真sideー
コリン性蕁麻疹ー。聞きなれない名前だった。
はっきり言って、何それ?という気持ちだった。その気持ちが由希には分かったのか詳細を教えてくれた。
「コリン性蕁麻疹は、運動した後や入浴後に発汗をするでしょう?私の体は、それに反応して蕁麻疹が出てしまうんだ。それで、アレロックとアレグラとかを飲んでる。これ、真に比べたらなんてことないかも知れないけれど、自分の中では結構辛かったんだ。辛くて辛くて、夜明日体育とかがあったらベットで1人で泣いていたよ。」
ギュッと、抱きしめた。自然とだった。自分の彼女が辛くて、怖さと戦っている。その姿に、胸が押しつぶされた。
「ま、真?」
「えらい。よく頑張っているね。えらいよ。」
「ふぐっ。ふぐっ。」
由希は、可愛い顔をくしゃくしゃにして泣いた。由希が泣き終わるまで、俺は由希のそばにいる、と決めた。
抱きしめながら、俺は祈る。
神様。どうか、俺を、いや由希とよぼよぼの爺さん婆さんになるまで一緒に生きさせてください。それが、出来ないのなら俺はあなた達を恨むかもしれません。せめて、彼女のそばに長くいられますように。お願いします、神様。
ギュッと抱きしめ続けていると、由希はさらに声を上げた。その泣き声が庭園に響いた。
由希が帰った後、俺は自分のスマホで由希のコリン性蕁麻疹について調べた。
色々調べていくと、由希が教えてくれなかった事が沢山載っていた。
持っている人の割合を調べてみると、手が震えた。
〈コリン性蕁麻疹 約7%〉
約7%。これを知った時、由希はどんな気持ちだったのだろう。絶望?悲しみ?本人じゃ分からない気持ちに、触れたら嫌かもしれないから、言わないでおこう。
「早川真さん。お夕飯です。」
気が付くと、お夕飯時になっていた。でも、由希のコリン性蕁麻疹のことがショックだったからか食欲が失せ、半分も食べれずそのまま片づけた。申し訳ない、と思いながら。
消灯時間まで、あと30分の時だった。本を読んでいたら、スマホに着信が鳴った。誰だろう?と思って見てみると、由希だった。
〈今日は、突然ごめんね。〉
〈なんで謝るの?〉
〈だって、辛い思いをさせてしまったでしょう?〉
〈それは、こっちのセリフだ。由希、ごめんな。〉
〈大丈夫だよ。〉
〈そうか。〉
〈おやすみなさい、真。〉
〈あぁ、おやすみ由希。〉
由希との連絡をした後、俺は目が冴えて仕方がなかった。眠くなくて、目を瞑っても眠れなかった。
気が付くと、12時を回っていた。
「俺は、由希に何をしてあげられるのだろう?」
心の中の声がポツリ、と零れ出てしまったみたいだった。でも、個室だったからか誰も注意はしなかった。そのあと、俺は声を押し殺して泣いた。泣きまくった。泣きまくって疲れたからか、すぐに眠れた。