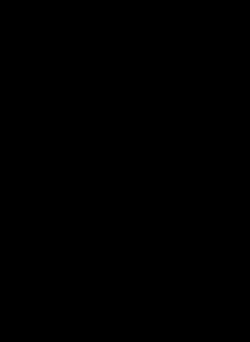第一章 始まりの朝
ミーンミンミン。
セミの鳴き声。夏の終わりが近づく朝。まるで、1日を知らせるアラームだ。
「ぅ、うぅ。」
時刻は、朝6時30分。
「由希ー。起きなさーい。」
階下から大きな声が聞こえるのは、私のお母さん。
「はーい。」
まだ寝たいのに…と思いつつこのまま寝たら朝から怒られるため渋々よっこらしょと身を起こした。
下に降りて、リビングへ向かうとお母さんが毎日のようにお弁当を詰めていた。私の通っている中学校は、給食制だ。でも、私は食物アレルギーというのを持っているためみんなと同じ給食が食べられない。しかも、学校に給食室がないからアレルギー対応給食がない。最悪ー。みんなと一緒に給食が食べたい、と何度思っただろう。あと何回、同じ思いをしなくてはならないんだろう。
ちなみに、私は卵と乳製品がだめだ。でも、その二つを使っていないパンなら食べられる。だから、今日の朝ご飯はパンだった。トーストに同じく乳・卵不使用のピーナッツバターを塗る。一枚目は、それで完成。二枚目は、マーガリンにいちごジャムでもなんでも付けて食べればマーガリンジャムの完成だ!
「いっただきまーす。」
うん!美味しい!口の中が幸せ!
あっという間に、私はトースト二枚を平らげた。
「行ってきまーす。」
「ちょっと、由希。お弁当忘れてるわよ。」
「あ、ごめんごめん。忘れてた。」
「んもう。危なかったわね。はい、お弁当。」
「ありがとう。行ってきまーす。」
「うん。行ってらっしゃい。」
暑い。秋が近いとはいえ、八月は朝でも気温が高い。今朝、ニュースで見たときは朝の時点で28℃ってお天気キャスターさんが言っていたっけ。時間に余裕が出るようにいつも早めに出てるからコンビニとかでクールダウンしたい。こういう時のコンビニって最強!中学校まで徒歩10分かかるかかからない位の近さ。コンビニは、中学がある途中にあるから歩いて五分程度。時刻は、7時30分。校門が開くのは、7時50分から8時05分までの間。クールダウンだけだけど失礼な気がするからスポーツドリンクでもなんでも買っていこうかな。
ティン、ティン。
コンビニにお客が来たよと知らせるためなのか室内に機械音が響いた。
コンビニ内には、皆クールダウンしに来たのか人がごった返していた。
コンビニ、涼しい。天国ー。
「あれ?由希もクールダウン中?」
人がごった返している中、声をかけてきたのは天野咲(あまのさき)。同級生で小学校からの親友だ。今は、残念ながらクラスは違っちゃったけど。
「そうだよ。咲も?」
「そうだよ。ついでに飲み物も買いに。」
「奇遇だね。私も、ついでに、ね。」
「同じだね。」
「むぅ。どれにしよう。」
水筒は、持ってきたけどなくなったら水道水を飲むことになる。そんなの嫌だ。
え〜っと。種類は、水、麦茶、紅茶、緑茶、コーヒー、スポーツドリンク。一番良さそうなのは、暑い夏にぴったり!スポーツドリンク!コーヒーを買ったら先生に怒られそうなのでやめておこう。後、コーヒーに入っているカフェインの摂取量も気をつけなくちゃ!コーヒーは、除外。
5分後。
「由希まだぁ~?」
咲の疲れた声が耳に入った。あれから5分後、変化なし!
私も、選ぶのに疲れてしまったため、最終的にスポーツドリンクを買った。
「ありがとうございました~。」
店員さんの声を後ろで聞きながら、私達は店を出た。
「由希。おはよう。」
教室入って、すぐ声をかけてきたのは、もう一人の親友盛岡早香(もりおかはやか)だ。
「早香。おはよう。」
「うん。おはよう。ねぇねぇ、由希。彼氏できた?」
「え、ぇぇぇぇぇぇぇ!?」
恋愛話が好物の早香は、たまにこういう質問をしてくる。
そのせいもあり、時々聞かれたとき私が驚きすぎて私の大声が教室中に響き、先生が「何事か⁉」と駆け付けたこともあった。そんなこともあり、クラスのみんなはもう慣れっこだけど、やっぱり朝はみんなびっくりするらしく私たちをジロジロと見ていた。はずっ!
「私はね、彼氏ってほどではないんだけど、好きな人がいるんだ。」
早香が頬を赤くしながらそう言った。
「だれ?」
「三年生の安田先輩。」
安田先輩は、恋愛に興味のない私ですら知ってる。学校一のイケメン、そしてファンの女の子たちからは安田王子とよばれている。私にとっちゃ、興味ないけど。安田先輩のことに興味を示さない人はすんごく少ないらしい。というか、いる?という感じらしい。私は、その数少ないうちの一人。確か、早香の情報によるとバスケ部のエース?だっけ?記憶がうろ覚えだからしっかりとは分からないけど。
「へぇ。頑張って。」
「うん!ありがとう!」
キーンコーンカーンコーン
1時間目の終わり、歴史の授業の終わりを告げる鐘が響いた。
「なぁ、次って体育だっけ?」
近くで話している男子の話に聞き耳を立てていると、「次」・「体育」という単語が聞こえた。次?体育?背筋がゾワリとした。私は、食物アレルギーのほかにもあるものを持っていてその理由が原因で体育が嫌い。しかも、今日は最悪の縄跳び強化練習がある。なんでかというと、九月にある縄跳び記録会が近づいているためらしい。縄跳び記録会とは、時間跳びをした後、種目別で自分で指定した技を2分間のうちに何回跳べてその時とんだ最高記録で勝負を挑む、というものだ。
とにかく、休み時間は10分しかない。急いで着替えないと遅刻になり、怒られてしまう。怒られるのは、絶対に嫌だ。
うちの中学のジャージは、青色。しかも、夏だから半袖に短パン。冬は、長袖に長ズボン。小学校に比べたら、まだマシなほうだ。小学校は、春・夏・秋は半袖短パン。冬は、半袖短パンに上にトレーナーを着るというものだった。しかし、6年生の1月に短パンにジャージみたいなのを着ていい、というものだ。私は、思った。「言うの遅っ!」と。そのまま、私は小学校を卒業した。
はぁ、気が重い。嫌だな。
【お願いしまーす!】
うぅ、ついに始まってしまった。まずは、学校縄跳びをやるらしい。学校縄跳びとは、音楽(校歌)に合わせて、指定された技をテンポよくやる、というやつだ。
最初は、前跳び。その後、駆け足跳び・ケンケン跳び・あやとびとか沢山やる。はっきり言って、めんどくさい。マジで。でも、「やれ」と言われたものはやるしかない。
実はいうと、私は自分で言うのも何なんだが縄跳びがまぁまぁ得意。3重跳びは、出来ないけど。高難易度の技でできるのは、後ろ2重跳び・リットル・ハヤブサは10回以上いける。後ろ2重跳びは、30回位は跳べる。リットルは、40回跳んだことがある。ハヤブサは、この二つと比べると全然跳べない。でも、「1回・2回しか跳べない。」とかじゃない。10回は、跳べる。あ、技の説明をしていなかった。リットルは、交差2重跳びで、ハヤブサはあやとびと2重跳びを一緒にやる技。後ろ2重跳びは、名前の通り後ろ跳びしながら2重跳びをするものだ。技の説明は、以上。後、私は小学校5年生の時、時間跳び(前跳び)で8分間跳んだこともあった。
学校縄跳びが終わったら、種目練習だ。
「次リットルー。」
【えぇー。】
先生の声に、クラス一同不満の声を出した。分からないけど、やったことのある人が少ない技だと思う。一方、私はリットルを散々やってきたからやったことがある。なので、私は言われた以上何も言えないので従うしかない。
ヒュンヒュン、と縄跳びが風を切る音がした。私の好きな音でもある。跳び終わった後、周りをグルリと見ると全員が私を見ていた。その目は、まるで漫画の目が点になっている様子ととても似ていて面白かった。思わず、クスリと笑ってしまった。そこで、気が付いた。もしかしたら、恐れていたものが出てしまうかもしれない、と。でも、それは遅かった。
体育が終わった後、腕や足を見ると、恐れていたものが沢山出ていた。それはーコリン性蕁麻疹(こりんせいじんましん)。一見、聞きなれない名前。だって、知名度は低いと思う。
コリン性蕁麻疹とは、運動後・入浴後に発汗すると出てくる。前に、ネットで調べたとき約7%の人しか持っていないらしい。つまり、その場に100人いたら約7人は、コリン性蕁麻疹を持っているかも知れない、という計算になる。多いようにも、少ないようにも私的には感じてしまう。これは、アレルギーとは違い生まれつきではない。
あれは、小学2年生の時。夏だった気がする。学校が夏休み期間なので遊びに出かけていた。
家族と沢山遊んだ。遊んだ遊んだ、と思ってホテルの部屋に戻った時、お母さんが私の足を見てこう言った。
「きゃあ、なにこれ⁉」
足を見てみると赤い斑点のようなものが足に出ていた。今まで、このようなことはなかった。突然の発症だった。なんの、前触れもなく。その時は、薬を塗って事なきことを終えた。
次に出たのは、3年生の秋。持久走大会に向けての練習をしていた。その練習が終わった後、友達の一言で2年生と同じ赤い斑点みたいなのが足に出ていた。その日は、早退して、いつも通っている皮膚科に受診した。診断の結果、「コリン性蕁麻疹だろう。」と言われた。そこから先、私は色々そのことについて調べた。持っている人の割合とか治療法とか原因とか対処法とか沢山調べた。何度も何度も読み返して、自分の頭に知識として入れた。ノートにも書いた。忘れないように付箋に書いた。〈私は、食物アレルギー(乳卵)・コリン性蕁麻疹を患っています〉と。6年生になって、思春期で皮脂の分泌が激しいからか沢山出るようになった。習い事の新体操にも影響した。新体操は、小学校一年生からはじめて、小学校卒業して辞めた。
もう、色々あって懲り懲りだ。コリン性蕁麻疹という縄張りから逃げ出したい、これも何度思ったことか。今は、アレルギーよりもこっちのことのほうが強く逃げ出したい、と思っている。中学に入ってからも、その思いはある。これから、一生私はこのような思いを抱えたまま生きていくのだろうか。
過去を振り返り終えて、私は、先生の所へ向かった。コリン性蕁麻疹が出た場合、冷やすといいらしい。誰にも、ばれず行かなくちゃ。体育教師・山田先生ももとへ。
「先生。」
「どうした?立森?」
「あの、汗に反応して蕁麻疹が出てしまったので保健室行っていいですか?」
「了解。分かった。」
ㇹッ。良かった。ひとまず、第一関門突破。
「ゴホッ ゴホッ。」
咳だ。運動した後、咳が出る。喘息って診断されてないのに。
「先生。蕁麻疹が出てきました。」
「あ、出てきちゃった?じゃあ、冷そっか。おいで。」
「失礼します。」
保健室の先生ー、山本絵麻先生は、若い女の先生でとても優しい。人当たりも良く、人望も厚い。なので、男女問わず人気が高い。
「え~っと。」
先生が何やら、戸棚の所でガサゴソとタオルを探していた。
「あった。ちょっと待ってて。」
「はい。」
先生が、タオルを濡らしてこちらにやってきた。
「よし。ちょっと足見せて。」
「はい。」
「あー、結構出てるね。風邪ひかないように気を付けて冷やしてね。」
先生は、そう言い、「はい。」と濡れたタオルを渡してくれた。
冷たーい。気持ちいい!
「あ、立森さん。こっちのほうがいいかも。」
先生がそういって見せてきたのは、濡れた藍染のタオルだった。
「あ、藍染の!」
「そう。藍染冷やし!どう?」
「とっても、冷たいです。」
藍染冷やしは、蕁麻疹がでた足によく効いた。しかし、さっきのタオルとは比べ物にならないくらいものすごく冷たい。ひょえ〜。
「ふふ。良かった。風邪、惹かないように気を付けてね。」
「はい。」
藍染冷やしは、まるでさっきまでの私の心の中のようだった。今は、先生のおかげで本当に少しだけ少しだけなんだけど青空が広がっていた。
はやく消えて。こんなのクラスの人になんか見られたくない。願っても願っても、いつもすぐには消えない。なんで?どうして?私は、このコリン性蕁麻疹のせいで、人生、邪魔されないだろうか。仕事とか就いた時に、影響は出ないのだろうか。神様は、なぜコリン性蕁麻疹の事について叶えてくれないのだろう。
キーンコーンカーンコーン
そんな私の思いを破るかのように、20分休み終了のチャイムが響き渡った。そのチャイムがなり終わった後、先生が私に声をかけてきた。
「立森さん?冷やしセット持って戻ってもいいわよ。」
「はい。」
冷やしセットとは、濡らしたタオルをいれるため、ボックスに入れ持ち運べるようにするためだ。
蕁麻疹は、まだ消えていない。心の中の青空が豪雪地帯の雪吹雪のように一瞬で変わった。怖いな。嫌だな。
そんな気持ちを抱えながら、保健室を出た。
3時間目と4時間目は、理科だった。教室に入っても、担当の先生はまだいなかった。
ふぅ、良かった、と安堵した気持ちになる。理科の先生は、怒るととても怖い。まぁ、事情話せば大丈夫なんだけどね。私が、自分の席に着いたとき丁度先生がやってきた。セーフ。
先生に言うのは、絶対に嫌だ。考えただけでも、気が引ける。
「は〜い。今日の学習は、体について。」
やったー!実は、私は膵臓とか腎臓とか大腿骨、HSPなど色々医学に関することを知るのにとても興味がある。それについてなんだけど、自分の部屋にあるホワイトボードには、付箋で「拡張型心筋症について」・「PTSDについて」・「脳震盪について」・「セカンドインパクト症候群」などなど病気について簡単にまとめたものを書いて貼っている。
それに、私の将来の夢は看護師だ。私は、母が元看護師。でも、うちらが生まれて辞めてしまった。今は、ホテルの清掃員をやっている。後ね、私が「看護師になる!」って決めたのはもう一つきっかけがあったんだ。
あれは、小学6年生の時。11月11日(土)に行われる青少年主張大会に向けて、6年生に募集をかけ、志願した人には原稿用紙1枚を渡しその1枚でざっくり書いていく。その内容で誰にしようか、先生たちの間で決めるというものだった。私は、アレルギーについて・将来の夢について書いた。ほかの子は、環境とか自分の将来の夢について書いた、と聞いた。その結果、見事私は学校代表に選ばれた。本番までの期間、文を増やしていき練習を続けてきた。
本番当日。足がガクガク震えた。でも、一生懸命スピーチした。市内のほかの小学校の人たちのスピーチを聞いていると怖くなったけど、頑張った。結果は、見事「最優秀賞」となり市内で1位になった。もらったものは、賞状・楯・図書カードなどなど豪華賞品をいただいた。
っと、授業に戻らないと先生に叱られる。
「え~、胃にある胃液は、釘を溶かすほどの威力がある。」
へぇ。胃液って釘を溶かすほど威力があるんだ。すごっ!覚えておいても損はなさそう。ノートに書いておこう。
「立森。」
え?私?
「はい。」
「問題。胃液の出る量は、1日どれくらいだ?」
ふっ。こんなの知っている。正解は、
「1日に2Lくらいです。」
「正解だ。」
【おぉー】
「座っていいぞ。」
はぁ。目立つのは好きじゃないんだけどな、などと考えていた。すると、無意識に腕や足を見ていた。消えかかってる、消えかかってる。良かった。
キーンコーンカーンコーン
3時間目が終わったー!良かったー。蕁麻疹は、すべて消えていた。休み時間の10分じゃ一階にある保健室に行くのは大変だしな。給食の時にしよう。
「由希?体育の終わった後、どこにいたの?」
「えっ?」
「だから、いなかったから。どこにいたの?」
「あぁ、ちょっと体調悪くて保健室に。」
早香、蕁麻疹は見ていないよね?
早香には、言っていない。食物アレルギーがあることは知っていても、コリン性蕁麻疹を持っていることは、咲にも伝えていない。心配をかけさせたくない。そんな思いを誰にも知らせたくない。
「大丈夫?無理してない?」
「うん。大丈夫。」
「ほんと?」
「もう、大丈夫だってばぁ。」
「そっか。そうだね。気を付けてね。」
「うん!」
大丈夫。バレていない、はず。早香にも咲にも、バレたくない。もし、2人にバレたらどうなるのだろう。怒るのかな?心配、かけさせちゃうのかな?怖い、な。
1段落ついたので、本を読もう。題名は、「キミが私を好きになる日」という本。題名を見て分かる通り、ラブストーリーだ。私は、恋愛はしたことないもののラブストーリーは好きだ。ちなみに、あらすじを言うと主人公はクラスで目立たず地味系な女の子。そんなある日、不治の病にかかり余命宣告を受ける。絶望の中、クラスで人気者の浅古君にひょんなことから助けてもらう。その1件以来、主人公は浅古君の事が好きになる。数少ない余命の中で、彼に振り向いてもらおうと努力する。2人の未来はー?という物語だ。
読み進めていくと、「わぁ、私もそんな恋してみたい!」などと思う。それができるのは、まだ先なんだろうな、とも思ってしまう。私は、今まで付き合った人おろか好きな人も出来たことがない。みんなは、好きな人がいるのに…。私は、おかしいのかな。変、なのかな。何にせよ、好きな人が見つかりますように。神様、お願いします。
放課後を迎えた。つまり、全授業が終わったということになる。
「早香。一緒に帰れる?」
「ごめん。今日部活だわ。」
「分かった。1人で帰るね。」
「うん。ごめん。」
早香が部活なら咲も部活あるだろうな。私は、蕁麻疹のこともあり帰宅部。早香はバスケ部。咲は、卓球部。いいなぁ、うらやましい。運動しても、蕁麻疹とか気にしないで出来て。ほんと、うらやましい。
教室を出て、校門に行く途中だった。運動部の子達が生き生きと活動しているのが窓から見えた。うらやましい。
「うらやましいな。」
思わず、声に出てしまった。慌てて、口をつぐんだけど校内がうるさかったからか私の言葉は誰の気にも留めなかったらしい。そのあと、すぐに逃げるかのように立ち去った。
「ただいま。」
「あ、由希。おかえりなさい。お父さん、もうすぐ着くって。」
「はーい。」
私のお父さんは、単身赴任している。しかも、遠い福岡で。ここは、福島だから結構な距離。時計を見ると時刻は午後5時30分。うん、まだ時間がある。2階に上がって、自分の部屋へと行く。机の上には、1冊のノート。このノートは、小説ノート。私は、趣味として小説を書いている。今までの総作品は、計10作品ぐらい。ちなみに、今執筆中の小説は、読むと同時に私を知ることができる。だけど、これは家族にも見せられない。だって、ここに書いてあるのは、私の秘密なんだから。
「ただいまー。」
お父さんの声。慌てて、下に行きリビングに入ると机の上に袋が置いてあった。何だろう?
「お、由希。おかえりなさい。そして、久し振り。」
「うん。ただいま。久し振り、お父さん。」
「あ、そうそう。2人にお土産。」
「何⁉」
お母さんは、お土産になると満腹でも食いつく。「なんで、食べられるの?」と聞いたら、「おやつは別腹なのよ。」って小さいころ教えてもらった。
「はい。由希には、あまおうラスク。由理には、いちごチョコレート。」
「わーい。」
お母さんが子供のように喜んだ。私は、内心では嬉しい!、と思ったが喜びの顔は出来なかった。その代わり、言葉に気持ちを載せて言った。「ありがとう。」と。
「って、ご飯!今日のご飯は、豪華だよ。腕によりをかけたわ。」
「はは、すごいな。」
お皿を並べ終えた後、全部を見るとやっぱり豪華だ。机の上には、唐揚げ、肉巻きポテト、野菜。うぅ、胃がもたれそう。それに肉肉しい。でも、まるでホテルのバイキング定食のよう。唐揚げを何個食べようか考えているときにお母さんに言われた。
「あ、由希。食べすぎ注意。吐くから。」
「はーい。」
そう。私は、胃、いや消化器系が弱いから食べ過ぎると吐いてしまう。油ものだってそうだ。前に、3回は絶対吐いてる。あれは、つらかったな…と思い出すと胃のあたりがひゅるんと冷たくなった、ように感じられた。
「いただきます。」
お父さんの号令で食事が始まった。まず、唐揚げ。ジューシー!肉も美味しい!次は、肉巻きポテト。美味い!甘辛いたれ(焼き肉のたれ)とよく合う!GOOD! 野菜も食べなくちゃ。チョレギドレッシング。う〜ん。幸せ!もう、胃が幸せ!
ふぅ。
「ご馳走様」
美味しかった。
「はーい。」
「あ、由希。新しい本はどうだ?面白いか?」
お父さんが聞いてきた。
面白い?面白いって何?
「分かんない。でも、多分面白い。」
「そうか。」
お父さんは、残念そうに短く言った。ひどく、悲しそうな顔をしていた。だって、私は、本で「面白い。」の判断がつかない。友達に貸した本の感想を聞くと「面白い。」とかえってきたのでよくわからなかったけど相槌は打った。それに、私は時々自分の気持ちが分からなくなることがある。私、本当に何なんだろう。その後、はぁ、とため息をついて眠った。
翌日のことだった。
ズキっと起きてすぐ頭痛がした。え、何?こんなこと、1度もない。そう思っているうちに、頭痛は治まった。
「「由希!おはよう。」」
咲と早香が声をかけてきた。
「おはよう。2人共。」
はぁ。経験したことのない出来事が朝に起きたため、気分は最悪。
「どうしたの?」
「大丈夫?」
私達は、皆心配性だ。「心配性にいいことなんてない!」と思っていた私は、生まれて初めて素晴らしい事でもあると知った。
「大丈夫。心配かけて、ごめん、ね?」
2人は何か言いたげだったけど、私は強引に話題を変えた。話していると3階の教室に着いて、咲と「放課後ー。」と言って別れた。そして、私は早香と2人で2年4組の教室に入った。
50×4。4時間目が終わり、給食の時間を迎えた。今日のご飯は、ご飯、味噌汁、白身魚のフライ、チリビーンズ、そして牛乳。私のメニューは、ご飯・白身魚のフライ・チリビーンズ・そして、終わりのゼリーとアーモンドミルク。ちなみに、ゼリーは保冷剤替わりだそう。
【いただきます。】
号令する日直の合図で給食の時間は始まる。まずは、白身魚のフライを1口。美味しい!目が漫画でいうハートマークになる。ご飯は、新潟県産のコシヒカリ。うん。美味しい。
心の中で食リポしながら、アーモンドミルクとゼリー以外を平らげた。まずは、ゼリー。ゼリーの味は、杏仁豆腐。温州ミカン味。うん。美味しい!実をいうと、ゼリーはゼリーでもこれはこんにゃくゼリー。そして、最後のアーモンドミルク!私は、砂糖入りが好きだ。だから、ほぼ毎朝アーモンドミルクを飲んでいる。時々、カフェイン0紅茶を飲むこともあるがミルクの代替としてアーモンドミルクを入れている。
グビグビと飲み、アーモンドミルクも飲み切った。
「ご馳走様でした。」
よし!読書!うわ〜。やっぱ食後の読書はいいな!
【皆さん、手を合わせてください。】
え?もう、ご馳走様の時間?時計を見ると確かにご馳走様の時間だった。また、読書で周りが見えなくなっていた。やっぱ、読書ってすごい!
そんなことを思いつつ、みんなと「ご馳走様でした。」をした。
五・六時間目も終わり、下校時刻になった。
やーっと帰れる!
「由希!早香!一緒に帰ろ!」
教室のドアで咲が手招きしていた。
「そうだね。」
「うん。帰ろ。」
「由希ー。好きな人、出来た?」
また、この質問か。でも質問者は咲なので早香ではない。
「いいや。出来てない。」
「じゃあ、気になっている人は?これはいるでしょ?」
「いないよ。」
「マジかー。もったいない。」
「もったいない」、か。私だって、恋愛したい。すんごくしたい。でも、恋の相手がいない。
しばらくの間、沈黙が続いた。最終的には、うちらの家の近くまで沈黙が続き、
「バイバイ。」と言って、別れた。
部屋に戻っても、恋愛のことばかり気にしていて、お母さんの呼びかけに気が付かなかった。気づいたときには、お母さんが怒鳴り声をあげていた。
下にリビングのテーブルを見るとじゃがバターがあった。乳製品がだめな私でも、バターはタンパク質量がすくないから大丈夫とはいえじゃがバターはちょっと…。
「由希!手伝って!」
「はーい。」
箸〜。箸はどこ〜?
箸を並べ終えて、ご飯も全部並べ終えたところで、丁度タイミング良くお父さんがやってきた。
「おっ!今日は、じゃがバターか〜。うまそうだな!なっ、由希!」
なぜ、私に話をふるのか。まぁ、どうでもいいけど。
「うん。」
「じゃ、いただきます。」
「「いただきます。」」
そう言って、じゃがバターを口に運ぶと今までとは何か違った。その正体がバターだと気が付くまでざっと5秒くらいかかった。
「お母さん。バター変えた?」
「えっ!分かるの?」
お母さんは、すっとんきょうな声をあげた。
「うん。」
「由希は、すごいわね〜。ねぇ、あなた。」
「あぁ。」
当たり前だ。お父さんが単身赴任から帰ってきたら母は毎回、これを作る。私は、バターを変えたぐらいしか分からない。けど、私よりすごい人がいた。その人は、産地まで当ててしまう位すごかった。その人のことを思うと、胸がギュッと傷んだ。だって、その人に「会いたい」と思っても会うことはできない。じゃがバターを美味しそうに食べるその人。考えれば考えるほど胸の奥がズシンと重くなった。
ミーンミンミン。
セミの鳴き声。夏の終わりが近づく朝。まるで、1日を知らせるアラームだ。
「ぅ、うぅ。」
時刻は、朝6時30分。
「由希ー。起きなさーい。」
階下から大きな声が聞こえるのは、私のお母さん。
「はーい。」
まだ寝たいのに…と思いつつこのまま寝たら朝から怒られるため渋々よっこらしょと身を起こした。
下に降りて、リビングへ向かうとお母さんが毎日のようにお弁当を詰めていた。私の通っている中学校は、給食制だ。でも、私は食物アレルギーというのを持っているためみんなと同じ給食が食べられない。しかも、学校に給食室がないからアレルギー対応給食がない。最悪ー。みんなと一緒に給食が食べたい、と何度思っただろう。あと何回、同じ思いをしなくてはならないんだろう。
ちなみに、私は卵と乳製品がだめだ。でも、その二つを使っていないパンなら食べられる。だから、今日の朝ご飯はパンだった。トーストに同じく乳・卵不使用のピーナッツバターを塗る。一枚目は、それで完成。二枚目は、マーガリンにいちごジャムでもなんでも付けて食べればマーガリンジャムの完成だ!
「いっただきまーす。」
うん!美味しい!口の中が幸せ!
あっという間に、私はトースト二枚を平らげた。
「行ってきまーす。」
「ちょっと、由希。お弁当忘れてるわよ。」
「あ、ごめんごめん。忘れてた。」
「んもう。危なかったわね。はい、お弁当。」
「ありがとう。行ってきまーす。」
「うん。行ってらっしゃい。」
暑い。秋が近いとはいえ、八月は朝でも気温が高い。今朝、ニュースで見たときは朝の時点で28℃ってお天気キャスターさんが言っていたっけ。時間に余裕が出るようにいつも早めに出てるからコンビニとかでクールダウンしたい。こういう時のコンビニって最強!中学校まで徒歩10分かかるかかからない位の近さ。コンビニは、中学がある途中にあるから歩いて五分程度。時刻は、7時30分。校門が開くのは、7時50分から8時05分までの間。クールダウンだけだけど失礼な気がするからスポーツドリンクでもなんでも買っていこうかな。
ティン、ティン。
コンビニにお客が来たよと知らせるためなのか室内に機械音が響いた。
コンビニ内には、皆クールダウンしに来たのか人がごった返していた。
コンビニ、涼しい。天国ー。
「あれ?由希もクールダウン中?」
人がごった返している中、声をかけてきたのは天野咲(あまのさき)。同級生で小学校からの親友だ。今は、残念ながらクラスは違っちゃったけど。
「そうだよ。咲も?」
「そうだよ。ついでに飲み物も買いに。」
「奇遇だね。私も、ついでに、ね。」
「同じだね。」
「むぅ。どれにしよう。」
水筒は、持ってきたけどなくなったら水道水を飲むことになる。そんなの嫌だ。
え〜っと。種類は、水、麦茶、紅茶、緑茶、コーヒー、スポーツドリンク。一番良さそうなのは、暑い夏にぴったり!スポーツドリンク!コーヒーを買ったら先生に怒られそうなのでやめておこう。後、コーヒーに入っているカフェインの摂取量も気をつけなくちゃ!コーヒーは、除外。
5分後。
「由希まだぁ~?」
咲の疲れた声が耳に入った。あれから5分後、変化なし!
私も、選ぶのに疲れてしまったため、最終的にスポーツドリンクを買った。
「ありがとうございました~。」
店員さんの声を後ろで聞きながら、私達は店を出た。
「由希。おはよう。」
教室入って、すぐ声をかけてきたのは、もう一人の親友盛岡早香(もりおかはやか)だ。
「早香。おはよう。」
「うん。おはよう。ねぇねぇ、由希。彼氏できた?」
「え、ぇぇぇぇぇぇぇ!?」
恋愛話が好物の早香は、たまにこういう質問をしてくる。
そのせいもあり、時々聞かれたとき私が驚きすぎて私の大声が教室中に響き、先生が「何事か⁉」と駆け付けたこともあった。そんなこともあり、クラスのみんなはもう慣れっこだけど、やっぱり朝はみんなびっくりするらしく私たちをジロジロと見ていた。はずっ!
「私はね、彼氏ってほどではないんだけど、好きな人がいるんだ。」
早香が頬を赤くしながらそう言った。
「だれ?」
「三年生の安田先輩。」
安田先輩は、恋愛に興味のない私ですら知ってる。学校一のイケメン、そしてファンの女の子たちからは安田王子とよばれている。私にとっちゃ、興味ないけど。安田先輩のことに興味を示さない人はすんごく少ないらしい。というか、いる?という感じらしい。私は、その数少ないうちの一人。確か、早香の情報によるとバスケ部のエース?だっけ?記憶がうろ覚えだからしっかりとは分からないけど。
「へぇ。頑張って。」
「うん!ありがとう!」
キーンコーンカーンコーン
1時間目の終わり、歴史の授業の終わりを告げる鐘が響いた。
「なぁ、次って体育だっけ?」
近くで話している男子の話に聞き耳を立てていると、「次」・「体育」という単語が聞こえた。次?体育?背筋がゾワリとした。私は、食物アレルギーのほかにもあるものを持っていてその理由が原因で体育が嫌い。しかも、今日は最悪の縄跳び強化練習がある。なんでかというと、九月にある縄跳び記録会が近づいているためらしい。縄跳び記録会とは、時間跳びをした後、種目別で自分で指定した技を2分間のうちに何回跳べてその時とんだ最高記録で勝負を挑む、というものだ。
とにかく、休み時間は10分しかない。急いで着替えないと遅刻になり、怒られてしまう。怒られるのは、絶対に嫌だ。
うちの中学のジャージは、青色。しかも、夏だから半袖に短パン。冬は、長袖に長ズボン。小学校に比べたら、まだマシなほうだ。小学校は、春・夏・秋は半袖短パン。冬は、半袖短パンに上にトレーナーを着るというものだった。しかし、6年生の1月に短パンにジャージみたいなのを着ていい、というものだ。私は、思った。「言うの遅っ!」と。そのまま、私は小学校を卒業した。
はぁ、気が重い。嫌だな。
【お願いしまーす!】
うぅ、ついに始まってしまった。まずは、学校縄跳びをやるらしい。学校縄跳びとは、音楽(校歌)に合わせて、指定された技をテンポよくやる、というやつだ。
最初は、前跳び。その後、駆け足跳び・ケンケン跳び・あやとびとか沢山やる。はっきり言って、めんどくさい。マジで。でも、「やれ」と言われたものはやるしかない。
実はいうと、私は自分で言うのも何なんだが縄跳びがまぁまぁ得意。3重跳びは、出来ないけど。高難易度の技でできるのは、後ろ2重跳び・リットル・ハヤブサは10回以上いける。後ろ2重跳びは、30回位は跳べる。リットルは、40回跳んだことがある。ハヤブサは、この二つと比べると全然跳べない。でも、「1回・2回しか跳べない。」とかじゃない。10回は、跳べる。あ、技の説明をしていなかった。リットルは、交差2重跳びで、ハヤブサはあやとびと2重跳びを一緒にやる技。後ろ2重跳びは、名前の通り後ろ跳びしながら2重跳びをするものだ。技の説明は、以上。後、私は小学校5年生の時、時間跳び(前跳び)で8分間跳んだこともあった。
学校縄跳びが終わったら、種目練習だ。
「次リットルー。」
【えぇー。】
先生の声に、クラス一同不満の声を出した。分からないけど、やったことのある人が少ない技だと思う。一方、私はリットルを散々やってきたからやったことがある。なので、私は言われた以上何も言えないので従うしかない。
ヒュンヒュン、と縄跳びが風を切る音がした。私の好きな音でもある。跳び終わった後、周りをグルリと見ると全員が私を見ていた。その目は、まるで漫画の目が点になっている様子ととても似ていて面白かった。思わず、クスリと笑ってしまった。そこで、気が付いた。もしかしたら、恐れていたものが出てしまうかもしれない、と。でも、それは遅かった。
体育が終わった後、腕や足を見ると、恐れていたものが沢山出ていた。それはーコリン性蕁麻疹(こりんせいじんましん)。一見、聞きなれない名前。だって、知名度は低いと思う。
コリン性蕁麻疹とは、運動後・入浴後に発汗すると出てくる。前に、ネットで調べたとき約7%の人しか持っていないらしい。つまり、その場に100人いたら約7人は、コリン性蕁麻疹を持っているかも知れない、という計算になる。多いようにも、少ないようにも私的には感じてしまう。これは、アレルギーとは違い生まれつきではない。
あれは、小学2年生の時。夏だった気がする。学校が夏休み期間なので遊びに出かけていた。
家族と沢山遊んだ。遊んだ遊んだ、と思ってホテルの部屋に戻った時、お母さんが私の足を見てこう言った。
「きゃあ、なにこれ⁉」
足を見てみると赤い斑点のようなものが足に出ていた。今まで、このようなことはなかった。突然の発症だった。なんの、前触れもなく。その時は、薬を塗って事なきことを終えた。
次に出たのは、3年生の秋。持久走大会に向けての練習をしていた。その練習が終わった後、友達の一言で2年生と同じ赤い斑点みたいなのが足に出ていた。その日は、早退して、いつも通っている皮膚科に受診した。診断の結果、「コリン性蕁麻疹だろう。」と言われた。そこから先、私は色々そのことについて調べた。持っている人の割合とか治療法とか原因とか対処法とか沢山調べた。何度も何度も読み返して、自分の頭に知識として入れた。ノートにも書いた。忘れないように付箋に書いた。〈私は、食物アレルギー(乳卵)・コリン性蕁麻疹を患っています〉と。6年生になって、思春期で皮脂の分泌が激しいからか沢山出るようになった。習い事の新体操にも影響した。新体操は、小学校一年生からはじめて、小学校卒業して辞めた。
もう、色々あって懲り懲りだ。コリン性蕁麻疹という縄張りから逃げ出したい、これも何度思ったことか。今は、アレルギーよりもこっちのことのほうが強く逃げ出したい、と思っている。中学に入ってからも、その思いはある。これから、一生私はこのような思いを抱えたまま生きていくのだろうか。
過去を振り返り終えて、私は、先生の所へ向かった。コリン性蕁麻疹が出た場合、冷やすといいらしい。誰にも、ばれず行かなくちゃ。体育教師・山田先生ももとへ。
「先生。」
「どうした?立森?」
「あの、汗に反応して蕁麻疹が出てしまったので保健室行っていいですか?」
「了解。分かった。」
ㇹッ。良かった。ひとまず、第一関門突破。
「ゴホッ ゴホッ。」
咳だ。運動した後、咳が出る。喘息って診断されてないのに。
「先生。蕁麻疹が出てきました。」
「あ、出てきちゃった?じゃあ、冷そっか。おいで。」
「失礼します。」
保健室の先生ー、山本絵麻先生は、若い女の先生でとても優しい。人当たりも良く、人望も厚い。なので、男女問わず人気が高い。
「え~っと。」
先生が何やら、戸棚の所でガサゴソとタオルを探していた。
「あった。ちょっと待ってて。」
「はい。」
先生が、タオルを濡らしてこちらにやってきた。
「よし。ちょっと足見せて。」
「はい。」
「あー、結構出てるね。風邪ひかないように気を付けて冷やしてね。」
先生は、そう言い、「はい。」と濡れたタオルを渡してくれた。
冷たーい。気持ちいい!
「あ、立森さん。こっちのほうがいいかも。」
先生がそういって見せてきたのは、濡れた藍染のタオルだった。
「あ、藍染の!」
「そう。藍染冷やし!どう?」
「とっても、冷たいです。」
藍染冷やしは、蕁麻疹がでた足によく効いた。しかし、さっきのタオルとは比べ物にならないくらいものすごく冷たい。ひょえ〜。
「ふふ。良かった。風邪、惹かないように気を付けてね。」
「はい。」
藍染冷やしは、まるでさっきまでの私の心の中のようだった。今は、先生のおかげで本当に少しだけ少しだけなんだけど青空が広がっていた。
はやく消えて。こんなのクラスの人になんか見られたくない。願っても願っても、いつもすぐには消えない。なんで?どうして?私は、このコリン性蕁麻疹のせいで、人生、邪魔されないだろうか。仕事とか就いた時に、影響は出ないのだろうか。神様は、なぜコリン性蕁麻疹の事について叶えてくれないのだろう。
キーンコーンカーンコーン
そんな私の思いを破るかのように、20分休み終了のチャイムが響き渡った。そのチャイムがなり終わった後、先生が私に声をかけてきた。
「立森さん?冷やしセット持って戻ってもいいわよ。」
「はい。」
冷やしセットとは、濡らしたタオルをいれるため、ボックスに入れ持ち運べるようにするためだ。
蕁麻疹は、まだ消えていない。心の中の青空が豪雪地帯の雪吹雪のように一瞬で変わった。怖いな。嫌だな。
そんな気持ちを抱えながら、保健室を出た。
3時間目と4時間目は、理科だった。教室に入っても、担当の先生はまだいなかった。
ふぅ、良かった、と安堵した気持ちになる。理科の先生は、怒るととても怖い。まぁ、事情話せば大丈夫なんだけどね。私が、自分の席に着いたとき丁度先生がやってきた。セーフ。
先生に言うのは、絶対に嫌だ。考えただけでも、気が引ける。
「は〜い。今日の学習は、体について。」
やったー!実は、私は膵臓とか腎臓とか大腿骨、HSPなど色々医学に関することを知るのにとても興味がある。それについてなんだけど、自分の部屋にあるホワイトボードには、付箋で「拡張型心筋症について」・「PTSDについて」・「脳震盪について」・「セカンドインパクト症候群」などなど病気について簡単にまとめたものを書いて貼っている。
それに、私の将来の夢は看護師だ。私は、母が元看護師。でも、うちらが生まれて辞めてしまった。今は、ホテルの清掃員をやっている。後ね、私が「看護師になる!」って決めたのはもう一つきっかけがあったんだ。
あれは、小学6年生の時。11月11日(土)に行われる青少年主張大会に向けて、6年生に募集をかけ、志願した人には原稿用紙1枚を渡しその1枚でざっくり書いていく。その内容で誰にしようか、先生たちの間で決めるというものだった。私は、アレルギーについて・将来の夢について書いた。ほかの子は、環境とか自分の将来の夢について書いた、と聞いた。その結果、見事私は学校代表に選ばれた。本番までの期間、文を増やしていき練習を続けてきた。
本番当日。足がガクガク震えた。でも、一生懸命スピーチした。市内のほかの小学校の人たちのスピーチを聞いていると怖くなったけど、頑張った。結果は、見事「最優秀賞」となり市内で1位になった。もらったものは、賞状・楯・図書カードなどなど豪華賞品をいただいた。
っと、授業に戻らないと先生に叱られる。
「え~、胃にある胃液は、釘を溶かすほどの威力がある。」
へぇ。胃液って釘を溶かすほど威力があるんだ。すごっ!覚えておいても損はなさそう。ノートに書いておこう。
「立森。」
え?私?
「はい。」
「問題。胃液の出る量は、1日どれくらいだ?」
ふっ。こんなの知っている。正解は、
「1日に2Lくらいです。」
「正解だ。」
【おぉー】
「座っていいぞ。」
はぁ。目立つのは好きじゃないんだけどな、などと考えていた。すると、無意識に腕や足を見ていた。消えかかってる、消えかかってる。良かった。
キーンコーンカーンコーン
3時間目が終わったー!良かったー。蕁麻疹は、すべて消えていた。休み時間の10分じゃ一階にある保健室に行くのは大変だしな。給食の時にしよう。
「由希?体育の終わった後、どこにいたの?」
「えっ?」
「だから、いなかったから。どこにいたの?」
「あぁ、ちょっと体調悪くて保健室に。」
早香、蕁麻疹は見ていないよね?
早香には、言っていない。食物アレルギーがあることは知っていても、コリン性蕁麻疹を持っていることは、咲にも伝えていない。心配をかけさせたくない。そんな思いを誰にも知らせたくない。
「大丈夫?無理してない?」
「うん。大丈夫。」
「ほんと?」
「もう、大丈夫だってばぁ。」
「そっか。そうだね。気を付けてね。」
「うん!」
大丈夫。バレていない、はず。早香にも咲にも、バレたくない。もし、2人にバレたらどうなるのだろう。怒るのかな?心配、かけさせちゃうのかな?怖い、な。
1段落ついたので、本を読もう。題名は、「キミが私を好きになる日」という本。題名を見て分かる通り、ラブストーリーだ。私は、恋愛はしたことないもののラブストーリーは好きだ。ちなみに、あらすじを言うと主人公はクラスで目立たず地味系な女の子。そんなある日、不治の病にかかり余命宣告を受ける。絶望の中、クラスで人気者の浅古君にひょんなことから助けてもらう。その1件以来、主人公は浅古君の事が好きになる。数少ない余命の中で、彼に振り向いてもらおうと努力する。2人の未来はー?という物語だ。
読み進めていくと、「わぁ、私もそんな恋してみたい!」などと思う。それができるのは、まだ先なんだろうな、とも思ってしまう。私は、今まで付き合った人おろか好きな人も出来たことがない。みんなは、好きな人がいるのに…。私は、おかしいのかな。変、なのかな。何にせよ、好きな人が見つかりますように。神様、お願いします。
放課後を迎えた。つまり、全授業が終わったということになる。
「早香。一緒に帰れる?」
「ごめん。今日部活だわ。」
「分かった。1人で帰るね。」
「うん。ごめん。」
早香が部活なら咲も部活あるだろうな。私は、蕁麻疹のこともあり帰宅部。早香はバスケ部。咲は、卓球部。いいなぁ、うらやましい。運動しても、蕁麻疹とか気にしないで出来て。ほんと、うらやましい。
教室を出て、校門に行く途中だった。運動部の子達が生き生きと活動しているのが窓から見えた。うらやましい。
「うらやましいな。」
思わず、声に出てしまった。慌てて、口をつぐんだけど校内がうるさかったからか私の言葉は誰の気にも留めなかったらしい。そのあと、すぐに逃げるかのように立ち去った。
「ただいま。」
「あ、由希。おかえりなさい。お父さん、もうすぐ着くって。」
「はーい。」
私のお父さんは、単身赴任している。しかも、遠い福岡で。ここは、福島だから結構な距離。時計を見ると時刻は午後5時30分。うん、まだ時間がある。2階に上がって、自分の部屋へと行く。机の上には、1冊のノート。このノートは、小説ノート。私は、趣味として小説を書いている。今までの総作品は、計10作品ぐらい。ちなみに、今執筆中の小説は、読むと同時に私を知ることができる。だけど、これは家族にも見せられない。だって、ここに書いてあるのは、私の秘密なんだから。
「ただいまー。」
お父さんの声。慌てて、下に行きリビングに入ると机の上に袋が置いてあった。何だろう?
「お、由希。おかえりなさい。そして、久し振り。」
「うん。ただいま。久し振り、お父さん。」
「あ、そうそう。2人にお土産。」
「何⁉」
お母さんは、お土産になると満腹でも食いつく。「なんで、食べられるの?」と聞いたら、「おやつは別腹なのよ。」って小さいころ教えてもらった。
「はい。由希には、あまおうラスク。由理には、いちごチョコレート。」
「わーい。」
お母さんが子供のように喜んだ。私は、内心では嬉しい!、と思ったが喜びの顔は出来なかった。その代わり、言葉に気持ちを載せて言った。「ありがとう。」と。
「って、ご飯!今日のご飯は、豪華だよ。腕によりをかけたわ。」
「はは、すごいな。」
お皿を並べ終えた後、全部を見るとやっぱり豪華だ。机の上には、唐揚げ、肉巻きポテト、野菜。うぅ、胃がもたれそう。それに肉肉しい。でも、まるでホテルのバイキング定食のよう。唐揚げを何個食べようか考えているときにお母さんに言われた。
「あ、由希。食べすぎ注意。吐くから。」
「はーい。」
そう。私は、胃、いや消化器系が弱いから食べ過ぎると吐いてしまう。油ものだってそうだ。前に、3回は絶対吐いてる。あれは、つらかったな…と思い出すと胃のあたりがひゅるんと冷たくなった、ように感じられた。
「いただきます。」
お父さんの号令で食事が始まった。まず、唐揚げ。ジューシー!肉も美味しい!次は、肉巻きポテト。美味い!甘辛いたれ(焼き肉のたれ)とよく合う!GOOD! 野菜も食べなくちゃ。チョレギドレッシング。う〜ん。幸せ!もう、胃が幸せ!
ふぅ。
「ご馳走様」
美味しかった。
「はーい。」
「あ、由希。新しい本はどうだ?面白いか?」
お父さんが聞いてきた。
面白い?面白いって何?
「分かんない。でも、多分面白い。」
「そうか。」
お父さんは、残念そうに短く言った。ひどく、悲しそうな顔をしていた。だって、私は、本で「面白い。」の判断がつかない。友達に貸した本の感想を聞くと「面白い。」とかえってきたのでよくわからなかったけど相槌は打った。それに、私は時々自分の気持ちが分からなくなることがある。私、本当に何なんだろう。その後、はぁ、とため息をついて眠った。
翌日のことだった。
ズキっと起きてすぐ頭痛がした。え、何?こんなこと、1度もない。そう思っているうちに、頭痛は治まった。
「「由希!おはよう。」」
咲と早香が声をかけてきた。
「おはよう。2人共。」
はぁ。経験したことのない出来事が朝に起きたため、気分は最悪。
「どうしたの?」
「大丈夫?」
私達は、皆心配性だ。「心配性にいいことなんてない!」と思っていた私は、生まれて初めて素晴らしい事でもあると知った。
「大丈夫。心配かけて、ごめん、ね?」
2人は何か言いたげだったけど、私は強引に話題を変えた。話していると3階の教室に着いて、咲と「放課後ー。」と言って別れた。そして、私は早香と2人で2年4組の教室に入った。
50×4。4時間目が終わり、給食の時間を迎えた。今日のご飯は、ご飯、味噌汁、白身魚のフライ、チリビーンズ、そして牛乳。私のメニューは、ご飯・白身魚のフライ・チリビーンズ・そして、終わりのゼリーとアーモンドミルク。ちなみに、ゼリーは保冷剤替わりだそう。
【いただきます。】
号令する日直の合図で給食の時間は始まる。まずは、白身魚のフライを1口。美味しい!目が漫画でいうハートマークになる。ご飯は、新潟県産のコシヒカリ。うん。美味しい。
心の中で食リポしながら、アーモンドミルクとゼリー以外を平らげた。まずは、ゼリー。ゼリーの味は、杏仁豆腐。温州ミカン味。うん。美味しい!実をいうと、ゼリーはゼリーでもこれはこんにゃくゼリー。そして、最後のアーモンドミルク!私は、砂糖入りが好きだ。だから、ほぼ毎朝アーモンドミルクを飲んでいる。時々、カフェイン0紅茶を飲むこともあるがミルクの代替としてアーモンドミルクを入れている。
グビグビと飲み、アーモンドミルクも飲み切った。
「ご馳走様でした。」
よし!読書!うわ〜。やっぱ食後の読書はいいな!
【皆さん、手を合わせてください。】
え?もう、ご馳走様の時間?時計を見ると確かにご馳走様の時間だった。また、読書で周りが見えなくなっていた。やっぱ、読書ってすごい!
そんなことを思いつつ、みんなと「ご馳走様でした。」をした。
五・六時間目も終わり、下校時刻になった。
やーっと帰れる!
「由希!早香!一緒に帰ろ!」
教室のドアで咲が手招きしていた。
「そうだね。」
「うん。帰ろ。」
「由希ー。好きな人、出来た?」
また、この質問か。でも質問者は咲なので早香ではない。
「いいや。出来てない。」
「じゃあ、気になっている人は?これはいるでしょ?」
「いないよ。」
「マジかー。もったいない。」
「もったいない」、か。私だって、恋愛したい。すんごくしたい。でも、恋の相手がいない。
しばらくの間、沈黙が続いた。最終的には、うちらの家の近くまで沈黙が続き、
「バイバイ。」と言って、別れた。
部屋に戻っても、恋愛のことばかり気にしていて、お母さんの呼びかけに気が付かなかった。気づいたときには、お母さんが怒鳴り声をあげていた。
下にリビングのテーブルを見るとじゃがバターがあった。乳製品がだめな私でも、バターはタンパク質量がすくないから大丈夫とはいえじゃがバターはちょっと…。
「由希!手伝って!」
「はーい。」
箸〜。箸はどこ〜?
箸を並べ終えて、ご飯も全部並べ終えたところで、丁度タイミング良くお父さんがやってきた。
「おっ!今日は、じゃがバターか〜。うまそうだな!なっ、由希!」
なぜ、私に話をふるのか。まぁ、どうでもいいけど。
「うん。」
「じゃ、いただきます。」
「「いただきます。」」
そう言って、じゃがバターを口に運ぶと今までとは何か違った。その正体がバターだと気が付くまでざっと5秒くらいかかった。
「お母さん。バター変えた?」
「えっ!分かるの?」
お母さんは、すっとんきょうな声をあげた。
「うん。」
「由希は、すごいわね〜。ねぇ、あなた。」
「あぁ。」
当たり前だ。お父さんが単身赴任から帰ってきたら母は毎回、これを作る。私は、バターを変えたぐらいしか分からない。けど、私よりすごい人がいた。その人は、産地まで当ててしまう位すごかった。その人のことを思うと、胸がギュッと傷んだ。だって、その人に「会いたい」と思っても会うことはできない。じゃがバターを美味しそうに食べるその人。考えれば考えるほど胸の奥がズシンと重くなった。