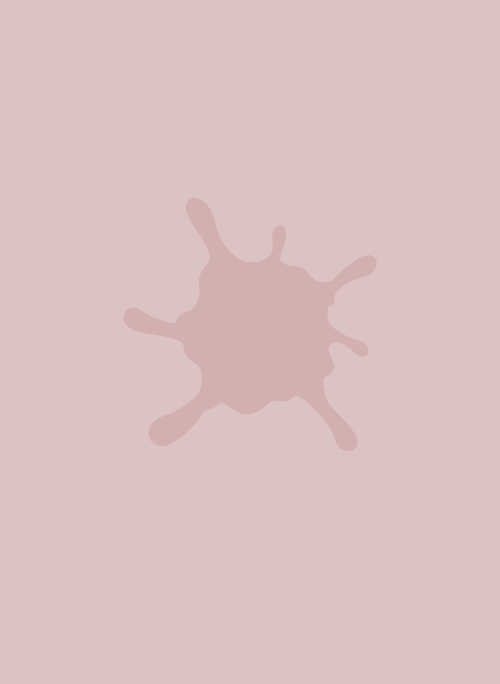「…夜野、朝?」
―記憶が、戻った。
朝くんのかけてくれた言葉、表情、一緒に見た風景、全てが頭に鮮明に蘇る。
「思い、出せた…ごめん…朝くん…」
何度も謝って涙を流す私は、彼の胸に顔を近づけた。ぎゅっとふたりで抱き合う。傘が落ちて濡れても、どうでもよかった。
「よかった、よかったあ…」
「消えたら、だめでしょ」
「っえ?」
私が言うのが珍しかったのか、どこか朝くんは惚けて聞き返す。
「朝くんとの記憶も思い出も、やっぱり、消えたら、だめ、です」
「…消えてた奴が言うなよ……」
ああ、私は本当に運がいい。朝くんを思い出せて、こうして巡り会えて、雨が降って。
―ねぇ、翠さん
―俺はくま深い方が好きだけど。
何度も私の名前を呼んでくれた誰かは、ほしい言葉をいつだってくれた誰かは…
「朝くんだった……」
朝くんと道のど真ん中で、傘も放り投げたまま、記憶を取り戻した私は抱き合っていた。
この時間が、ずっと、続けばいいのに。
この雨が降り止まないことを、願っていた。
゜
゜
゜