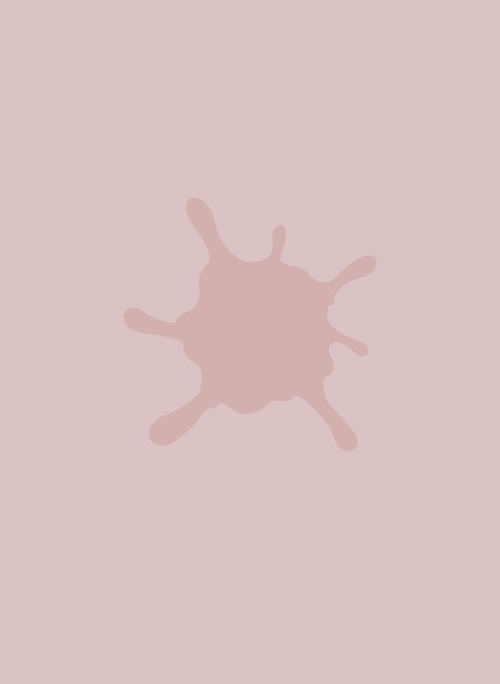すぐに謝ろうとすると、その前に、今度は東花が「そう」と縦に頷いた。
「…俺、やきもち焼いて嫉妬してた」
東花は優しく鼻で笑った。その笑顔は、どこか朝くんの笑顔を思い出させた。
「バカみたい。あいつが翠に近付いたからって俺、翠に…、勝手に嫉妬、した。なんであいつで、なんで俺じゃないのかって」
「と、東花、顔、赤…」
「あ?黙れ見んな?」
いつものツンツンしている東花に戻ったようで、思わず口元が緩んでしまった。
「俺は、毎日をどうでもよさそうに生きてるけれど、遅れてでもちゃーんと学校に来る、不思議な、お姫様が大好きだったよ」
「…お、おひめさまて」
思わずポカンと口を開ける。そんな私を見て、また東花は小さく笑っていた。
「ほら、あの…誰だっけ、小鳥?にも言われただろ。ちゃんと体倒して休めろよ」
耳を赤くした東花は、パイプ椅子から立ち上がった。
「行く、の?」
「伝えたいこと、伝えれてよかった」
「…行っちゃうか、そっか、うん、ばいばい」
「なに落ち込んでんの?翠の人は、あのクズだろ」
東花に笑われてしまった。
違うし、とも、そうです、とも言えない。言葉にできない、なんとも不思議な感情だった。なんなのだろう、この感情は。