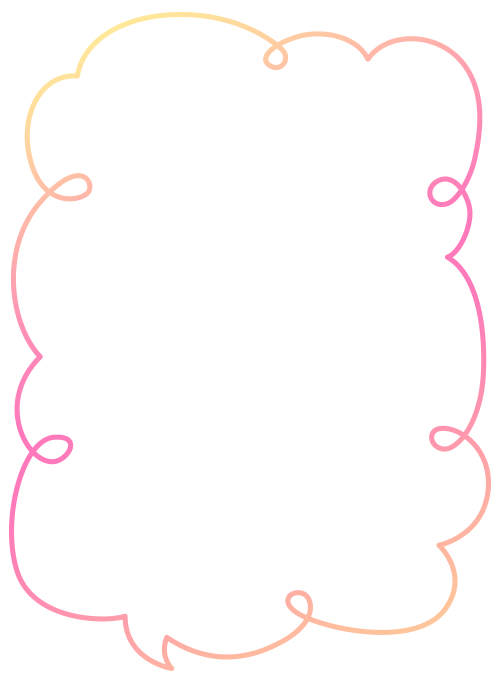6月27日。
璃玖先輩の誕生日一日前。
璃玖先輩の記憶が、リセットされる前日。
「璃玖先輩、どこか行きたいところ、ありますか?」
「どこでも。」
「じゃあ、僕の家、とか……。」
「……へ?」
「いや、あの、やましいことは何も……。」
「日付が変わる前には送りますから!」
「あはは、ちーくんって本当面白いよね。」
「あんまりいいものはないですけど……。」
「ううん、いいの。」
「私は、今日ちーくんといられればそれでいい。」
……あ、ズルい。
照れてしまいそうだった。
「もう、5時なんだね。」
「送ります。」
「ちーくんの家で19歳迎えてもいい気がしてきた。」
「……ダメですよ、そんなの。“明日の璃玖先輩”が驚きます。」
「じゃあ、“明日の私”に向けてメモを残しておけばいい。」
「起きてすぐに残されたメモを見ても、自分の筆跡かどうかなんてわからないんじゃないですか。」
「ちーくんって現実主義だね。」
「……僕だって怖いんですよ。“今日の璃玖先輩”が、もう明日にはいなくなっちゃうから。」
「ねぇ、智紘くん。」
璃玖先輩が僕の名前を呼ぶ。
「智紘くんは、明日も“私”に会ってくれるよね?」
「当たり前です。」
「じゃあさ、“智紘くんを忘れた私”って、“私”じゃないのかな?」
「……違います。」
「智紘くんは、私を見つけてくれるんだよね?」
「はい。」
「なら、いいじゃん。私は、智紘くんが側にいてくれるなら、それでいいよ。」
「そりゃあね、“自分が記憶障害だ”って知った時は辛かったけど、少なくとも、“今”は、“この時間は”、独りじゃないから。」
「だから、大丈夫。大丈夫なんだよ。」
「……本当に、いいんですか。先輩の家に泊まるなんて。」
「うん。“明日の私”にはこんな格好いい彼氏がいるんだよーって自慢したいからね。」
「先輩って、そんなキャラでしたっけ?」
「さあね」
それから僕は、先輩の家で先輩が作ってくれた手料理を食べ、お風呂をいただくという十分すぎる接待を受けた。
「ちーくん」
「何ですか、先輩。」
「私が起きたら、ちゃんと自己紹介してね。あと私の説明も。」
「わかってます。」
「ちーくん」
「何かありましたか、先輩。」
「好きだよ」
「僕もです。」
「おやすみ」
「おやすみなさい。」