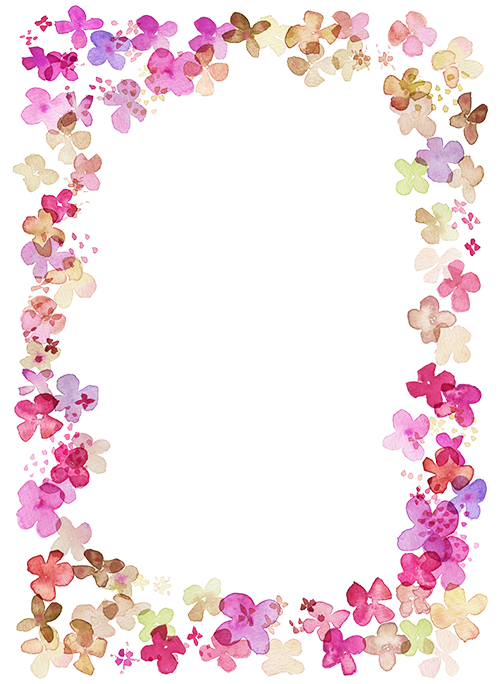(希望なんて名ばかりの絶望の地。……誰だか知らないが、皮肉な名前をつけたものだ)
リオネルがこっそり嘆息した時、「聞いているのかしら!?」というアルレットのヒステリックな声が聞こえてきた。
思考に意識を飛ばしていたリオネルは、続く王妃の言葉を聞き逃してしまったようだ。
王妃は赤い唇をゆがめて、イライラとテーブルの上を爪で叩いていた。
「申し訳ありません。聞いておりませんでした」
慇(いん)懃(ぎん)に答えると、アルレットの細い眉が跳ね上がった。
どうでもいいが、眉を抜きすぎだ。
アルレットの眉は、まるでペンで描いた一本の線のように細い。
というかあれは本当に線だけで、毛は存在していないんじゃないのかと、リオネルは再び思考をどこか遠くへ飛ばしかけた。それくらい、香水臭いこの部屋でこの女の前にいることが苦痛で仕方がなかったのだ。
アルレットは目に見えて苛立っているようだが、ふうと息を吐くと、一転して笑顔になった。
(……今日の王妃は本当に不気味だな)
こんな不気味な王妃のもとからは早々に立ち去るに限る。
さっさと彼女の要件を聞いて、部屋から出ていこうと考えたリオネルは、アルレットの言葉に表情を取り繕うことも忘れて目を見張ることとなった。
リオネルがこっそり嘆息した時、「聞いているのかしら!?」というアルレットのヒステリックな声が聞こえてきた。
思考に意識を飛ばしていたリオネルは、続く王妃の言葉を聞き逃してしまったようだ。
王妃は赤い唇をゆがめて、イライラとテーブルの上を爪で叩いていた。
「申し訳ありません。聞いておりませんでした」
慇(いん)懃(ぎん)に答えると、アルレットの細い眉が跳ね上がった。
どうでもいいが、眉を抜きすぎだ。
アルレットの眉は、まるでペンで描いた一本の線のように細い。
というかあれは本当に線だけで、毛は存在していないんじゃないのかと、リオネルは再び思考をどこか遠くへ飛ばしかけた。それくらい、香水臭いこの部屋でこの女の前にいることが苦痛で仕方がなかったのだ。
アルレットは目に見えて苛立っているようだが、ふうと息を吐くと、一転して笑顔になった。
(……今日の王妃は本当に不気味だな)
こんな不気味な王妃のもとからは早々に立ち去るに限る。
さっさと彼女の要件を聞いて、部屋から出ていこうと考えたリオネルは、アルレットの言葉に表情を取り繕うことも忘れて目を見張ることとなった。