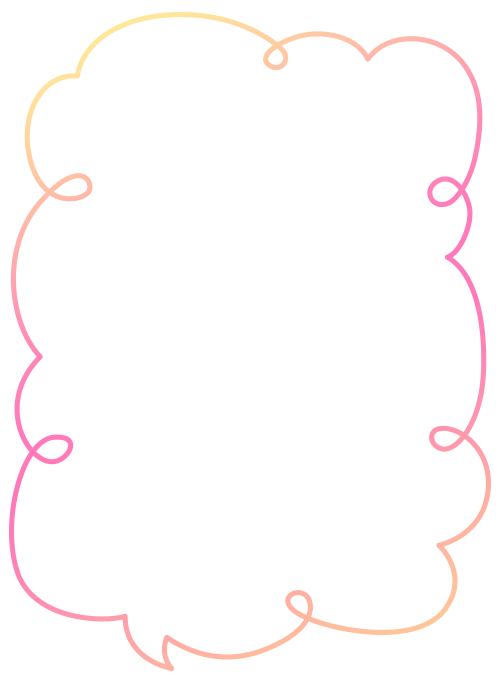――夏目side
きっかけを作るのに必死だった。
澄ました顔で、何も考えてないような顔をして、いつだって彼女の前に座って。
自分という存在を無理矢理にでも視界に入れてやろうという魂胆は今思えば滑稽でしかなかっただろう。
7時43分。
肌を突き刺すようなひんやりとした風に目を瞑る。
と同時に、少し、呼吸を整えるように大きく息をすれば、肺が冷たさで浸食されていく。
見慣れたバス停前では箱型の大型車が待ち人を乗せる為にゆっくりと停車する。
寒さから逃げるように乗り込めば、自然と視線は決まった場所へと流れていく。
一番後ろ、向かって左にはこれまた見慣れた、というよりも目的の彼女が静かに佇む。
彼女から見れば右側になるその座席に、俺は素知らぬ顔で前列を確保。
油断すると、30代半ばのサラリーマンに横取りされかけるので、最近はバス停でも一番前を陣取るよう努めている。
そんな俺の小さな計画など知りもしない彼女は、艶やかな光を放つ髪の隙間からイヤホンを装着し音楽を聞いている。
同じクラスというだけで接点はない。ましてや社交的ではない互いの性格上、話すタイミングさえ訪れない。
気になる子の前に平然とした顔で座るのが、俺の精一杯のアピール。
自分でもこんなにも小心者だったのかと驚かされる。そして呆れて笑いさえ込み上げてくる。
きっかけを作るのに必死だった。
澄ました顔で、何も考えてないような顔をして、いつだって彼女の前に座って。
自分という存在を無理矢理にでも視界に入れてやろうという魂胆は今思えば滑稽でしかなかっただろう。
7時43分。
肌を突き刺すようなひんやりとした風に目を瞑る。
と同時に、少し、呼吸を整えるように大きく息をすれば、肺が冷たさで浸食されていく。
見慣れたバス停前では箱型の大型車が待ち人を乗せる為にゆっくりと停車する。
寒さから逃げるように乗り込めば、自然と視線は決まった場所へと流れていく。
一番後ろ、向かって左にはこれまた見慣れた、というよりも目的の彼女が静かに佇む。
彼女から見れば右側になるその座席に、俺は素知らぬ顔で前列を確保。
油断すると、30代半ばのサラリーマンに横取りされかけるので、最近はバス停でも一番前を陣取るよう努めている。
そんな俺の小さな計画など知りもしない彼女は、艶やかな光を放つ髪の隙間からイヤホンを装着し音楽を聞いている。
同じクラスというだけで接点はない。ましてや社交的ではない互いの性格上、話すタイミングさえ訪れない。
気になる子の前に平然とした顔で座るのが、俺の精一杯のアピール。
自分でもこんなにも小心者だったのかと驚かされる。そして呆れて笑いさえ込み上げてくる。