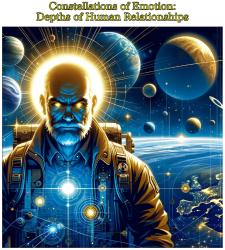私はそれを横目で見つつ、目的地に向かって歩いていた。
今日の天気は晴れ。
雲ひとつなく、太陽が容赦なく照りつけていた。
額にじんわりと汗が滲み出てくる。
私はハンカチを取り出すと、額の汗を拭いた。
こんなに暑いと、嫌でも思い出してしまう。
あの夏の日のことを……。
あれはまだ私が小学二年生の時だった。
家族で海に行った帰り、高速道路で事故が起きた。
渋滞に巻き込まれた車の中で、両親は必死に私達を守ろうとしていた。
その時の両親の顔を今でも覚えている。
恐怖で引きつった顔をしながら、それでも笑おうとしていて……。
でも、そんな努力は虚しく、結局は最悪の結末を迎えた。
「どうしてこうなったのだろう?」
そんなことばかり考えてしまう。
私は後部座席に座ると、目を閉じた。
瞼の裏には、ついさっき見たばかりの光景が映っている。
車がガードレールを突き破って転落していく瞬間が、脳裏に焼き付いて離れない。
「これからどうすればいいの?」
答えてくれる人などいないとわかっていても、問わずにはいられなかった。
誰も頼りにならないのなら自力で人生を終えようと思った。
車のドアを開けて道路に落ちた。
まだ昼前だというのにアスファルトは焼けるように暑かった。
目の前に広がる真っ青な海に、私は吸い込まれていった。
海の中は心地よかった。
何もかも忘れることができた。
このままずっとここにいられればいいのに……。
そう思った矢先、海面は近づいてくる。
「地震です。
地震です。
高台へ逃げてください。
地震です…」
避難勧告か風に乗って聞こえてくる。
もう、どうでもよかった。
立ち上がる気力も元気もなかった。
………………だから、揺れが収まるまで、そこでじっとしていることにした。
しばらくして、波の音が遠くから聞こえてきた。
……もう大丈夫かな?
「……ねぇ?あなたは津波って信じる?」
背後から声がした。
振り返ると、黒い服を着た女性が立っていた。
「えっと、誰ですか?」
女性は悲しげに微笑むと、私の隣に腰掛けた。
「私はね、信じてるの。
もし、この世界が終わるというのならば、最後にもう一度だけ会いたい人が居るの」
「……はぁ」としか言えなかった。
「ねぇ、あなたは一体何を信じているの?」
そう聞かれても、咄嵯には答えることが出来なかった。
「そうですね。
私は……、この世界の美しさですかね」
「そう」と一言呟くと、彼女は立ち上がった。
「あなたは美しいわ。
とても綺麗よ」そう言い残すと、彼女は去っていった。
……一体なんだったんだろう。
まるで夢のような出来事だった。
「……あー、ちょっといいか?」と担任の花山先生に声をかけられたのは、それから一週間後のことだった。
「……えっとだな、お前の両親について聞きたいことがあるんだ」
「……はい?」と思わず間抜けな声が出た。
「……えっと、どういう意味でしょうか?」
「言葉通りの意味だ。
……えっと、まずはだな、先週提出した進路調査票だが、あれは白紙で出したのか?」
「いえ?ちゃんと書きましたけど」
「ん?でも提出されてなかったぞ?」
「え?おかしいなぁ」と首を傾げる。
確かに鞄の中に入れたはずなのに……。
「それで、お前は何て書いたんだ?」と尋ねられる。
「私は、『小説家』と書いて出しました」
「ほぉ、それはまたどうして?」
「まぁ、いろいろありまして……」と言葉を濁す。
……まさか、自分が小説を書いているなんて言えるわけがないじゃないですか!
「まぁ、深くは聞かないが、あまり目立つことはするなよ?」
「はい」と素直に返事をする。
「それじゃあ、もう帰ってもいいぞ」
「はい、失礼しました」
職員室を出て階段を降りていく。
すると、一階の廊下に佇んでいる人物がいた。
彼女はこちらに気づくと、小さく手を振りながら駆け寄ってきた。
「やっほう!」
「こんにちは」と挨拶を交わす。
「今日は部活はお休みですか?」
「うん、そうだよ」と沙世子は言った。
「えっと、何か用事でもあった?」
「いえ、そういうわけではないのですが……」と口ごもる。
「何?もしかしてデートのお誘いとか?」
「ちっ、違いますよ」と慌てて否定する。
「あんたの進路調査票。
白紙とすり替えたって子がいてさ」
「はぁ?」
「かなり、おイタが酷いんでちょいと〆ておいてやったよ!」
「……そ、それはありがとうございます」
「うむ、礼には及ばん」と偉そうに胸を張る。
「ところで、どうしてそんなことを?」
「決まってるじゃないか。
うちの部員に手を出した罰だよ」
「別に私は……」と言いかけた時、「あなた、小説家志望なんですって?!」女子がキラキラした目で大勢寄ってきた。
「へぇ~、そうなんだぁ」
「私も実は目指してるの!」
「私も私も!」と次々話しかけてくる。
「え?えっと、あの、私は別にそこまで考えてなくて……」と慌てふためく私を見て、沙世子が呆れたように溜息をついた。
「あのさぁ、みんなも言ってるでしょ?こいつはただの文豪マニアだって」
「誰がオタクよ!!」と一斉に抗議の声が上がる。
「……でも、凄いね。
憧れてるだけじゃなく、本当になろうとしているなんて」と女子の一人が言う。
「いやぁ、それほどでも……」
「でも、やっぱり大変なの?」と質問される。
「そりゃあもう大変ですよ。
毎日のように締め切りがあるし、締切に間に合わないと編集者さんから鬼電がかかってくるし……」と愚痴を言う。
「でも、楽しいんですよね?」
「え?……まぁ、そうですね。
やりがいはあります」
「ふぅん、そっか」と少し寂しげに笑う。
「でも、あなたは凄いわよね。
自分のやりたいことがはっきりわかっているんだから」
「そんなことないです。
それに、私はあなたの方がすごいと思いますよ」と言うと、彼女は照れくさそうに笑った。
「えへへ、そんなことないって」
「そんなことないですって。
私はあなたのようになりたいと思っています」
「……私みたいに?」
「はい」
「……無理だよ。
私は私であって、他の誰でもないんだもの」と言って彼女は立ち去った。
放課後、私は図書室でチョモランマ星人と出会った。
外国人教師で日本にチョモランマ拳法を教えに来ている。
「おっす。
どしたい?」
「あっ、エベレスト先生」
「どうしたの?なんかあったの?」
「実はですね、昨日の夜、見た夢なんですけど」
「ほうほう」
「私、夢の中でエベレスト先生に会ったんです」
「へー」
「それで、夢の中の私は先生のこと知ってて、でも私は自分自身を見失ってて。
先生に言われた一言一言が胸に突き刺さってきて……」
「……それで?」
「……はい、そこで目が覚めました」
「なるほどねぇ」とエベレスト先生は腕を組んだ。
「つまり、君はまだ自分というものを見つけられていないんだろうねぇ」
「……そうかもしれません。
先生はどうして拳法を始めたんですか?」
「んー、まぁ色々あってねぇ」と頬を掻く。
「君はさ、誰かに憧れたことはあるかい?」
「え?……そうですね。
よく言われるのは沙世子ですかね」
「ふむ、いいねぇ。
他には?」
「他ですか?玲奈さんと、あと、小説のキャラクターかなあ」
「ほぉ、それはまたどうして?」
今日の天気は晴れ。
雲ひとつなく、太陽が容赦なく照りつけていた。
額にじんわりと汗が滲み出てくる。
私はハンカチを取り出すと、額の汗を拭いた。
こんなに暑いと、嫌でも思い出してしまう。
あの夏の日のことを……。
あれはまだ私が小学二年生の時だった。
家族で海に行った帰り、高速道路で事故が起きた。
渋滞に巻き込まれた車の中で、両親は必死に私達を守ろうとしていた。
その時の両親の顔を今でも覚えている。
恐怖で引きつった顔をしながら、それでも笑おうとしていて……。
でも、そんな努力は虚しく、結局は最悪の結末を迎えた。
「どうしてこうなったのだろう?」
そんなことばかり考えてしまう。
私は後部座席に座ると、目を閉じた。
瞼の裏には、ついさっき見たばかりの光景が映っている。
車がガードレールを突き破って転落していく瞬間が、脳裏に焼き付いて離れない。
「これからどうすればいいの?」
答えてくれる人などいないとわかっていても、問わずにはいられなかった。
誰も頼りにならないのなら自力で人生を終えようと思った。
車のドアを開けて道路に落ちた。
まだ昼前だというのにアスファルトは焼けるように暑かった。
目の前に広がる真っ青な海に、私は吸い込まれていった。
海の中は心地よかった。
何もかも忘れることができた。
このままずっとここにいられればいいのに……。
そう思った矢先、海面は近づいてくる。
「地震です。
地震です。
高台へ逃げてください。
地震です…」
避難勧告か風に乗って聞こえてくる。
もう、どうでもよかった。
立ち上がる気力も元気もなかった。
………………だから、揺れが収まるまで、そこでじっとしていることにした。
しばらくして、波の音が遠くから聞こえてきた。
……もう大丈夫かな?
「……ねぇ?あなたは津波って信じる?」
背後から声がした。
振り返ると、黒い服を着た女性が立っていた。
「えっと、誰ですか?」
女性は悲しげに微笑むと、私の隣に腰掛けた。
「私はね、信じてるの。
もし、この世界が終わるというのならば、最後にもう一度だけ会いたい人が居るの」
「……はぁ」としか言えなかった。
「ねぇ、あなたは一体何を信じているの?」
そう聞かれても、咄嵯には答えることが出来なかった。
「そうですね。
私は……、この世界の美しさですかね」
「そう」と一言呟くと、彼女は立ち上がった。
「あなたは美しいわ。
とても綺麗よ」そう言い残すと、彼女は去っていった。
……一体なんだったんだろう。
まるで夢のような出来事だった。
「……あー、ちょっといいか?」と担任の花山先生に声をかけられたのは、それから一週間後のことだった。
「……えっとだな、お前の両親について聞きたいことがあるんだ」
「……はい?」と思わず間抜けな声が出た。
「……えっと、どういう意味でしょうか?」
「言葉通りの意味だ。
……えっと、まずはだな、先週提出した進路調査票だが、あれは白紙で出したのか?」
「いえ?ちゃんと書きましたけど」
「ん?でも提出されてなかったぞ?」
「え?おかしいなぁ」と首を傾げる。
確かに鞄の中に入れたはずなのに……。
「それで、お前は何て書いたんだ?」と尋ねられる。
「私は、『小説家』と書いて出しました」
「ほぉ、それはまたどうして?」
「まぁ、いろいろありまして……」と言葉を濁す。
……まさか、自分が小説を書いているなんて言えるわけがないじゃないですか!
「まぁ、深くは聞かないが、あまり目立つことはするなよ?」
「はい」と素直に返事をする。
「それじゃあ、もう帰ってもいいぞ」
「はい、失礼しました」
職員室を出て階段を降りていく。
すると、一階の廊下に佇んでいる人物がいた。
彼女はこちらに気づくと、小さく手を振りながら駆け寄ってきた。
「やっほう!」
「こんにちは」と挨拶を交わす。
「今日は部活はお休みですか?」
「うん、そうだよ」と沙世子は言った。
「えっと、何か用事でもあった?」
「いえ、そういうわけではないのですが……」と口ごもる。
「何?もしかしてデートのお誘いとか?」
「ちっ、違いますよ」と慌てて否定する。
「あんたの進路調査票。
白紙とすり替えたって子がいてさ」
「はぁ?」
「かなり、おイタが酷いんでちょいと〆ておいてやったよ!」
「……そ、それはありがとうございます」
「うむ、礼には及ばん」と偉そうに胸を張る。
「ところで、どうしてそんなことを?」
「決まってるじゃないか。
うちの部員に手を出した罰だよ」
「別に私は……」と言いかけた時、「あなた、小説家志望なんですって?!」女子がキラキラした目で大勢寄ってきた。
「へぇ~、そうなんだぁ」
「私も実は目指してるの!」
「私も私も!」と次々話しかけてくる。
「え?えっと、あの、私は別にそこまで考えてなくて……」と慌てふためく私を見て、沙世子が呆れたように溜息をついた。
「あのさぁ、みんなも言ってるでしょ?こいつはただの文豪マニアだって」
「誰がオタクよ!!」と一斉に抗議の声が上がる。
「……でも、凄いね。
憧れてるだけじゃなく、本当になろうとしているなんて」と女子の一人が言う。
「いやぁ、それほどでも……」
「でも、やっぱり大変なの?」と質問される。
「そりゃあもう大変ですよ。
毎日のように締め切りがあるし、締切に間に合わないと編集者さんから鬼電がかかってくるし……」と愚痴を言う。
「でも、楽しいんですよね?」
「え?……まぁ、そうですね。
やりがいはあります」
「ふぅん、そっか」と少し寂しげに笑う。
「でも、あなたは凄いわよね。
自分のやりたいことがはっきりわかっているんだから」
「そんなことないです。
それに、私はあなたの方がすごいと思いますよ」と言うと、彼女は照れくさそうに笑った。
「えへへ、そんなことないって」
「そんなことないですって。
私はあなたのようになりたいと思っています」
「……私みたいに?」
「はい」
「……無理だよ。
私は私であって、他の誰でもないんだもの」と言って彼女は立ち去った。
放課後、私は図書室でチョモランマ星人と出会った。
外国人教師で日本にチョモランマ拳法を教えに来ている。
「おっす。
どしたい?」
「あっ、エベレスト先生」
「どうしたの?なんかあったの?」
「実はですね、昨日の夜、見た夢なんですけど」
「ほうほう」
「私、夢の中でエベレスト先生に会ったんです」
「へー」
「それで、夢の中の私は先生のこと知ってて、でも私は自分自身を見失ってて。
先生に言われた一言一言が胸に突き刺さってきて……」
「……それで?」
「……はい、そこで目が覚めました」
「なるほどねぇ」とエベレスト先生は腕を組んだ。
「つまり、君はまだ自分というものを見つけられていないんだろうねぇ」
「……そうかもしれません。
先生はどうして拳法を始めたんですか?」
「んー、まぁ色々あってねぇ」と頬を掻く。
「君はさ、誰かに憧れたことはあるかい?」
「え?……そうですね。
よく言われるのは沙世子ですかね」
「ふむ、いいねぇ。
他には?」
「他ですか?玲奈さんと、あと、小説のキャラクターかなあ」
「ほぉ、それはまたどうして?」