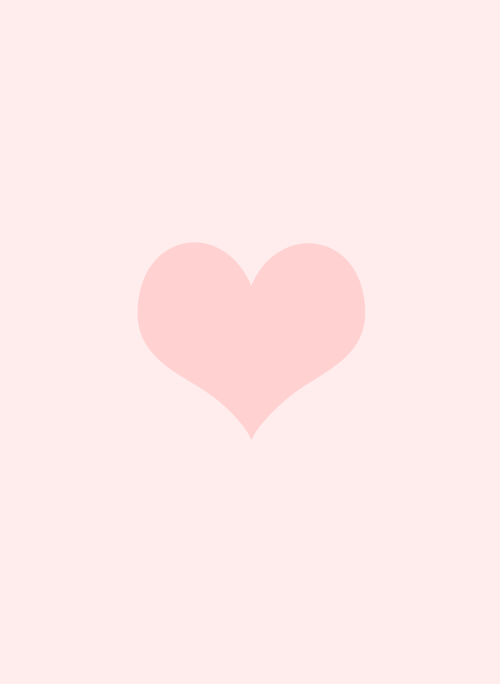海花side
「好きです___」
そんなの、言われるはずがないのに。
1人で舞い上がって、本当にバカみたい。
さっきまで、流くんに告白される夢を見ていただなんて、口が裂けても誰にも言えない。
流くんのこと、考えすぎちゃってたのかな……?
そんなの、私が流くんを好きすぎておかしい人みたいじゃん。
少し赤くなった頬を手で仰ぎながら、ゆっくりとベッドから立ち上がる。
「刈谷さん、体調はどう?」
「だいぶマシになりました。ありがとうございました」
養護教諭の先生に軽く頭を下げると、私は保健室を出た。
どうやら、私はぐっすりと寝ていたらしく、起きた時にはもう六限が終わり、部活のない生徒は下校の時間となっていたのだ。
……勉強、やりすぎたかも。
ちょっとだけ気をつけよう、軽くため息をついて玄関へ向かおうとすると___。
「先輩」
背後から、聞きたくて聞きたくてたまらなかった彼の声。
……いや、そんなわけないか。
大体、突き放したのは私だし。私があんなにあからさまに言ったから……。
立ち止まったまま、振り返るか悩んでいると、今度ははっきりと声が聞こえた。
「海花先輩」
ゆっくりと振り返る。
ずっと見ていなかった彼の姿。
相変わらず無愛想な表情だけど、実は優しくて。
背が高くて、派手で。
___私が好きになっちゃった人。
「……流くん……」
ポロリと彼の名前を口にすると、流くんは安心したように微笑んだ。
その表情は、今まで見てきたどの彼よりも優しい表情で。
「家まで送ります」
そして、いつもと変わらない優しさだった。
________________________
「……」
「……」
歩き始めて、数分。
学校を出てから、破られることのない沈黙が二人の間に続いていた。
私の隣を歩く流くんをチラリと隠し見る。
なぜかいつも車道側を歩いていて、私に歩幅を合わせてくれていて。
全部私に対する気遣いをしてくれたのかな、ってそう思うだけでも、なんだか胸が苦しくなる。
流くんに対する好きって気持ち、諦めようと思ってたのにな。
そんな私の頭に浮かぶ岩木桃香ちゃんの姿。
流くんのことを好きな女の子なんて、きっと100人くらいいるだろう。
それがなんだかとても辛くて、悲しくて。
流くんの笑顔とか、匂いとか、優しい声とか。そういうの、全部私だけが知っていればいいのに、なんて子供じみたことまで思ってしまう自分も嫌になってくる。
冷たくなった手に息を吹きかける。
……寒いな。
流くんと話してるときは、全然寒くなくて、むしろ寒いなんて忘れてるくらいなのに。
今日は違う。
うつむきながら歩いている途中、ふわりと首元に温かいものが触れると同時に、流くんの香りが私を包み込んだ。
「え……」
すぐ隣を見ると、流くんがさっきまで巻いていたはずのマフラーがなくて。
その代わり、それが私の首にゆるく巻きつけられていた。
「……冷えるとよくないから」
さっきまで流くんの首につけられていたマフラー。
まだ、流くんの体温が残ってる。
まるで流くんに抱きしめられているみたいな感覚がして、瞬く間に顔が赤く染まっていく。
こんなの、好きなのやめられるわけないじゃん……。
「体調、もう大丈夫ですか」
ほら、そうやって優しくしてくれるから。
「俺の勉強に付き合ってくれてたからですよね」
「ち、ちが___」
「クマ、ずっとできてた」
私のこと、見ていないようでしっかりと見ている流くんの目が、しっかりと私を捉える。
ずっとわかってた。
流くんが、私のことを心配して「今週は放課後なしにして休んでほしい」と言ったことも。
___でも、それを突き放してるって捉えちゃった私が流くんを逆に突き放して、わざと距離を置いたことも。
全部、流くんのことが好きだから、私が面倒くさくなっちゃったってことも。
「……好き」
不意に、口からこぼれ出た二文字の言葉。
それは、消え入りそうなくらい小さくて、弱くて、すぐに暗闇に溶けて。
たった二文字の言葉なのに、なぜか我慢できなかった。
どうしても伝えたかった。
___それなのに。
「え……」
「こっ、後輩!後輩として、流くんのこと好きだよって話!」
あぁ、もう。
なんでこんなしょうもない嘘、ついちゃうの。から元気で出した明るい声は、静かな住宅街に反響する。
「……俺は先輩として見てない」
「っ……え……?」
流くんが立ち止まると同時に、サラサラな金髪が揺れて、流くんの目にかかる。
その奥の瞳は、暗くてよく見えない。
「友達だとも思ってない」
今まで聞いたことがないくらい、真剣な声。
「や、やだな……。なに、急に?悲しいじゃん、やめてよ」
どんどんと近づいてくる距離に思わず、流くんの胸板を押し返した。
……もしかして私、本当に先輩以下の存在……?
流くんにとって私、人間じゃないんじゃ……?
「海花先輩、俺ってただの後輩ですか」
流くんの胸板を押していた私の手を、するりと彼の細くて長い指に絡め取られる。
ドキドキと、うるさいくらいに心臓が鳴っていて、何も考えられない。
「好きって、本当に後輩として?」
___そんなわけない。
今すぐにでも、この手を握り返して……甘えたい。
流くんの優しく声も、笑顔も、全部全部独り占めしちゃいたい。
「ほんとは……っ、流くんのこと___」
そこまで言った時だった。
「海花!」
まるで止まった世界が動き出したかのように、外部から私の声を呼ぶ声が聞こえたのは。