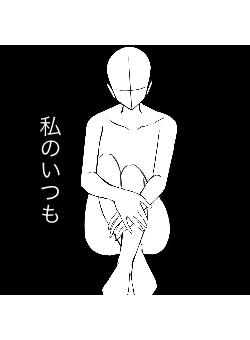最近、彼は私に気があるのではないかと思うことがある。
そうだったらいいな、なんて、淡い期待を持っている。
「しーほちゃん!一緒に帰ろーぜー」
「うん」
このごろ、毎日のように光輝くんと帰っている。
人気者の彼なら一緒に帰る友だちなんでいくらでもいるだろうに
それも私が期待を抱く理由の一つだ。
「あー、やっぱり、しほちゃんと話してる時が1番落ち着くなあ」
「あ、ありがと」
彼はずるい。
「あ!私、教室に教科書忘れてきた!取りに行くので帰っていてください。」
「え、でも、そんくらい待ってるよ、それか一緒に行こ?」
「いや、そんな悪いです。さようなら!」
無理やり話を終わらせて、学校へ走った。
「はあはあ、着いた」
自分の教室に向かう。
ドアを開けようとしたその時、中から話し声が聞こえた。
「ねえ、最近、清水さん、光輝と距離近くね?」
「え、それな、なんかうざ」
「ね!光輝も絶対嫌がってるよ」
「どうせ、清水さんが一方的に光輝を追っかけてるだけでしょ?」
「光輝かわいそー」
「そもそも釣り合ってないわ」
「それなw身の程わきまえろ」
私は静かに学校を出た。
もう空は日が落ちて薄暗くなっていた。
帰り道をとぼとぼ一人で帰る。
自然と涙が込み上げてきた。
止めようと思って天を仰ぐ。
それでも、溢れてきて、私は声を殺しながら泣いた。
だって、そうだ。
明るくて、おもしろくて、かっこよくて、クラスの人気者な光輝くんがこんな暗くて地味で陰キャな私のことを好きなんて世界線、おこがましい。
彼が私のことを好きかもだなんて考えが自意識過剰すぎて、急にはげしい羞恥心が襲ってくる。
もう私の感情はぐちゃぐちゃだった。
そうだったらいいな、なんて、淡い期待を持っている。
「しーほちゃん!一緒に帰ろーぜー」
「うん」
このごろ、毎日のように光輝くんと帰っている。
人気者の彼なら一緒に帰る友だちなんでいくらでもいるだろうに
それも私が期待を抱く理由の一つだ。
「あー、やっぱり、しほちゃんと話してる時が1番落ち着くなあ」
「あ、ありがと」
彼はずるい。
「あ!私、教室に教科書忘れてきた!取りに行くので帰っていてください。」
「え、でも、そんくらい待ってるよ、それか一緒に行こ?」
「いや、そんな悪いです。さようなら!」
無理やり話を終わらせて、学校へ走った。
「はあはあ、着いた」
自分の教室に向かう。
ドアを開けようとしたその時、中から話し声が聞こえた。
「ねえ、最近、清水さん、光輝と距離近くね?」
「え、それな、なんかうざ」
「ね!光輝も絶対嫌がってるよ」
「どうせ、清水さんが一方的に光輝を追っかけてるだけでしょ?」
「光輝かわいそー」
「そもそも釣り合ってないわ」
「それなw身の程わきまえろ」
私は静かに学校を出た。
もう空は日が落ちて薄暗くなっていた。
帰り道をとぼとぼ一人で帰る。
自然と涙が込み上げてきた。
止めようと思って天を仰ぐ。
それでも、溢れてきて、私は声を殺しながら泣いた。
だって、そうだ。
明るくて、おもしろくて、かっこよくて、クラスの人気者な光輝くんがこんな暗くて地味で陰キャな私のことを好きなんて世界線、おこがましい。
彼が私のことを好きかもだなんて考えが自意識過剰すぎて、急にはげしい羞恥心が襲ってくる。
もう私の感情はぐちゃぐちゃだった。