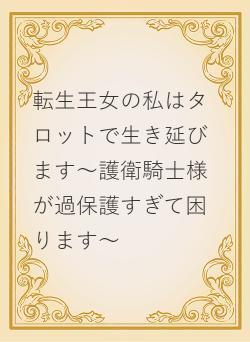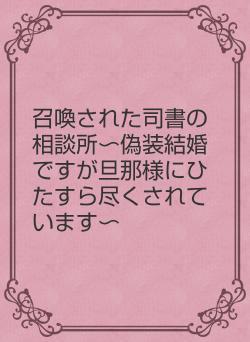それから首都に戻れたのは三週間後。
もっと早く帰路につけるはずだったのに、そうならなかったのは、偏にシオドーラの護送に揉めた……は揉めたが、最大の原因はその方法だった。
「あいつが近くにいると、八つ裂きにしそうだ」
そう、シオドーラはガーラナウム城に収監されていたわけではない。城外にある、なんと自警団の牢屋に入れられていたのだ。
アリスター様がこっそりやり兼ねない、という理由で。だから護送もまた、同様のことだった。
そんな物騒なことを口ずさむアリスター様を、私はソファーに座りながら、その横顔を見た。
「お願いですから、止めてください。聖女殺しという悪評まで立てられたらどうするんですか」
「偏屈にもう一つ、付くだけだ」
「屁理屈を捏ねないでください。旦那様の話題が上がる度に、シオドーラもワンセットで付くのは嫌ですからね」
最終手段、とばかりに拗ねてみると、「それもそうだな」と素直になるのだから、さらに嫌になる。
「しかし、メイベルの近くにあいつを置くのはまた違う話だ」
「では、転移魔法陣で一気に首都まで行きましょう。お金はかかりますが、罪人の護送と言えばなんとかなるでしょう」
クリフに頼む前に、そのような名目でシオドーラを聖女から罪人という立場にすれば、皇后様の耳にも届くだろう。もしくは皇帝から皇后様に。
それでも、二、三日はかかるだろうけれど。
「……背に腹は代えられんな」
「そんなにお嫌ですか? シオドーラを首都に連れて行くのが」
「そこまで譲歩する必要があると思ってな」
「言いたいことは分かりますが……そもそもシオドーラがあそこまで追い込まれてしまった原因は、私にあるので……」
たとえ不可抗力であっても……。
しかしアリスター様は納得できなかったようだ。
「間違ってはいないが、自分の中で解決するのが聖女、いや大人ってもんだろう。それに俺の方が迷惑をかけられた挙げ句、追い込まれたんだぞ。メイベルが気にかける必要はない」
「追い込まれるって、そんなにシオドーラと結婚しろと周りに言われていたんですか?」
私もあまり話題に出したくないから言わなかったけれど、シオドーラが勘違いするほどだ。気にならないわけではなかった。
「……俺は一人っ子だからな。二十六、という年齢も相まって、周りが要らぬ世話を焼くんだ。その中の一つにシオドーラがいたというだけだ」
「えっ、でも、あの時は『なりたい連中は山程いる』って言っていませんでした?」
「……憶えていたのか」
まるで、重要なことは憶えていないくせに、どうでもいいことは憶えているんだな、と言われているような気がした。
一応、契約結婚の話なのだから、憶えていて当然だと思うんだけど……。しかも、まだ一年は経っていない。忘れたくても忘れられるだろうか、と思えるほどの出来事だったのに。
「旦那様からしたら十三年振りの再会ですが、私にとっては初めて会ったのと同じなんですよ。忘れてもよろしいんですか?」
「だがアレは……」
「ご自分でも悪いことをしたと思っています?」
「いや、こうして念願だったメイベルを手に入れたんだ。悔いはないさ」
これは屁理屈? それとも自慢? いや、自慢げにいうことじゃない気がするけれど。
思わず反応に困ってしまった。だけど、何故か顔が熱い。
「加えていうと、うるさく言ってきた奴らの念願も、そろそろ出来でもいい頃合いだと思うんだがな」
「念願?」
「そういうところは察しが悪いのはワザとか? 跡継ぎのことだよ」
「跡継ぎ……っ!」
アリスター様にお腹を指差され、私は咄嗟に手で隠すような仕草をした。途端、ソファーに押し倒される。
「まだなら今からでも……」
「だ、ダメです! 明るい内からは嫌だって――……」
言ったじゃないですか、という言葉は、アリスター様に口で塞がれてしまい言えなかった。
「ならば寝室に行こう。あそこは天蓋カーテンがあるから明るくないぞ」
「はぁはぁ……。揚げ足、いえ屁理屈を捏ねないでください。私が言った『明るい』はそういう意味じゃないことくらい、知っているではないですか!」
「関係ない。シオドーラの件で譲歩したんだ。今回はこっちにも譲歩してもらうぞ」
「えっ、ちょっと!」
すでに私の拒否権などなかったのだ。横抱きにされたと思ったら、宣言通り寝室へ。しかもちゃんと天蓋カーテンを閉められたものだから、私に逃げ場などなかった。
もっと早く帰路につけるはずだったのに、そうならなかったのは、偏にシオドーラの護送に揉めた……は揉めたが、最大の原因はその方法だった。
「あいつが近くにいると、八つ裂きにしそうだ」
そう、シオドーラはガーラナウム城に収監されていたわけではない。城外にある、なんと自警団の牢屋に入れられていたのだ。
アリスター様がこっそりやり兼ねない、という理由で。だから護送もまた、同様のことだった。
そんな物騒なことを口ずさむアリスター様を、私はソファーに座りながら、その横顔を見た。
「お願いですから、止めてください。聖女殺しという悪評まで立てられたらどうするんですか」
「偏屈にもう一つ、付くだけだ」
「屁理屈を捏ねないでください。旦那様の話題が上がる度に、シオドーラもワンセットで付くのは嫌ですからね」
最終手段、とばかりに拗ねてみると、「それもそうだな」と素直になるのだから、さらに嫌になる。
「しかし、メイベルの近くにあいつを置くのはまた違う話だ」
「では、転移魔法陣で一気に首都まで行きましょう。お金はかかりますが、罪人の護送と言えばなんとかなるでしょう」
クリフに頼む前に、そのような名目でシオドーラを聖女から罪人という立場にすれば、皇后様の耳にも届くだろう。もしくは皇帝から皇后様に。
それでも、二、三日はかかるだろうけれど。
「……背に腹は代えられんな」
「そんなにお嫌ですか? シオドーラを首都に連れて行くのが」
「そこまで譲歩する必要があると思ってな」
「言いたいことは分かりますが……そもそもシオドーラがあそこまで追い込まれてしまった原因は、私にあるので……」
たとえ不可抗力であっても……。
しかしアリスター様は納得できなかったようだ。
「間違ってはいないが、自分の中で解決するのが聖女、いや大人ってもんだろう。それに俺の方が迷惑をかけられた挙げ句、追い込まれたんだぞ。メイベルが気にかける必要はない」
「追い込まれるって、そんなにシオドーラと結婚しろと周りに言われていたんですか?」
私もあまり話題に出したくないから言わなかったけれど、シオドーラが勘違いするほどだ。気にならないわけではなかった。
「……俺は一人っ子だからな。二十六、という年齢も相まって、周りが要らぬ世話を焼くんだ。その中の一つにシオドーラがいたというだけだ」
「えっ、でも、あの時は『なりたい連中は山程いる』って言っていませんでした?」
「……憶えていたのか」
まるで、重要なことは憶えていないくせに、どうでもいいことは憶えているんだな、と言われているような気がした。
一応、契約結婚の話なのだから、憶えていて当然だと思うんだけど……。しかも、まだ一年は経っていない。忘れたくても忘れられるだろうか、と思えるほどの出来事だったのに。
「旦那様からしたら十三年振りの再会ですが、私にとっては初めて会ったのと同じなんですよ。忘れてもよろしいんですか?」
「だがアレは……」
「ご自分でも悪いことをしたと思っています?」
「いや、こうして念願だったメイベルを手に入れたんだ。悔いはないさ」
これは屁理屈? それとも自慢? いや、自慢げにいうことじゃない気がするけれど。
思わず反応に困ってしまった。だけど、何故か顔が熱い。
「加えていうと、うるさく言ってきた奴らの念願も、そろそろ出来でもいい頃合いだと思うんだがな」
「念願?」
「そういうところは察しが悪いのはワザとか? 跡継ぎのことだよ」
「跡継ぎ……っ!」
アリスター様にお腹を指差され、私は咄嗟に手で隠すような仕草をした。途端、ソファーに押し倒される。
「まだなら今からでも……」
「だ、ダメです! 明るい内からは嫌だって――……」
言ったじゃないですか、という言葉は、アリスター様に口で塞がれてしまい言えなかった。
「ならば寝室に行こう。あそこは天蓋カーテンがあるから明るくないぞ」
「はぁはぁ……。揚げ足、いえ屁理屈を捏ねないでください。私が言った『明るい』はそういう意味じゃないことくらい、知っているではないですか!」
「関係ない。シオドーラの件で譲歩したんだ。今回はこっちにも譲歩してもらうぞ」
「えっ、ちょっと!」
すでに私の拒否権などなかったのだ。横抱きにされたと思ったら、宣言通り寝室へ。しかもちゃんと天蓋カーテンを閉められたものだから、私に逃げ場などなかった。