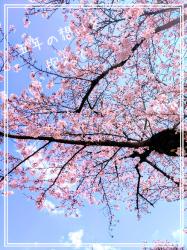画面に表示された俺の過去の作品を神田さんは丁寧に一つずつ見ていった。
すべて見終わるまでの約10分間、俺は真剣な顔で画面を見つめる神田さんを眺めていた。
「うちに所属する気ない?」
「俺、まだ中学生ですけど…」
「知ってるよ。でも俺は所属してもらうだけの技術と才能があると思う。無理強いはしないけど、よかったら。親御さんとかと相談して、所属する気になったら連絡して。これ、俺の名刺」
「ありがとうございます」
すべて見終わるまでの約10分間、俺は真剣な顔で画面を見つめる神田さんを眺めていた。
「うちに所属する気ない?」
「俺、まだ中学生ですけど…」
「知ってるよ。でも俺は所属してもらうだけの技術と才能があると思う。無理強いはしないけど、よかったら。親御さんとかと相談して、所属する気になったら連絡して。これ、俺の名刺」
「ありがとうございます」