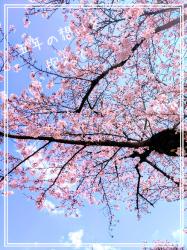だが、ようやく近づいた夢を目の前に諦めるわけにはいかなかった。
再び理玖のところに戻った時、理玖はなぜか呆然としていた。
私たち以外に誰もいない応接室で1人座っている。
「どした?なんかあったの?」
「あ、いや。行こっか」
立ち上がる理玖をよそに私は報告した。
「というか、ねえ、私所属してほしいって言われた!次回契約!!すごくない?!」
「契約…」
理玖がようやく目を見開いて私を見た。
再び理玖のところに戻った時、理玖はなぜか呆然としていた。
私たち以外に誰もいない応接室で1人座っている。
「どした?なんかあったの?」
「あ、いや。行こっか」
立ち上がる理玖をよそに私は報告した。
「というか、ねえ、私所属してほしいって言われた!次回契約!!すごくない?!」
「契約…」
理玖がようやく目を見開いて私を見た。