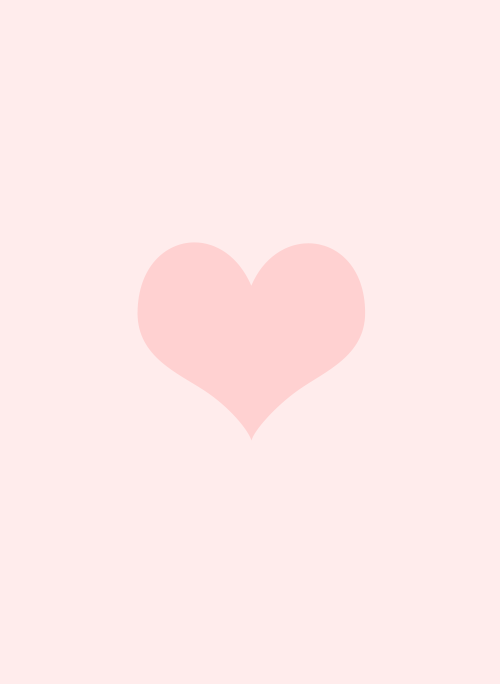「ウィロウ地方はここと比べたら田舎だから、若い女性が好きそうなおしゃれなお店なんてないし、娯楽になるような場所自体ない。それなのに、いつもヴァイオレットは文句の一つも言わないし、ほしいものだって一度も言ったことがない」
「私は、おしゃれなお店よりも本さえあればいいんです。田舎だとか、都会だとか、考えたこともありません。……穏やかな気持ちで毎日を過ごしたい。ただそれだけです」
ヴァイオレットは屋敷での毎日を思い浮かべる。おいしいお茶を用意してくれるアイリス、掃除や料理が得意なリオン、魔法家系だというのに非魔法家系の自分たちに優しく接してくれるイヴァン。自分から望んでウィロウ地方に来たわけではない。しかしーーー。
「私は、あの穏やかで温かい屋敷が、自然豊かなウィロウ地方が、大好きです。欲を言うならば、ランカスター家のお屋敷でずっと共に働いてきたミモザがいたらと思いますが」
ヴァイオレットがそう言うと、イヴァンの頰が赤く染まっていく。そして、彼の顔に笑みが戻った。
「ヴァイオレット、そう言ってくれて嬉しいよ。だからお礼をさせてほしい」
「私は、おしゃれなお店よりも本さえあればいいんです。田舎だとか、都会だとか、考えたこともありません。……穏やかな気持ちで毎日を過ごしたい。ただそれだけです」
ヴァイオレットは屋敷での毎日を思い浮かべる。おいしいお茶を用意してくれるアイリス、掃除や料理が得意なリオン、魔法家系だというのに非魔法家系の自分たちに優しく接してくれるイヴァン。自分から望んでウィロウ地方に来たわけではない。しかしーーー。
「私は、あの穏やかで温かい屋敷が、自然豊かなウィロウ地方が、大好きです。欲を言うならば、ランカスター家のお屋敷でずっと共に働いてきたミモザがいたらと思いますが」
ヴァイオレットがそう言うと、イヴァンの頰が赤く染まっていく。そして、彼の顔に笑みが戻った。
「ヴァイオレット、そう言ってくれて嬉しいよ。だからお礼をさせてほしい」