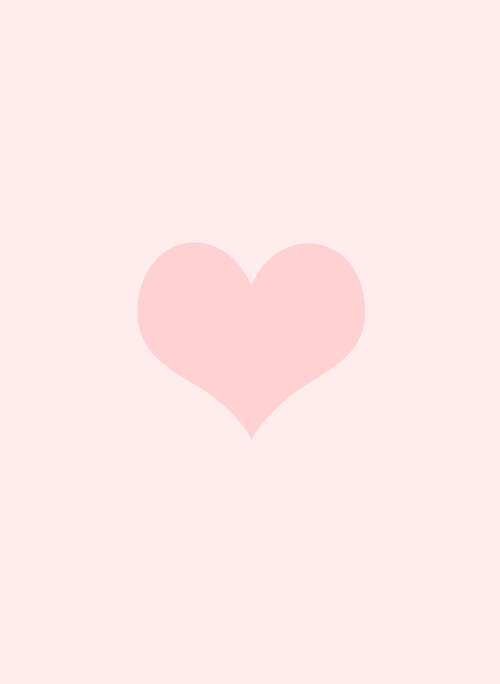父親は店の奥へ行った。靴を脱ぎ、あがった。まことも続いた。
父親は階段を上った。二階に部屋があるのだ。まことも続いた。まことはうきうきしていた。
二階。廊下が続いている。右側にドアがあり、突き当りにドアがある。
父親が歩いて行く。右側のドアを通り過ぎる。
「え、おやじ、おやじの部屋にあるんじゃねえの」
父親はだまっている。
「お、おい、そっちは私の部屋だぜ」
「・・・・・・」
「お、おい、私の部屋に入ったんじゃあるめえ」
父親は、ドアのドアノブに触った。
「おい!」
と、まことは大声をあげた。
「こらこら、年頃の娘の部屋にはいんじゃねえ」
父親が振り向いていった。
「ほほお、そうか」
「え」
「おぬしもそろそろ年頃か」
「え」
「まあ、年頃の男はそういう本を隠してたりするからなあ」
「て、てめえ、やっぱり男扱いか。そういう本てどういう本だよ」
「なんていうかあ、女性の写真とか」
「ああ、なんだよそれ」
まことは父親につきをいれた。父親は軽くよける。
「さては図星じゃな」
「て、てめええええええ」
「お前も色気づいたのう」
まことはつきをいれつづける。
「制服着たくないのか」
まことはつきをやめた。
「そうそう。憧れのセーラー服」
父親は微笑んだ。
「じゃあ、見せてやろう」
といって父親はドアノブに手をかけた。ドアを開けた。父親が中に入った。まことが続いた。
そこでまことが目にしたのは、壁にかけられた学ランだった。まことは止まった。え。なにこれ。やっぱりだ。
「まことよ。よかったな。やっと学ランが着られるのじゃ。お前も男じゃなあ」
まことはこぶしを握り締めた。涙がほほをつたった。
「ほお、そんなにうれしいか。よいか、男でも泣いていいのじゃぞ」
「こんなこったろうと思ったぜ」
と、まこと。
まことは振り返って、廊下をかけた。
「どうしたまこと」
父親は階段を上った。二階に部屋があるのだ。まことも続いた。まことはうきうきしていた。
二階。廊下が続いている。右側にドアがあり、突き当りにドアがある。
父親が歩いて行く。右側のドアを通り過ぎる。
「え、おやじ、おやじの部屋にあるんじゃねえの」
父親はだまっている。
「お、おい、そっちは私の部屋だぜ」
「・・・・・・」
「お、おい、私の部屋に入ったんじゃあるめえ」
父親は、ドアのドアノブに触った。
「おい!」
と、まことは大声をあげた。
「こらこら、年頃の娘の部屋にはいんじゃねえ」
父親が振り向いていった。
「ほほお、そうか」
「え」
「おぬしもそろそろ年頃か」
「え」
「まあ、年頃の男はそういう本を隠してたりするからなあ」
「て、てめえ、やっぱり男扱いか。そういう本てどういう本だよ」
「なんていうかあ、女性の写真とか」
「ああ、なんだよそれ」
まことは父親につきをいれた。父親は軽くよける。
「さては図星じゃな」
「て、てめええええええ」
「お前も色気づいたのう」
まことはつきをいれつづける。
「制服着たくないのか」
まことはつきをやめた。
「そうそう。憧れのセーラー服」
父親は微笑んだ。
「じゃあ、見せてやろう」
といって父親はドアノブに手をかけた。ドアを開けた。父親が中に入った。まことが続いた。
そこでまことが目にしたのは、壁にかけられた学ランだった。まことは止まった。え。なにこれ。やっぱりだ。
「まことよ。よかったな。やっと学ランが着られるのじゃ。お前も男じゃなあ」
まことはこぶしを握り締めた。涙がほほをつたった。
「ほお、そんなにうれしいか。よいか、男でも泣いていいのじゃぞ」
「こんなこったろうと思ったぜ」
と、まこと。
まことは振り返って、廊下をかけた。
「どうしたまこと」