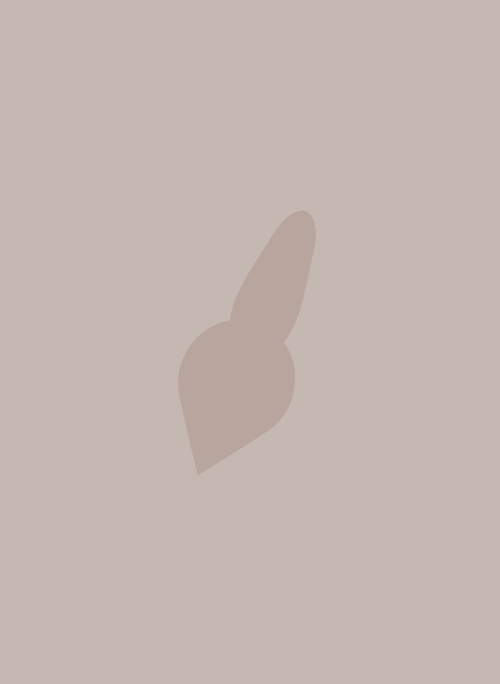あたしが、この部屋に足を運ぶ様になったいきさつはだいたいそんな感じだ。
「ただいまー」
高く澄んだ声が玄関から聞こえてきた。
リビングの扉のガラスから、顔を覗かせると綾子さんが高いヒールの靴を乱暴に脱ぎ捨てたところだった。
「あー疲れたー」
綾子さんはリビングに入ってきてそうそうソファーにもたれた。
あたしはすっと立ち上がり冷蔵庫からお茶をとりだしコップに注いで綾子さんのもとへ持っていく。
「はい」
「ありがとー。りく」
綾子さんは笑うともともと釣り上がっている猫目がさらに釣り上がる。
丁寧に巻かれた髪の毛からなのか、透き通るほど白い肌からなのか、綾子さんからはいつもほのかに甘酸っぱい良い匂いがする。
綾子さんいわく、自分の匂いをオトコに焼き付けるそうだ。
『そうやって、じわじわ蝕んでいくの。あたしを忘れさせないために』
いつだったかそんなことを色香を放つ顔で言っていた。
これが愛人契約で生計をたてる人間なのだ、と感心さえさせてしまう。
そりゃあ、こんなどの角度から見ても申し分のない美人になら貢がずにはいられなくなるのだろう。