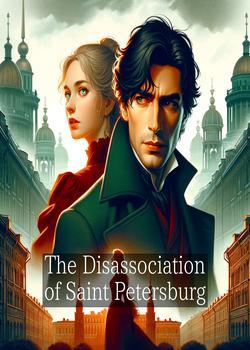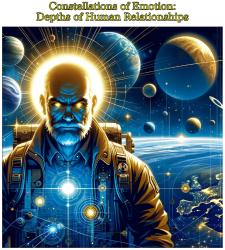。早く支度しないと遅刻しちゃいますよ。いいんですか、社長」
私は彼の肩を揺すって起こそうとした。彼はなかなか目を覚ましてくれなかった。
私はもう一度、彼の名前を呼んだ。そして、彼の頬を軽く叩いた。
彼はようやく目を開けるとゆっくりと体を起こした。
「ああ、おはよう……。うん、大丈夫だよ。ちゃんと覚えてる。でも、もう少しだけ待ってくれないかい。すぐ着替えるから」
彼はそう言うと、のろのろとした動作でベッドから抜け出した。そして、スーツを手に取ると、のそのそと寝室から出ていった。
しばらくして彼が戻ってきた。そして、テーブルの上に置いてあった眼鏡をかけると、椅子に座って新聞を読み始める。
その様子を見て、ふと疑問が浮かび上がった。
「あの、いつも気になってたんだけど、その眼鏡って伊達なんですよね。どうしてわざわざ度入りのものをかけてるんですか?」
私がそう尋ねると、彼は不思議そうに首を傾げた。
「ん、これのことかい。これはね、ファッションなんだよ。気分を変えたいときにかけるようにしてるんだ。それにこれなら君に素顔を見られなくて済むから都合がいいと思ってね。でも、よく考えたら意味がないよね。君はもう僕の顔なんて見飽きるほどに見てきているのだから」
彼は苦笑いしながら言った。私は思わずドキッとする。
確かに私は彼の顔が好きだ。というより、彼以外の男性に興味を持てなかった。私は小さい頃から異性に対して関心を持つことができなかった。
でも、それはある意味では幸せなことだったかもしれない。だって、誰かと恋愛をするということは相手の嫌な
「――ねえ、昨日のことだけど、私、変なこととかしてないわよね。ちょっと酔ってたせいもあって記憶が曖昧なの。もし何か失礼なことをしていたら謝るから教えてくれる?」
彼女は不安そうな顔で訊ねてきた。
僕は咄嵯に答えようとしたが、すぐに思い留まった。彼女がどこまで覚えているのか分からない以上、下手なことは言わない方がいいと思ったのだ。ただ、それでも言えることがあるとすれば、
「う、ううん、全然、気にすることなんてなかったよ。むしろ楽しかったっていうかさ。だから、こっちこそお礼を言いたいくらいで……。あ、そうだ。また今度一緒にどこか行かない。今度はもっとゆっくりできるところへ行こうよ。たとえば温泉旅行なんてどうかな。それだったら、きっと疲れも取れるだろうしさ」
そんな提案をした途端、彼女の顔がパッと明るくなった。僕がホッとしていると、……そんなのダメに決まってんじゃない どこからかそんな声が聞こえてきた。
えっ、誰の声だろう 周りを見回したが誰もいない。しかし、耳を澄ますと再び同じ声が響いてきた。……そんなの許さないから でも、周りには彼女しかいないはずだ。でも、彼女は明らかに違う場所から話しかけてきていた。まるで、すぐ近くにいるみたいな感じだった。まさか、幽霊? 僕は恐くなって逃げ出したくなった。でも、なぜか体が動かない。それどころか意識まで遠退いていく感じがした。
すると、彼女は僕の目の前に立っていた。
その瞬間、僕の心臓は激しく高鳴った。顔は真っ赤に染まり、全身が熱くなるのを感じた。
彼女はとても綺麗だ。スタイルもいいし、顔立ちも整っている。
でも、一番好きなのは瞳だ。彼女の目は宝石のように輝いている。その輝きに魅了された僕は彼女の虜になってしまった。だから、いつの日からか彼女のことが頭から離れなくなった。
でも、彼女の方はそうでもなかったみたいで、他の男とばかり付き合っていた。だから、僕なんかじゃ無理だと諦めかけていた。
そんなある日、僕は彼女と再会した。
その日は仕事でミスをして上司に怒られてしまった。それで落ち込んだまま帰宅していたときのことだった。
「あれ、もしかして佐藤くん?」
後ろを振り返ると彼女が立っていた。
「あ、やっぱり佐藤くんだ。どうしたの、こんなところで。もしかして、今帰り?」
「う、うん。そういう君はどうしてここに?」
「えっ、どうしてって、ここ私の家の近くだから。それよりさ、良かったら家に寄っていかない」
彼女は微笑みながら言った。「私、ちょうど今、友達と一緒にお茶でもしようと思ってたんだけど、佐藤くんも一緒に来ない?」
驚きと喜びが入り混じった感情が僕を包み込んだ。彼女が誘ってくれるなんて、夢のようだった。
「本当にいいのか?僕、ちょっと気が重いんだけど…」
彼女は優しく笑って言った。「大丈夫、気にしないで。友達もいるし、楽しい時間になるよ。」
彼女の言葉に背中を押され、僕は彼女の家に向かった。その日から、僕と彼女の関係は少しずつ変わっていった。
しかし、その後の出来事が僕の人生を一変させることになるとは、まだ知る由もなかった。
---
暗く冷えきった部屋の中で、主人公と彼女は医師の前に座っていた。壁時計の秒針が静かに時を刻む中、医師は深い息を一つつき、二人に目を向けた。
「結論から言うと、お二人が体験している症状は、サンクトペテルブルク離人症という疾患によるものと考えられます。」
主人公と彼女は驚きの目で医師を見つめた。
「サンクトペテルブルク離人症?」彼女が繰り返した。
医師は頷きながら説明を始めた。「19世紀末、サンクトペテルブルクのある医者が初めて報告した症状です。患者は、人々の微細な変化に極端に敏感になり、自分や他者が変わってしまったという感覚に苛まれます。髪型や体つき、声のトーンなどの些細な違いを捉え、それを理由に他者が別人であると感じるのです。」
主人公は医師の言葉を聞きながら、彼女との再会時の違和感を思い出していた。彼女もまた、主人公の変わりゆく姿に戸惑っていたのだろう。
「この症状は、強迫神経症のような強迫的な思考や行動に基づいている部分があります。しかし、サンクトペテルブルク離人症は、人々の身体や存在そのものに対する認識の歪みが中心となっています。」
彼女が小さく声を挙げた。「それって、私たちが感じている違和感や疑念、それがこの病気のせいだってこと?」
医師は優しく頷いた。「はい、その通りです。しかし、この症状は治療が可能です。カウンセリングや認知行動療法を通じて、症状を緩和させることができるでしょう。」
主人公は彼女の手を握りしめた。「じゃあ、私たち…」
彼女は微笑みながら言った。「大丈夫。一緒に乗り越えていこう。」
医師は二人の手を見て微笑んだ。「心配しないでください。お二人なら、きっとこの症状を乗り越えることができるでしょう。」
部屋の中は静かに時が流れ、二人は新たな希望を胸に、未来へと歩み始めた。