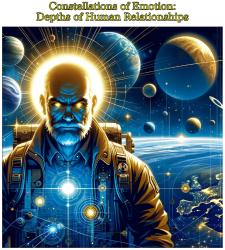。
そんなある日のことだった。学校から帰っている途中、道端に小さなダンボール箱が置かれていた。中を覗くと白い毛布が敷いてあり、その中に猫が入っていた。どうやら捨てられてしまったらしい。雨に濡れていたので弱っているのは明らかだった。でも、このまま見過ごすわけにはいかない。
とりあえず家に連れて帰ったものの、どうやって飼ってあげればいいのか分からなかったので母に訊ねた。
翌日になると猫は元気になっていた。餌を与えると勢いよく食べた。その後、体を洗ってあげたり、ブラッシングをしたりといろいろお世話をしてあげた。猫は嫌がる素振りは見せなかったが、心を許している感じもしなかった。やっぱりまだ怯えているみたいだ。だからなのか、時折、不安そうな顔で見つめてくるので可愛くてしょうがなかった。そうやって見つめられるとついキスしたくなる。でも、嫌われたくはないのでグッと堪えることにした。そして夜になったら布団に入れてあげることにした。最初は戸惑っていたけれど、やがて安心したのか、そのままスヤスヤ眠ってしまっていた。その姿は天使のように見えた。その寝顔を見た瞬間、心を奪われてしまったのは言うまでもなかった。
次の日も朝から猫のお世話をすることにした。ミルクを飲ませたり、排せつを処理したりした。また、遊び道具を作ってあげて、退屈しないように努めてあげた。最初は興味を持っていなかったが、やがて遊ぶようになった。どうも気に入ってくれたようで、一生懸命おもちゃにじゃれつき、「ニャア!」と鳴いていた。
本当にかわいい生き物だと思った。ずっと眺めていたくなるくらいである。ただ、困ったこともあった。この子の性別がまだ判明していないのである。もしオスであれば去勢手術をしないといけないのだが、それに関しては少し抵抗感があった。できればこのまま成長させてやりたいので、いずれ分かることだろうと深く気にしないことにした。
しかし、三日経っても四日経っても、この子から性別が明かされることはなかった。この子がメスである可能性もあるし、オスである可能性もある。どちらにしても、これ以上待ち続けるのは無駄だと思ったので、獣医に相談することにした。獣医は性別を確認するために検査を行ってくれた。そして、結果はオスであることが判明した。これで安心して去勢手術をすることができる。獣医から手術の日程を決めるように言われたので、早速手続きを進めることにした。
手術当日、猫を連れて獣医院に向かった。猫は不安そうな表情を浮かべていたが、私はしっかりと彼を支えていた。手術が終わるまで待つ間、私は獣医に手術の詳細を尋ねた。獣医は丁寧に説明してくれたが、私は手術のことよりも、猫が無事であることを祈るばかりだった。
手術が終わり、猫を連れて帰宅した。彼はまだ麻酔が残っているのか、少しグロッキーな様子だった。私は彼を優しく抱きしめながら、「大丈夫だよ、もうすぐ元気になるから」と囁いた。
数日後、彼は元気になっていた。去勢手術の影響も少しずつ薄れ、以前と変わらない活発な姿勢を見せてくれた。私は彼の回復を喜びながら、彼との時間を大切に過ごすことを決めた。
それからというもの、私たちはますます絆を深めていった。彼は私の心の支えとなり、私は彼の成長を見守ることで自分自身も成長していくことができた。彼との出会いが私の人生を豊かにしてくれたのだ。
そして、ある日のこと。私は彼と一緒にお散歩している最中、ふと彼の目に異変を感じた。彼は私に対して懇願するような目でこちらを見つめていた。私は彼の気持ちを察し、彼を抱きしめながら「どうしたの?」と尋ねた。
彼は微かに尻尾を振りながら、私に向かって鳴き声を上げた。私は彼の気持ちを理解し、彼を連れて行く先を変えることにした。彼が行きたい場所へと向かって歩き出すと、彼はますます興奮し始めた。私は彼と一緒に走り回り、彼の喜ぶ姿を見ることで自分も幸せな気持ちになった。
彼との時間は私にとって貴重なものだ。彼がいることで私の日常が輝きを増し、心に安らぎを与えてくれる。彼は私の大切な存在であり、これからもずっと一緒にいたいと心から思っている。
この先も彼との出会いが私の人生にとって大きな意味を持つことは間違いない。彼との絆を深めながら、私は自分自身を成長させていくことができるだろう。彼との未来に期待を抱きながら、私は彼と共に歩んでいくのだった。
「俺の名前は佐藤隆二。ごく普通のサラリーマンをやっていて今は35歳。妻と二人暮らし。趣味は映画鑑賞。あと最近はゲームも始めたかな」
「へえー、そうなんだ。ちなみにどんな映画を観るの?」
彼女は俺のプロフィールに興味を持ったのか尋ねてきた。
俺は答える前に彼女の方に視線を向けた。そこには当然のことながら、にこやかな表情を浮かべている彼女がいるわけで……。俺は一瞬、言葉を失ってしまった
「……ねえ、どうして黙っちゃうの?」
彼女の反応を見る限りどうも伝わっていないようだ。
「あ、いや、その……。あんまりこういうの喋るの得意じゃないからさ……」……我ながら情けないと思う そう思う一方で彼女は笑みを絶やすことなく俺を見続けている
「……じゃあ今度はあなたの番よ。ほら、自己紹介してくれる?」
「あ、はい……」
俺は観念するかのように口を開く。
彼女の顔は浮かない。
「な、何? 何か問題でもあるの!? はっきり言ってくれる! 怒らないからさ!!」
すると突然、彼女は大きく口を開けて叫んだ。
そんなことないよって言いたかったけど言えなかった。何しろ彼女の剣幕が凄まじかったからだ。こんなの生まれて初めての経験だったので動揺を隠しきれなかった。おかげで喉元に熱いものが込み上げてきそうになった。なので、なんとか我慢するしかないのであった。
しかし
「私、何かマズいこと聞いちゃったのかな……」
彼女は心配そうに僕の顔色を窺っていた。……そんなことはないと慌ててフォローを入れる。でも、彼女の方から見れば今の僕は挙動不審にしか見えないのではないだろうか。……そう思うとますます落ち込んでしまう 彼女は僕を気遣ってくれたのかもしれない。何だか申し訳ないことをしたなと思う。でも、正直 何も言えない自分が情けなかった
「ごめんなさい……余計なこと聞いて……あなたは何も悪くないわ。悪いのは……全部、私の方なんだから……!」
彼女は震えていた。今にも泣き出しそうだった。……そんな彼女を見ていると、自分の胸が締め付けられるような感覚を覚えた そんな顔をさせたくない 僕は無意識のうちに彼女に手を伸ばしかけていた。しかし、途中でハッとして動きを止める 僕はなんて馬鹿なことをしようとしたのだろう こんな気持ちになったのは久し
「―――さん、起きてください。もう朝ですよ。今日は大事な会議があるんでしょ