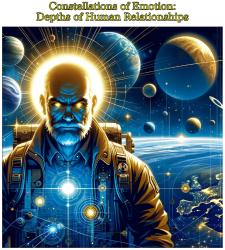「ところであなたはどんな願い事をするつもりだったんですか?」
「えっと、それは……秘密です」
「えぇ~教えてくださいよぉ」
俺がしつこく食い下がると、女性は恥ずかしげに口を開いた。
「……内緒にしてもらえますか?」
「うん、わかった。誰にも言わないよ」
俺は真面目な顔をして答えると、女性は小さく息を吐いて話し始めた。
「私は今年の文化祭を最後に転校することになったんです。それで、最後の文化祭だけはみんなと同じ場所で楽しみたくて……」
女性はどこか寂しげな目をしながら遠くを見つめていた。もしかしたら彼女は自分の学校で最後の文化祭を迎えられなかったのかもしれない。だからこそ文化祭をやりたかったんだろう。俺は彼女の気持ちを考えると、何だか胸が締め付けられるような思いがした。きっと俺よりもずっと辛かったに違いない。そう思うと無性に目の前にいる女性のことを抱きしめてあげたくなったが、俺は必死の理性を振り絞ってそれを抑え込んだ。こんなことをしてしまえば不審者に思われてしまう。今はただ隣で話をすることしかできないが、いつか彼女が心から文化祭を楽しむことができたらと思う。そのためにも俺ができることは一つだけだ。俺は彼女に優しく微笑みかけると、明るい声で言った。
「ねぇ知ってる?ハロウィンの夜には仮装をして近所の家を訪ね歩くっていう風習があるんだけど、それは悪い精霊や魔女たちから身を守るために行われるものなんだ。そしてその時に『トリック・オア・トリート』という言葉をかけるとお菓子をもらえるんだよ。これは子供だけの特権だけど、大人になった今でも大切な人と共有したい思い出になるはずだ。だから来年、もし良かったら一緒にハロウィンの行事に参加してみないかい?その時までにお互いの夢をかなえられたらいいな」
俺の言葉に女性は目を輝かせると、「約束します!」と言って右手を差し出してきた。俺はその手をしっかり握りしめると、「よろしくね!」と笑いかけた。