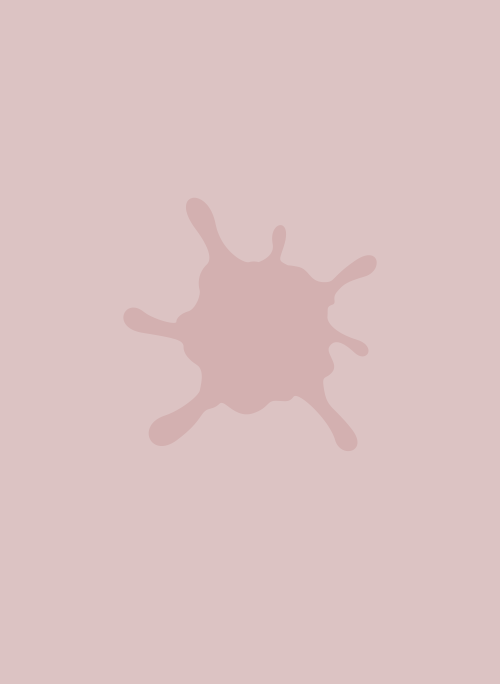――――――…生まれたときから、誰にも受け入れられないのが当たり前だった。
人が当たり前のように持っている優しさ、愛情、温もり。
それらは僕にとって幻想で、決して手の届かないものだった。
手を伸ばしても追いすがろうとしても、掴むことは出来ない。
来る日も来る日も、僕は同族に罵られ、石を投げられてきた。
「こっちに来るな、バケモノめ!」
「なんて恐ろしい姿だ。まさに罪の姿そのものだ」
「お前のような生き物が、この世に生まれてしまったことが間違いだったんだ」
「生きてきて恥ずかしいと思わないのか?」
この世のありとあらゆる汚い言葉をぶつけられ、蔑まれ続ける。
群れの中から阻害され、一人ぼっちでふらふらと彷徨うしかない。
自分の何が悪いのか、何故そんな風に傷つけられるのか、幼い頃の僕には分からなかった。
誰も説明してくれなかった。
でも、水面に映る自分の姿を見れば、僕がいじめられる理由は明らかだった。
この異形の姿を見れば、誰だって近寄りたくないに決まってる。
成長するにつれ、段々と心が麻痺していく。
どんな言葉で傷つけられようとも、何も感じなくなっていく。
殴られても、石を投げられても、痛くない。
一人ぼっちで生きていくのが当たり前。誰にも受け入れられないのが当たり前。
僕はこうして、永遠に孤独の中で生きていく。
望もうと望むまいと、それ以外に、僕に選択肢などなかった。
何も感じなくて良い。全て忘れてしまえば良い。
時折、息を吹き返したように傷口がぱっくりと開いて、酷く痛むこともあるけれど。
感情に蓋をしよう。何を言われても何も感じないように。
鏡に映る自分の姿に絶望しないように。
一人ぼっちで生きていけるように。
…その、はずだったのに。
「あなたと一緒なら、私はもう寂しいことなんてないわ」
僕は出会ってしまった。自分の孤独を埋めてくれる存在に。
これこそ、僕の真の過ちだったのだ。
人が当たり前のように持っている優しさ、愛情、温もり。
それらは僕にとって幻想で、決して手の届かないものだった。
手を伸ばしても追いすがろうとしても、掴むことは出来ない。
来る日も来る日も、僕は同族に罵られ、石を投げられてきた。
「こっちに来るな、バケモノめ!」
「なんて恐ろしい姿だ。まさに罪の姿そのものだ」
「お前のような生き物が、この世に生まれてしまったことが間違いだったんだ」
「生きてきて恥ずかしいと思わないのか?」
この世のありとあらゆる汚い言葉をぶつけられ、蔑まれ続ける。
群れの中から阻害され、一人ぼっちでふらふらと彷徨うしかない。
自分の何が悪いのか、何故そんな風に傷つけられるのか、幼い頃の僕には分からなかった。
誰も説明してくれなかった。
でも、水面に映る自分の姿を見れば、僕がいじめられる理由は明らかだった。
この異形の姿を見れば、誰だって近寄りたくないに決まってる。
成長するにつれ、段々と心が麻痺していく。
どんな言葉で傷つけられようとも、何も感じなくなっていく。
殴られても、石を投げられても、痛くない。
一人ぼっちで生きていくのが当たり前。誰にも受け入れられないのが当たり前。
僕はこうして、永遠に孤独の中で生きていく。
望もうと望むまいと、それ以外に、僕に選択肢などなかった。
何も感じなくて良い。全て忘れてしまえば良い。
時折、息を吹き返したように傷口がぱっくりと開いて、酷く痛むこともあるけれど。
感情に蓋をしよう。何を言われても何も感じないように。
鏡に映る自分の姿に絶望しないように。
一人ぼっちで生きていけるように。
…その、はずだったのに。
「あなたと一緒なら、私はもう寂しいことなんてないわ」
僕は出会ってしまった。自分の孤独を埋めてくれる存在に。
これこそ、僕の真の過ちだったのだ。