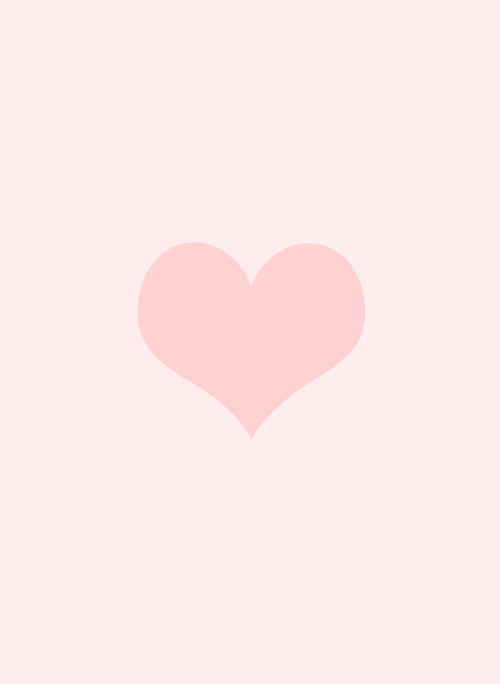――――――…スクルトが、僕に殺される未来を知っていた?
有り得る話ではある。
知っていたのに、スクルトは逃げなかった。
何故?
僕に打ち明けても、逃げ出しても変わらない、『赤』い未来だったから?
でも、本当に最期の瞬間に僕を憎んでいたのなら、その未来が見えた時点で、僕を問い詰めたはずだ。
「お前に殺される未来が見えたんだが、これはどういうことだ」って。
それなのにスクルトは、それをしなかった。
自分の人生の終わりが見えても、逃げることも隠れることも臆することもなく、ただその未来を受け入れた…。
僕に殺されるという未来を。
「思い出してください。あなたの愛した人の最期を。スクルトさんは本当に…あなたを憎んでいたんですか?」
「…それは…」
僕は再度、記憶を手繰り寄せた。
思い出したら、胸が張り裂けそうになる記憶。
だから蓋をして、鍵をして、決して開けることなくしまい込んだ。
二度と思い出したくない記憶だった。
記憶の鍵を開けて、蓋を開けて中身を引っ張り出す。
それは僕にとって、酷く辛いことだった。
でも、もしシュニィ・ルシェリートの言っていることが正しいのだとしたら。
僕はこれまでずっと、自分の記憶を歪めて…。
あの日…あの日僕は、突然内なる衝動に駆られて、それから意識が遠くなって…。
自分の身体のはずなのに、まるで自分のものじゃないような感覚がして…。
気がついたら、この手でスクルトを…。
「…っ…!」
その瞬間を思い出して、僕の目の前に恐ろしい記憶がフラッシュバックした。
まるで今現実に起きていることのように、鮮明に情景が思い浮かぶ。
あのときスクルトは僕の前にいて。
豹変した僕を見ても、少しも驚いた様子はなくて…。
僕の爪がスクルトを引き裂くその瞬間。
スクルトの顔は、憎しみと怒りに歪んでいた…。
…。
…。
…本当に?
「思い出してください。本当は何があったのか、よく思い出すんです」
シュニィ・ルシェリートの声が、頭の中に響いた。
思い出したくない。
思い出したら辛くて堪らなくなるから、必死に記憶に蓋をし続けた…。
…でも。
「あなたの愛する人が、最期にあなたに何を伝えようとしたのか…。分かってあげてください」
と、シュニィ・ルシェリートは言った。
スクルトが…最期に、僕に何を言おうとしたのか。
僕に何を伝えようとしたのか。
…それは…。
「…!」
目の前に、スクルトの最期の瞬間が浮かび上がった。
有り得る話ではある。
知っていたのに、スクルトは逃げなかった。
何故?
僕に打ち明けても、逃げ出しても変わらない、『赤』い未来だったから?
でも、本当に最期の瞬間に僕を憎んでいたのなら、その未来が見えた時点で、僕を問い詰めたはずだ。
「お前に殺される未来が見えたんだが、これはどういうことだ」って。
それなのにスクルトは、それをしなかった。
自分の人生の終わりが見えても、逃げることも隠れることも臆することもなく、ただその未来を受け入れた…。
僕に殺されるという未来を。
「思い出してください。あなたの愛した人の最期を。スクルトさんは本当に…あなたを憎んでいたんですか?」
「…それは…」
僕は再度、記憶を手繰り寄せた。
思い出したら、胸が張り裂けそうになる記憶。
だから蓋をして、鍵をして、決して開けることなくしまい込んだ。
二度と思い出したくない記憶だった。
記憶の鍵を開けて、蓋を開けて中身を引っ張り出す。
それは僕にとって、酷く辛いことだった。
でも、もしシュニィ・ルシェリートの言っていることが正しいのだとしたら。
僕はこれまでずっと、自分の記憶を歪めて…。
あの日…あの日僕は、突然内なる衝動に駆られて、それから意識が遠くなって…。
自分の身体のはずなのに、まるで自分のものじゃないような感覚がして…。
気がついたら、この手でスクルトを…。
「…っ…!」
その瞬間を思い出して、僕の目の前に恐ろしい記憶がフラッシュバックした。
まるで今現実に起きていることのように、鮮明に情景が思い浮かぶ。
あのときスクルトは僕の前にいて。
豹変した僕を見ても、少しも驚いた様子はなくて…。
僕の爪がスクルトを引き裂くその瞬間。
スクルトの顔は、憎しみと怒りに歪んでいた…。
…。
…。
…本当に?
「思い出してください。本当は何があったのか、よく思い出すんです」
シュニィ・ルシェリートの声が、頭の中に響いた。
思い出したくない。
思い出したら辛くて堪らなくなるから、必死に記憶に蓋をし続けた…。
…でも。
「あなたの愛する人が、最期にあなたに何を伝えようとしたのか…。分かってあげてください」
と、シュニィ・ルシェリートは言った。
スクルトが…最期に、僕に何を言おうとしたのか。
僕に何を伝えようとしたのか。
…それは…。
「…!」
目の前に、スクルトの最期の瞬間が浮かび上がった。