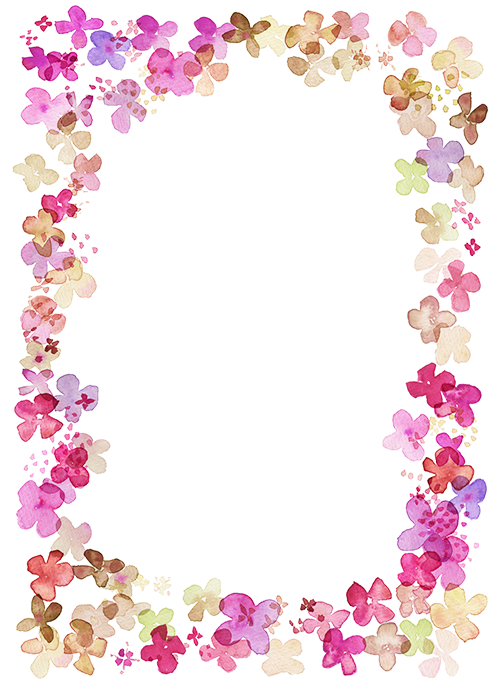それにそんな行為があったかと思うとただでさえ許せないというのに、はらわたが煮え繰り返りそうだ。
けどこれも必要なことだと自分に言い聞かせ、彼女に視線を向ける。
リーベは先程の恐怖や不安で一杯といった表情から、不思議そうなものに変わっていた。
この様子だとあの男にそういったことはされていないのかもしれない。
いや、彼女に知識がないだけで実際は、なんてこともあり得るのか。
彼女は首を傾げながら俺を見る。
「性的なことって?」
「体を触られたり、無理矢理迫られたりしたことはなかったか?」
少尉が彼女の質問に答える。
リーベはぴんとこないようで、やはり不思議そうに首を傾げていた。
「その様子だとそういう行為はなかったようだな。変なことを聞いてすまなかった」
ひとまず彼女があの男にそういったことをされていなかったことに安堵する。
だからといって、あれだけリーベのことを傷つけた男のことを許そうだなんて思う筈がないが。
「これだけ聞ければいいだろう。リーベ話してくれてありがとう。疲れただろうし、今日はもう帰っていいぞ」
少尉がリーベに優しく微笑みかける。
彼女の体の震えもおさまっていたので、彼の言葉に甘えて、今日はもう帰宅することにする。
けどこれも必要なことだと自分に言い聞かせ、彼女に視線を向ける。
リーベは先程の恐怖や不安で一杯といった表情から、不思議そうなものに変わっていた。
この様子だとあの男にそういったことはされていないのかもしれない。
いや、彼女に知識がないだけで実際は、なんてこともあり得るのか。
彼女は首を傾げながら俺を見る。
「性的なことって?」
「体を触られたり、無理矢理迫られたりしたことはなかったか?」
少尉が彼女の質問に答える。
リーベはぴんとこないようで、やはり不思議そうに首を傾げていた。
「その様子だとそういう行為はなかったようだな。変なことを聞いてすまなかった」
ひとまず彼女があの男にそういったことをされていなかったことに安堵する。
だからといって、あれだけリーベのことを傷つけた男のことを許そうだなんて思う筈がないが。
「これだけ聞ければいいだろう。リーベ話してくれてありがとう。疲れただろうし、今日はもう帰っていいぞ」
少尉がリーベに優しく微笑みかける。
彼女の体の震えもおさまっていたので、彼の言葉に甘えて、今日はもう帰宅することにする。