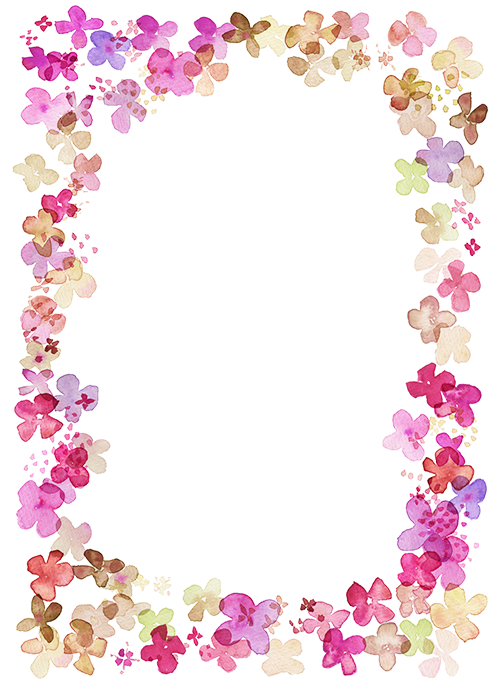リーベがついてくる気配を感じなかったので振り向くと、きらきらとした目で俺の部屋を見渡していた。
あまりじろじろ見られるのはなんだか恥ずかしいが、その様子が可愛くて笑みが溢れる。
「何か気になるものでもあった?」
「あの部屋には本しかなかったから、どれも新鮮に感じて楽しいの」
あんな劣悪な環境にいたのだから、俺のシンプルな部屋でも物珍しく感じるのだろう。
彼女がいたところは窓もなければ、掃除もちゃんとされていないようで、やけに埃っぽい部屋というよりも物置きと言ったほうが正しいようなところ。
リーベが妖精でなければ、すぐに病気になっていたことだろう。
それを考えると心が痛む。
そんな環境から彼女を助け出すことができて本当によかった。
俺が暗い顔をしたのに気づいたらしい彼女に微笑みかける。
「リーベが楽しそうならよかった。これから出かけるから支度しようか」
「どこに行くの?」
「俺の職場だよ」
“俺の職場”という言葉を聞くと、彼女はぱっ、と表情を明るくさせる。
なんだか嬉しそうで可愛い。
あまりじろじろ見られるのはなんだか恥ずかしいが、その様子が可愛くて笑みが溢れる。
「何か気になるものでもあった?」
「あの部屋には本しかなかったから、どれも新鮮に感じて楽しいの」
あんな劣悪な環境にいたのだから、俺のシンプルな部屋でも物珍しく感じるのだろう。
彼女がいたところは窓もなければ、掃除もちゃんとされていないようで、やけに埃っぽい部屋というよりも物置きと言ったほうが正しいようなところ。
リーベが妖精でなければ、すぐに病気になっていたことだろう。
それを考えると心が痛む。
そんな環境から彼女を助け出すことができて本当によかった。
俺が暗い顔をしたのに気づいたらしい彼女に微笑みかける。
「リーベが楽しそうならよかった。これから出かけるから支度しようか」
「どこに行くの?」
「俺の職場だよ」
“俺の職場”という言葉を聞くと、彼女はぱっ、と表情を明るくさせる。
なんだか嬉しそうで可愛い。